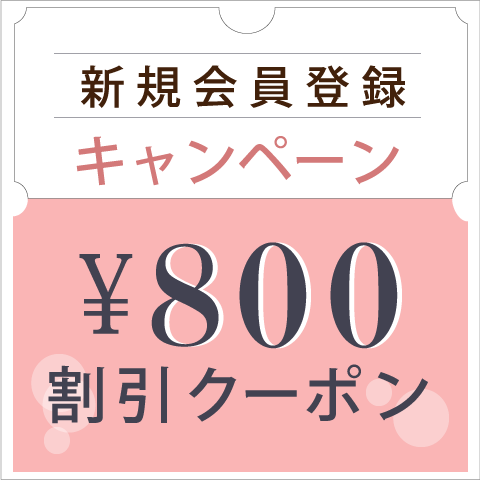今年の夏も温暖化のせいで、各地で40度近い気温を記録しているイタリア。
全国のジェラート屋さんの前には長い行列ができ、冷たくクリーミーなジェラートで暑さを癒そうとする人たちであふれています。
みんなが大好きなジェラートは今やもう夏の風物詩ではなく、すっかり年間を通じて食べるものとしての地位を築いています。
メロンやイチゴなどのさっぱり季節のフルーツ系か、チョコレートやピスタチオの濃厚タイプ、生クリームやチーズなどのミルク系を数種盛りにして、カップで食べるか、コーンで食べるか、はたまたブリオッシュに挟むのか。
こどもだけでなく、お店の前には笑ってしまうほど真剣な顔をして悩んでいる大人たちが見られます。
イタリアでは、だれもがひいきにしているジェラート屋さんがある一方で、新しくオープンしたお店や評判のいいジェラテリアにも足を運んでいる人が多いです。
“イタリアのミシュラン”とも言われるグルメガイド『ガンベロ・ロッソ』は、毎年ジェラテリアだけを特集したガイドブックを発行していて、特に美味しいと評価されたお店には「三つ星」ならぬ「三つのコーン」のマークがつけられ、毎年そのランキングが話題になります。
美味しいレストランと同じくらい、ジェラテリアもみんなの注目の的なんです。
本物の味を見抜けるか?“神聖なジェラート”をめぐる熱い論争|ヒサタニミカさんのイタリアレポート
【私のお気に入りジェラテリア】
毎日食べるほどジェラートが好きな私の心からのおすすめジェラテリアは3つあります。

まず一つめは、近所にある「PANNA & CO. パンナ・エ・コ」。
ジェラート・アルティジャナーレ(職人による手作りジェラート)の王道のようなお店で、旬の素材のみを使って店内で製造しています。特にフルーツ系のフレーバーは絶品で、まるで果物そのもの、いや、それ以上のおいしさ。
夏には「桃とワイン」や「バジリコとレモン(右上写真)」「ラズベリー」といった、さっぱり系の味がお気に入りです。

素材へのこだわりが強く、収穫期が限られる果物を使ったジェラートは、たった1週間だけしか販売されないことも。
中には、ジェラタイオ(ジェラート職人)のアレッサンドロさんが自宅の庭で採れたスモモを使ったフレーバーもありました。
ローマに2店舗展開しており、毎日アレッサンドロさんが小さなラボラトリーでせっせとジェラートを仕込んでいます。

次は、ローマで最も有名なジェラテリアのひとつ「OTALEG オタレグ」。
日本のジェラートイベントにもゲストとして招かれているマルコさんのお店で、彼は子どもの頃からのジェラート愛をそのまま職業にした、情熱あふれるジェラタイオ。
彼のジェラートはとにかくフレーバーが独創的で、ゴルゴンゾーラチーズやアスパラガスなどの野菜系から、カレーなどのスパイス系まで、どんな素材でも彼の手にかかれば、驚くほどエレガントでおいしいジェラートに仕上がります。店内のラボで毎日夜中に、その日売る分だけを新鮮に製造していて、訪れるたびに新しいフレーバーに出会えるのも楽しみの一つ。「客ウケしない、絶対売れないと分かっていても、どうしても作ってみたくなるんだよね」と笑いながら話してくれるマルコさん。まさに“ジェラート愛”のかたまりです。

そして最後は、シチリア・パレルモの「CAPPADONIA カッパドニア」。
元イタリアジェラート協会の会長でもあるアントニオ・カッパドニアさんのお店。
ここで食べたピスタチオのジェラート(右上写真)は、一生忘れられないすばらしい味でした。想像していたような鮮やかな緑ではなく、自然なベージュ色。これが無着色、無香料のピスタチオなんだと実感します。ローマで食べるピスタチオジェラートとは別物で、素材の力強さとフレッシュさが違います。思い出すたびに、またパレルモまで行きたくなるほどです。
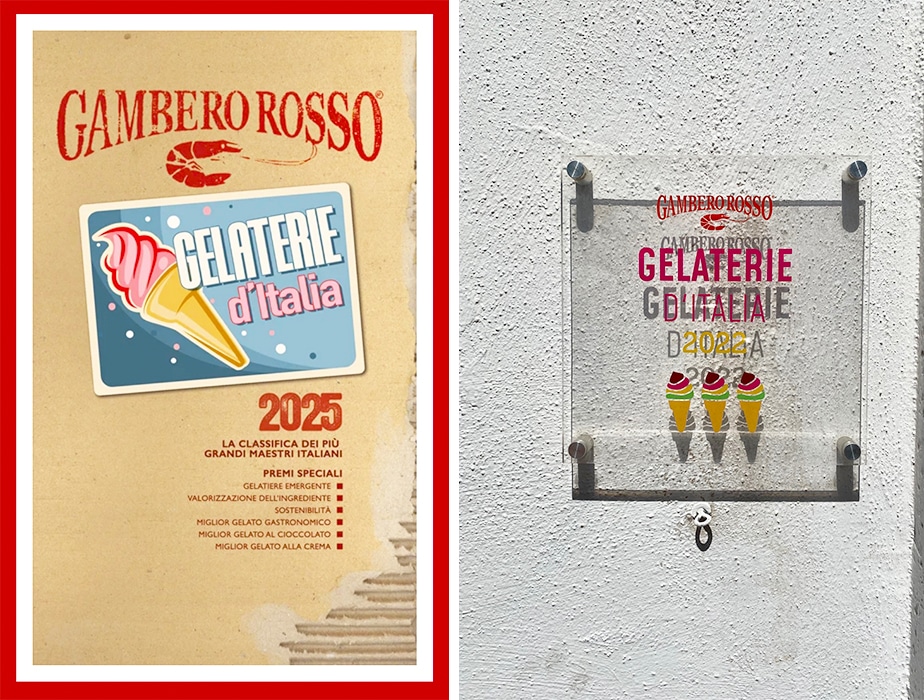
ちなみに、これら3店舗すべてがガンベロ・ロッソのジェラテリアガイドで「3つのコーン」を獲得しています。共通するのは、添加物を一切使わず、旬の素材にこだわり、フルーツ系には可能な限り砂糖を使わないというスタイル。
まさに「アルティジャナーレ(職人製)」のジェラートです。
【アルティジャナーレの明確な定義づけがないという問題】
イタリア国内にはジェラートを販売する店舗が3万9,000軒あり、そのうち専門のジェラテリアが9,000軒。年間売上はイタリア国内のオリーブオイルのそれに近づきつつあるほどで、なんと30億ユーロ(約5,100億円)にも上ります。
さらに、原材料や機械、ショーケースなどを製造する関連企業の売上額を加えると、相当な経済規模を持つ産業です。
それにもかかわらず「明確な定義づけをする法律」は、いまだに影も形もないまま。粉にミルクや水を追加するだけでできあがる袋入り加工ジェラート製品の増加も著しく、そのジェラテリアと果物やチョコレートなど原材料の仕入れから行っているアルティジャナーレのジェラテリアは似て非なるものがあります。
もちろんどちらもそれぞれの消費市場がありますが、「アルティジャナーレ(職人製)」という言葉が、あまりに軽々しく使われているのが現状です。
ジェラートを食べる人も、作る人も、今イタリアで注目されているのは、どんなフレーバーがあるかではなく、あふれかえるジェラートがある中でどのようにしてそのクオリティーを認識するかということです。
ちょうど1週間前に、農業省でこのテーマをめぐる会合が開かれ、ジェラートの製造から販売に関わる関係者たちが参加しました。
ジェラート職人たちが改めて「手作りジェラートと大量生産ジェラートは売られているものの中身が全然違うにもかかわらず、それを明確に区別する法律が存在しない」ことを指摘しました。テーマは「本物の“ジェラート・アルティジャナーレ(職人による手作りジェラート)”とは、一体何か?それをどのように定義づけるのか?」
 (PANNA & CO.の店内とラボラトリー)
(PANNA & CO.の店内とラボラトリー)
「PANNA & CO.」のアレッサンドロさん曰く「砂糖や牛乳の含有率といった数値で差がつく話ではない。問題は、“誰でも簡単にジェラテリアをオープンできてしまう”ことです。昨日まで全く別の職業だった人でも、初期投資さえすれば今日からジェラタイオを名乗れる。最低基準もなければ、職業登録も、資格制度もありません。勉強し、実験し、技術を磨いた人と、ただミックス粉を袋から出して混ぜている人との違いが、まったく可視化されていないのです。職人のジェラートは靴や服の職人と同じく素材を仕入れるところから始まります。手作りジェラートは、“中身”だけでなく、“作り手”を見ればわかるのです。」
オリーブオイルやバルサミコ酢、ワインには、品質を守るための厳しい規定や格付け制度がありますが、ジェラートにはそれがありません。考えてみると、これだけ生活に溶け込んでいて、みんなが大好きな存在なのに、ルールが追いついていないのが現状なんですね。
【おいしいジェラテリアの見分け方】
 (左:OTALEG オタレグのラズベリーとドライフルーツ、右:CAPPADONIA カッパドニアのブラッドオレンジとレモン)
(左:OTALEG オタレグのラズベリーとドライフルーツ、右:CAPPADONIA カッパドニアのブラッドオレンジとレモン)
そんなまだまだ改善されないイタリアの現状ですが、私はジェラートを食べ歩き、おいしいジェラート屋さんを見分けるポイントというのがわかるようになりました。
・原材料(果実やカカオなど)の仕入れから行っている。
・ジェラテリアの中にある自分の工房(ラボラトリー)で作っている。
・ジェラートの色が自然な色合い(けばけばしい色ではない)。
・季節ごとにフレーバーが変わる。
ただの“冷たいデザート”ではない、イタリアが誇る“食のアート”としてのジェラート。
イタリアを訪れた際には、ぜひお気に入りのジェラテリアを見つけてみてくださいね。
■イタリアのジェラテリア
PANNA & CO. パンナ&コ
https://pannaeco.wixsite.com/gelato
OTALEG オタレグ
https://www.otaleg.com/
CAPPADONIA カッパドニア
https://www.cappadonia.it/
■ヒサタニミカさんのご紹介

ヒサタニ ミカ
京都生まれ京都育ち。1996年よりローマ在住。
サントリーグループのワイン輸入商社のイタリア駐在員事務所マネージャーを経て、ワインや食材輸入業者のコンサルタント、イタリア飲食店日本開業プロジェクトのコーディネートを行う。25年以上にわたり、イタリア全国に広がる生産者やフード&ワインイヴェントを巡り、イタリア飲食界に纏わるメディアへの企画、取材、寄稿も行っている。また日本の大学への国際研修プログラムにて「イタリア食文化」の講師を務める。
AISイタリアソムリエ協会(正規コース)ソムリエ資格を取得し、現在ではイタリアで数々のワインコンクールの審査員を担う。イタリア外国人ジャーナリスト協会会員。