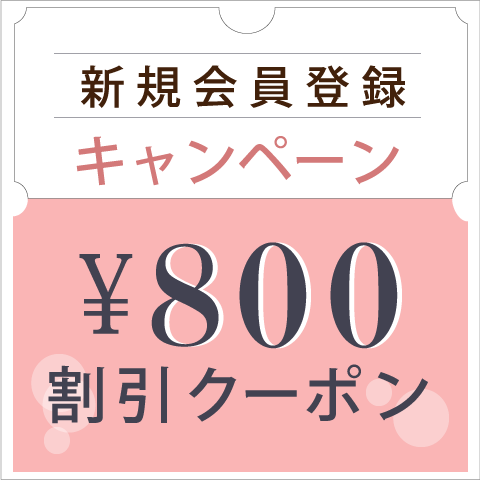寒くなってきたこのごろ、皆さんお元気でお過ごしですか。
忙しい毎日が過ぎれば、クリスマスに冬休みと、ワクワクする時間が待っています。
ダイニングプラスブログでは、スタッフがおすすめしたい「イチ推しレシピ本」を2回に分けてご紹介します。
師走のくつろぎのひとときに、どうぞご覧ください。
得意料理や得意ジャンルはさまざま、でもみんなずば抜けて「食いしん坊」のダイニングプラス スタッフ。
食事を心から愛するスタッフによるおすすめレシピ本たち。第1回は食いしん坊&呑み助のスタッフKと、レシピ本蔵書数千冊(!)のスタッフHがご紹介するこの4冊です。
\食いしん坊&呑み助のKさんおすすめレシピ本/
 「上野万梨子のオーブン料理」
「上野万梨子のオーブン料理」
子供の頃から食いしん坊でお料理は好きでした。でも家にはオーブンがなく、ねだっても買ってもらえなかったので、
代わりに「オーブントースターで作るお菓子」なる本を買ってもらったのを覚えています。
大学時代にイギリスでホームステイした時、ラッキーなことにその家のお母さんは、
当時はまだ日本では珍しかった料理ケータリングのお仕事をされていました。つまり、お料理上手だったのです。
キッチンはあこがれのL字で大理石の作業台、後ろには大小のオーブンがビルドインで備え付けられていました。
当時、携帯電話はまだ普及しておらず、デジタルカメラも持っていたかどうか。。。
残念ながらそのキッチンは画像としては残っていないのに、頭には鮮明に残っています。
その頃からオーブン料理の素晴らしさを実感しました。
さらに社会人になってフランスで1年半の滞在を経て帰国して今の仕事を始めたころ、
「うちで扱っている食材を使ってオーブン料理をしたら、家族や友人とおしゃべりに花を咲かせている間にご馳走ができるじゃないか!」
日本でのオーブン料理を普及すればいいのにな。。。と思うようになりました。
そんな時に出会ったのがこの本です。
美味しそうなお料理の写真や丁寧なレシピの説明だけでなく、時折出てくるフランスの風景写真や上野万梨子さんのコラムに魅了されました。
今でも時折眺めては楽しみ、お料理の参考にさせてもらっています。
・上野万梨子さんについて
1976年、ル・コルドン・ブルー パリ校卒業。帰国後フランス料理教室を始め、新しい時代の若きスター料理研究家として活躍。
1991年からは活動の拠点をパリに移し、日仏の食文化にかかわる発信を続ける。
近著のエッセイ「パリのしあわせスープ 私のフランス物語」(世界文化社)など著書多数。
Instagram @ueno.mariko.official
・ダイニングプラスではフランス料理家、上野万梨子さんのレシピを大好評連載中!
>簡単おしゃれレシピ "アペロディネ Apero Dinatoire"
「あっ」と驚くような食材の組み合わせ、目からウロコのおいしさ、美しさは必見です。
(写真はブーダンノワールとじゃがいものグラタン Boudin noir aux deux pommes
撮影:上野万梨子さん)

(書籍情報)
書名 上野万梨子のオーブン料理―オーブンがなければはじまらないクッキングブック
著者 上野万梨子 レスパース編
写真家 長嶺輝明
出版社 文化出版局
発行年 1998年
※現在こちらの書籍は販売終了しております
「ドイツ家庭料理(暮らしの設計ムック本152号)」
今も勤めるこの会社に出会ったのは大学時代のアルバイトでした。
食の展示会で試食や接客のアシスタントをするお仕事でした。当時発売されたばかりの
ドイツ・ノッカー社のソーセージの担当で、ソーセージやレバーケーゼを焼いては切って出す、
という楽しい4日間を4回過ごしました。
その後、入社してすぐ、ドイツのソーセージをたくさん扱い、自分でも大好きなのに、本場のドイツ料理がどんなものか、全然知らない自分に気づきました。
そのとき出会ったのがこの本です。
表紙にはどーんと白ソーセージのスープ。
迷わず買いました。
ドイツ家庭料理の数々、日本では見かけない食材の写真の他、季節ごとのドイツ文化がコラムとして散りばめられて、興味津々で何度も開きました。
特に「ヘルガ叔母さん風のアーティショー」という見開きページでは当時見たこともなかったアーティチョークの食べ方を9手順にも分けて丁寧に説明してあって、「なんだ、この野菜は!?」と衝撃を受けたのを覚えています。
当時、高級スーパーや百貨店の青果コーナーに行くと、アーティチョークはありますか?と聞くも、逆に「それ、なんですか?」
と返されることの方が多かった時代です。

その後、アーティチョークへの憧れは消えることなく、
数年後にニューヨークのウィークリーマンションに滞在した時、
スーパーでアーティチョークを初めて見て、買って調理した時の感動は忘れられません。
あいにくノッカー社は工場がなくなってしまいましたが、
今でも宝物のように大切にしている本のひとつです。
(書籍情報)
書名 わが家の料理ノート ドイツ家庭料理(暮らしの設計ムック本152号)
著者名 シュルツ祥子(さちこ)
版元社名 中央公論社
発行年月日 1983年
※現在こちらの書籍は販売終了しております
つづいてレシピ本を紹介するのは、レシピ本をなんと数千冊!?所有しているスタッフHさん。お料理への情熱は
並大抵のものではありません。膨大な数のレシピ本を読んできたHさんがおすすめするのは、どんな本でしょう?
\レシピ本蔵書数千冊 Hさんおすすめ/
「おいしい!生地」
小さい頃、手仕事が好きな母が作ってくれるお菓子が好きでした。
大人になって懐かしくなり、自分でもお菓子を作ってみようと初めて購入したレシピ本です。
美味しそうなお菓子の数々と本の中とは思えない、まるで目の前に実物があるかのような
美しく立体的で生地の状態が伝わってくる写真の数々に魅了され、
一気にお菓子の道が切り拓かれた、人生のバイブルとも呼べる大切な一冊です。
書名 おいしい!生地
著者 小嶋ルミ
出版社 文化出版局
出版年 2004年

「イタリアの地方菓子」
お菓子の勉強を始めて数年経った頃に出会った本です。
地方ごとにある歴史や文化から、お菓子も生まれているのだと知り、
お菓子から、その地方の歴史や文化にも興味を持つようになった一冊です。
今では地方菓子の本は珍しくありませんが、この当時はまだ少なかったと思います。
私が購入した本は2005年発行のもので絶版ですが、
2017年に「イタリアの地方菓子とパン」というタイトルで、リニューアルしたものが世界文化社より発行されています。

(書籍情報)
書名 イタリアの地方菓子
著者 須山雄子
出版社 料理王国社
発行年 2005年
※現在は世界文化社から「イタリアの地方菓子とパン」として再販
いかがでしたか?
ブログ「スタッフおすすめレシピ本」第2回は「暮らしにうるおい」編です。おたのしみに!
(担当:サラ)
スタッフおすすめレシピ本【第1回/ おもてなし編】
<ダイニングプラスについて>
2001年創業の輸入食品通販サイト。日本を代表する高級ホテルや有名レストランが採用する高品質な食品を、どなたでも1パックから購入できます。商社直営。
>海外食品通販「ダイニングプラス」トップページはこちらから
・簡単おいしく!おせちにも華やか「洋そうざい」コーナーはこちら
-
 ブーダン ノワール 470g (豚の血と脂の腸詰)
ブーダン ノワール 470g (豚の血と脂の腸詰) -
 メルゲーズ ムートン 生ソーセージ 400g (国内加工)
メルゲーズ ムートン 生ソーセージ 400g (国内加工) -
 ヴァイスヴルスト ドイツ職人の白ソーセージ
ヴァイスヴルスト ドイツ職人の白ソーセージ -
石窯焼き風 田舎風パン (パン ド カンパーニュ )
-
 パテ ド カンパーニュ ブロック (田舎風豚のパテ)オーセンティック
パテ ド カンパーニュ ブロック (田舎風豚のパテ)オーセンティック -
 ビーフ100% ひき肉ステーキ(ステークアッシェ) 100g×2
ビーフ100% ひき肉ステーキ(ステークアッシェ) 100g×2 -
 ブレス産 AOP発酵バター 250g
ブレス産 AOP発酵バター 250g -
 ミニ カヌレ 7個入り
ミニ カヌレ 7個入り -
 薔薇のハーブソルト(ミル付き)
薔薇のハーブソルト(ミル付き) -
 ベラミーズパイシート フレッシュバター100% 300g
ベラミーズパイシート フレッシュバター100% 300g -
 とろニシン レモンじめ 2フィレ(100g~160g)
とろニシン レモンじめ 2フィレ(100g~160g) -
 焼くだけ!大きなクロワッサン 発酵バターが香るフランス産 Bake up生地 60g×4個入り
焼くだけ!大きなクロワッサン 発酵バターが香るフランス産 Bake up生地 60g×4個入り -
 りんごとカスタードのタルト(直径約21cm10カット)タルトノルマンディー
りんごとカスタードのタルト(直径約21cm10カット)タルトノルマンディー -
 【送料込み】欧州パンとこだわりのバターを愉しむ欲張りセット
【送料込み】欧州パンとこだわりのバターを愉しむ欲張りセット -
 【送料込み】ヨーロッパ ちょい呑みセット
【送料込み】ヨーロッパ ちょい呑みセット
パリのマルシェ食材とお料理|上野万梨子さんのフランスレポート

東京の山手線の内側とほぼ同じ面積しかないパリ。そこに月曜日を除く毎日30から多い日で40近くの朝市が開かれます。広場のように人が集まれる場所があれば、そこには朝市が立つという感じで、パリジャンの暮らしを支える大切な存在です。
写真は地上を走るメトロ高架橋下のグルネル朝市。モットピケ・グルネル駅とデュプレックス駅間の500メートルにわたる大きなマルシェです。
食料品の買い出しといっても男女比は半々くらいで、それこそ暮らしむきも人種も様々な老若男女が分け隔てなく集まり真剣に品定めする様子には迫力があるものです。

しばらく家を留守にして帰宅すると、早速向かうのは朝市です。キッチンの野菜カゴや冷蔵庫に何もない状態でまず買うのは基本の野菜。サラダのヴィネグレットソースに使うエシャロット、ニンニク、煮込みに欠かせないローリエとタイム、そしてジャガイモ、人参、玉葱、ポロ葱、料理の味を決めるのに便利なシャンピニョンなどです。市場を歩き回るとあれもこれも買って帰りたくなるものですが、そこは抑えてまずは基本のものから。
上の写真を撮った頃のポロ葱はまだ細身ですが、寒くなるにつれてどんどん太くなり甘みも増します。今頃のポロ葱は下の写真のような感じで、ポワローヴィネグレットに使うならこちらです。

右列に見えるのは日々の料理に出番が多いエシャロット3種。

一番上の小粒で表皮が灰色のものは最も風味が強いタイプ。生牡蠣に添えるヴィネガーに刻んで入れるのはこちらです。その下が肉料理向きのエシャロット、そしてその下の細長いものは辛味がやさしいタイプになります。
左列にはロートレック産のニンニク。箱に入っているのは黒ニンニクです。
フランスでは玉ねぎの品種も豊富です。

これに対して一般的な玉葱はオニオン・ジョーヌ(黄色い皮の玉ネギ)と呼ばれるもの(左上の写真)で、バターで炒めた時の甘い匂いには素晴らしいものがあります。
皮付きのまま輪切りにして、オリーブオイルをかけ、塩をふってオーブンで焼いた赤玉葱。(右上の写真)

ヴィネグレットソース用に刻んで、いつでも使えるように冷蔵保存しているニンニク、エシャロットです。
この店ではジャガイモの種類も豊富それぞれの値札にはどのような調理法に合うかも書かれています。

ポタージュやピュレ、フリットに向くポクポクタイプ、実がしまった煮込み向きタイプ、フライパンソテーに向くタイプ、茹でてサラダに使うのに向いているもの、オーブン焼きに適したもの、皮付きのまま蒸し焼きに向くものなどなど。新ジャガは別として地中で熟してから収穫されているので、包丁の入り具合が日本の市場に出ているものとは違うようです。ガリガリしない。力を入れずにスルッと刃が滑るように切れるのには思わずニヤッとしてしまうほどです。アマンディーヌ、シャルロット、ポンパドール、モナリザ、ジュリエット、ベル・ド・フォントネなど、ジャガイモの名前の多くが女性の名前、あるいは女性を思わせる呼び名です。 右上はジャガイモとポロネギのスープ煮。

人参、ジャガイモ、セロリ、玉葱などのスープ エメンタールチーズを5ミリ角くらいに切りって器に入れ、そこにスープを注ぎます。チーズが四角いままプチュッと柔らかくなったところをスプーンですくっていただくと美味しいものです。
マッシュルームのことをフランスではシャンピニョン・ド・パリと言います。

赤みを帯びた茶と白があり、風味の点では変わりありませんが、サラダに加えて生で食べるのは白い方です。
新鮮なうちはカサがしっかり閉じていますが、次第に開いて黒ずみはじめます。
ただこのような状態になったものは風味が上がっているものなので、 スープにすると鮮度が良いものよりかえって味が濃く出て美味しいものです。
ラスパイユのBIO市に出る卵のスタンド。

白玉、赤玉、茶玉と3種類ありますが、殻の色は卵を産んだ鳥の羽の色と同じで、栄養価や美味しさと殻の色とは関係がありません。フランスの卵の黄身は薄い黄色をしていますが、それは麦を主とした餌を与えられるから。日本では黄身の色が濃いほど栄養がある良い卵と信じられているため、パプリカやマリーゴールドを混ぜた餌を食べさせてオレンジ色にしていることも多いようです。

上の写真の緑の卵ケースには“鶏を殺さない卵”と書いてあります。どういうことでしょう。
これは、卵を産まなくなった雌鳥を殺処分せずに協力農家などに引き取ってもらい、自然死するまで生かすというプロジェクトの元に産ませた卵だからなのです。当然他の卵より価格は上がりますが、この考えに賛同した人たちが購入することで成り立っています。
健康的で鮮度がよい卵の状態をお見せするために、写真の皿蒸し卵は過熱前の状態です。
平皿にフレッシュクリームを流し、薄切りハムと卵を盛りつけてパセリを散らし、湯を張ったフライパンにスノコを置いてその上に皿を置き、蓋をかけて黄身が半熟になるまで火にかけます。

グルノーブル風皿焼き卵。
バターを塗った焼き皿に卵を割り入れ、オーブンで湯煎焼きにします。あるいは、湯を張ったフライパンに網を敷き、その上に焼き皿をのせて蓋をかけて蒸し焼きに。半熟に仕上げたら塩をふり、あらかじめ用意しておいたクルトンとケッパー、パセリを散らし、好みでオリーブオイルをまわして。家庭ではこのような卵料理を前菜としてメイン料理の前にいただきます。
エシャロットとニンニク、タマネギは常にキッチンに置いているもっとも基本の素材です。

湿気が少ないフランスなので、こうしてカゴなどに入れて外に出しておいても問題ありません。
春から初夏にかけて、エシャロットは右上の写真のような葉付きの束を買い、フックに下げて自然乾燥させます。
ジャガイモは紙袋に入れてカゴの中に。そろそろ使った方がよい状態のものは忘れないように外に出しておきます。
ローリエとタムは1束の量が多くてフレッシュのうちに使い切れるものではなく、乾燥したら瓶などで保存します。

これはフランスのジャガイモの中で最もサイズが大きいビンチと、最も小さいデリカテス。瓶の中はローリエとタイムです。
こうして基本素材が揃っていれば毎日の料理がとてもスムース。料理にはリズム感が大切だと常々思いますが、 このキッチンコーナーは調理の基本になるリズムの源なのかもしれません。
<ダイニングプラスについて>
2001年事業開始の輸入食品通販サイト。「読売テレビ」「関西テレビ」「ダンチュウ」や「エル・ジャポン」など、メディア紹介多数。だれもが知る高級ホテルやレストランが採用する高品質な輸入食品を、どなたでも1パックから購入できます。商社直営。
-
 ブレス産 AOP発酵バター 250g
ブレス産 AOP発酵バター 250g -
 ベルデンソ 無ろ過 エキストラバージン オリーブオイル 500ml オリタリア
ベルデンソ 無ろ過 エキストラバージン オリーブオイル 500ml オリタリア -
 ハーフバゲット 140g×2個入り
ハーフバゲット 140g×2個入り -
 優しい味わいのホワイトハム (ジャンボンプティ ブラン)
優しい味わいのホワイトハム (ジャンボンプティ ブラン) -
 肉厚の旨味 大粒ほたて貝(青森産 黄金ほたて) Lサイズ
肉厚の旨味 大粒ほたて貝(青森産 黄金ほたて) Lサイズ -
 フランス伝統生ハム IGP ジャンボン ド バイヨンヌ 50g
フランス伝統生ハム IGP ジャンボン ド バイヨンヌ 50g -
 薔薇のハーブソルト(ミル付き)
薔薇のハーブソルト(ミル付き) -
 地中海風 野菜のキッシュ (タルトメディテラネ)
地中海風 野菜のキッシュ (タルトメディテラネ) -
 6種のベリー 北欧カフェデニッシュ 2個入
6種のベリー 北欧カフェデニッシュ 2個入 -
 三角 プレッツェル 85g×2
三角 プレッツェル 85g×2 -
 ブルターニュ産 クッキー(ガレット)3種アソート缶(オレンジフラワー)
ブルターニュ産 クッキー(ガレット)3種アソート缶(オレンジフラワー) -
バタープレッツェル 79g×2個入り
-
 訳あり バゲット ルヴィノワーズ
訳あり バゲット ルヴィノワーズ -
 【送料込み】欧州パンとこだわりのバターを愉しむ欲張りセット
【送料込み】欧州パンとこだわりのバターを愉しむ欲張りセット -
 【送料込み】週末ご褒美プチセット
【送料込み】週末ご褒美プチセット
マルシェでみつけた秋の味|上野万梨子さんのフランスレポート

パリの中心で暮らしていながら都会の住人のような気があまりしないのです。
その理由はいくつかあるのですが、家から半径600メートルに二ヶ所、週に計4日開かれる朝市の存在が大きいでしょう。
食料品店が軒をなす商店街も大型スーパーマーケットも同じ圏内にありますが、青空市に溢れる季節の彩りと香りは、 日常の必要不可欠な買い物が気持ちのリフレッシュのもとにもなり、用がなくても足を向けたくなる魅力があります。

一般的に旬と言われる時期より一歩前に味わうことに粋を感じるのが日本人ですが、パリの朝市にやって来るのは今こそが旬のものばかり。まだかな、まだかな、と思っていると、一気に出はじめて山になって売られ、それが 「次あたりでもう終わりかな」と告げられれば、ほんとうに次の次のマルシェの日には姿が消えてしまうものなのです。
10月に入って今はまさにキノコ狩りのシーズンです。

(写真:セップやジロールなどのキノコがたくさん)
今ごろ田舎の森の近くの薬局には「毒キノコにご注意」と、食べられるキノコと食べられない怖いキノコをイラストで描いたポスターが貼り出されていることでしょう。
そしてパリの朝市には、湿った森の土や枯葉をつけた秋のキノコが旬の真っ盛りを迎えています。たださすがにすべてが森から届いたものというわけではありません。パリ近郊農家が、昔の採石場あとなどの地下で栽培しているものも多く、私が買いに寄るのはBIOの野菜のみを扱うスタンドです。

(写真左:こちらは巨大なプルロット、写真右:スパラジ(スパラジスとも))
海綿か白木耳のような姿のこちらはスパラジ。見た目はこんなですが風味は素晴らしく “貧乏人の白トリュフ” とでも言いましょうか。

バターでエシャロットとともに炒めフレッシュクリームを加えるだけで、家庭でも美食家のパスタが出来上がります。
もう一品は、日本では杏茸と呼ばれるオレンジ色のジロール。

これはニンニクバターで炒めて刻みパセリ仕上げ。田舎パンに焼き汁をつけて食べるのがまたよし。
10月のマルシェで目を引くのは季節のフルーツです。

パリ近郊のBIO農家のスタンドには秋の味覚が一堂に。手前はコンフェランスという品種の梨、その向こうには まだ小粒のリンゴ、そしてキノコも見えます。花をつけたハーブが売られるのも10月の今頃です。

8月末には出始めるレーヌクロードという青梅のようなプラムはそろそろ食べ収め。ほぼ同時期に出てあっという間に姿を消してしまう黄色い小さなプラム、ミラベルはすでになし。フレーバーキングという名の濃い赤の品種でプラムの季節は終了します。
そしてプラムにかぶって登場した葡萄とイチジク、ノワゼットやクルミ、そして栗が並びあって、朝市は今まさに実りの秋の大舞台です。

ところでフランスでは種あり葡萄が主流です。小さな葡萄なら一粒一粒指でつまみなどせずに、男なら房にかぶりついてムシャムシャ種ごと食べてしまうことも。
これはフランスでは珍しく種なし葡萄のサントニアルです。薄皮で種がないならと、試しに作ってみたのがこちらです。

オリーブオイルで軽く炒めたあと水ほんの少々加えて蓋をして1分から2分(大きさや熟し加減により)火にかけただけのものです。リキュールもスパイスも使わずに超シンプルに。いくらでも食べられる美味しさです。

写真はこれをブッラータに添えたところ。日本の種無し葡萄は大粒がほとんどですから、同じようにはできないでしょう。熟し方が足りないとソースがとれないので未熟なものは選ばず、半分にカットして作ってはいかがでしょう。
秋にはさまざまな品種のプラムが出回り、コンフィチュール作りが楽しいシーズンです。

灰色がかった緑のプラムはレーヌクロード。オレンジ色のコンフィチュールは出盛りの頃に作っておいたミラベルのコンフィチュール。

レーヌクロードとフレーバーキングのコンフィチュールで朝食。
保存を前提としていないので砂糖はプラムの重さの25%のみで、皮もつけたまま大きめにカットして。パンにつけるのはもちろんですが、フランスの濃厚なクレームフレッシュに添えて食べるのが最高です!
<ダイニングプラスについて>
2001年事業開始の輸入食品通販サイト。「読売テレビ」「関西テレビ」「ダンチュウ」や「エル・ジャポン」など、メディア紹介多数。だれもが知る高級ホテルやレストランが採用する高品質な輸入食品を、どなたでも1パックから購入できます。商社直営。
-
 ブレス産 AOP発酵バター 250g
ブレス産 AOP発酵バター 250g -
 ブレス産 発酵バター ドゥミセル (加塩) 250g
ブレス産 発酵バター ドゥミセル (加塩) 250g -
石窯焼き風 ライ麦パン(パン・オ・セーグル)
-
 ハーフバゲット 140g×2個入り
ハーフバゲット 140g×2個入り -
 贅沢いちごジャム (プレザーブスタイル)
贅沢いちごジャム (プレザーブスタイル) -
 薔薇の花びら茶
薔薇の花びら茶 -
 2種チーズのバスクチーズケーキ
2種チーズのバスクチーズケーキ -
 とろニシン レモンじめ 2フィレ(100g~160g)
とろニシン レモンじめ 2フィレ(100g~160g) -
 焼くだけ!大きなクロワッサン 発酵バターが香るフランス産 Bake up生地 60g×4個入り
焼くだけ!大きなクロワッサン 発酵バターが香るフランス産 Bake up生地 60g×4個入り -
 薪窯ナポリ風ピザ マルゲリータ 200g
薪窯ナポリ風ピザ マルゲリータ 200g -
 モデナ産 バルサミコ酢 IGP 5グレープ 250ml (オリタリアブランド)
モデナ産 バルサミコ酢 IGP 5グレープ 250ml (オリタリアブランド) -
 フランス伝統生ハム IGP ジャンボン ド バイヨンヌ 200g
フランス伝統生ハム IGP ジャンボン ド バイヨンヌ 200g -
 【送料込み】欧州パンとこだわりのバターを愉しむ欲張りセット
【送料込み】欧州パンとこだわりのバターを愉しむ欲張りセット -
 【送料無料・ギフト包装】ベルデンソ 無ろ過 EXVオリーブオイル&ジャムギフト
【送料無料・ギフト包装】ベルデンソ 無ろ過 EXVオリーブオイル&ジャムギフト -
 【送料込み】週末ご褒美プチセット
【送料込み】週末ご褒美プチセット
ナポリのストリートフードと空中厨房?!|スタッフ海外体験記

数年前の夏のこと、トマト生産に立ち会うためにナポリに向かいました。
この時のナポリ滞在予定は1週間。諸事情によって具体的な予定も決められない長逗留をすることになったため、いろんな対応がしやすいように、街中のプチホテルに宿泊することにしました。
ホテルはナポリ随一の繁華街を一歩奥に入ったところにあり、入口はとてもわかりにくい。
辛うじて見つけた入口はとても古びていてここにホテルがあるとはとても思えません。なぜならその狭いスペースには無人の守衛室らしき部屋と古びたエレベーターがあり、エレベーターを囲むように石の階段がついているだけ。どうやらこのビルの2階にホテルのフロントがあるらしく、荷物もあったので、エレベーターを使うことに。

そこにあるエレベーターは当然のように手で開ける扉のついた旧式のもの。中に入ると何とコイン式で、10セントコインを入れる古い箱が付いているのです。古いんだか新しいんだか、、、と思わず苦笑です。コインを入れてほんとに動くのか?疑問に思いながら恐る恐るコイン投入。すると階数を表わす数字ボタンが点灯してどうやら電源が入ったようです。
エレベーターを降りるとホテルの入口がありました。
それまでの不安を取り払ってくれるきれいな自動ドアの入口。ホテルは小さいながら部屋はきちんとしていて清潔でした。
安心するとお腹がすくものですね。
荷ほどきもそこそこに、表の通りに出てみることにしました。

にぎやかな歩行者専用のその通り沿いには両側に小さいお店が軒を連ねています。食べ物もたくさんあります。
その時目に入ったのはピザのテイクアウトショップ。
恰幅ののいいピッツァイオーロらしいお兄さんがオーダーごとにピザ生地を広げて作っています。シンプルにマルゲリータを注文して待つこと数分。

奥のピザ窯にピザを入れて回しながら焼き上げたら何枚か重ねた紙の上に置いて手渡しです。それを半分にたたんでかぶりつくのです。

焼きたてのピザの美味しいこと!!
その後何度かこのお店にお世話になることになるのでした。。。
さて、別の日。
ホテルで教えてもらったおすすめのお店の中で一番近そうなところに行ってみることにしました。
そこはかつて悪名高かったスペイン地区の一角にありました。
教えてもらった通りに歩いて、お店の名前を確認して、どう考えてもここ、という場所にあったのはお惣菜屋さん風の小さいお店。

確かに表にはテーブルとイスがいくつか置いてあって食べられる様子。お店の中には冷蔵ケースがあって、お惣菜が並んでいる他、パスタや缶詰などの保存食も販売されていて、グロッサリーも兼ねたお店のようです。お店の奥にキッチンがある様子もなく、ほんとにここかな?と半信半疑でお店に声をかけると、どうぞ、と言ってメニューを渡されました。
前菜盛り合わせやパスタなどを注文し、待っていると、何やらサービスの男性がお店を出たり入ったり。
そのうち、外から戻ってきたお店の人が我々のテーブルにお料理を持ってきました。

いよいよ謎が深まってよく見ると、お店を出て小道を横切って斜め前の建物の下まで行って上を見上げています。
すると上から黄色いかごがするすると降りてくるのです。

その黄色いかごについたロープを目で追うと、ビルの3階にあたる窓辺の小さいベランダから女性がかごを下している姿が見えました。
そうか!上でお料理して運んでるんだ!と気づいた時の楽しさ!
これぞナポリです!
ホテルの人も遠い国からきた私たちにナポリらしいエンターテインメントを見せたかったのでしょうね。
もちろん美味しかったのですが、何よりも空からやってきた温かいお料理の楽しさに、忘れられない食事シーンとなりました。
<ダイニングプラスについて>
2001年事業開始の輸入食品通販サイト。「読売テレビ」「関西テレビ」「ダンチュウ」や「エル・ジャポン」など、メディア紹介多数。だれもが知る高級ホテルやレストランが採用する高品質な輸入食品を、どなたでも1パックから購入できます。商社直営。
-
 薪窯ナポリ風ピザ 3チーズ 200g
薪窯ナポリ風ピザ 3チーズ 200g -
 薪窯ナポリ風ピザ マルゲリータ 200g
薪窯ナポリ風ピザ マルゲリータ 200g -
 セミドライ チェリートマトのオイル漬け 180g
セミドライ チェリートマトのオイル漬け 180g -
 完熟チェリートマトが丸ごと入ったトマトパスタソース 280g
完熟チェリートマトが丸ごと入ったトマトパスタソース 280g -
 ハーブ香るブラートヴルスト ドイツ職人の絹引き焼きソーセージ
ハーブ香るブラートヴルスト ドイツ職人の絹引き焼きソーセージ -
 【電子レンジ対応】 エスカルゴ XLサイズ 12個入(殻付き/ガーリックバター入り)
【電子レンジ対応】 エスカルゴ XLサイズ 12個入(殻付き/ガーリックバター入り) -
 解凍するだけ カナダ産 ムール貝
解凍するだけ カナダ産 ムール貝 -
 単一品種 ノチェッラーラ イタリア産100% EXVオリーブオイル
単一品種 ノチェッラーラ イタリア産100% EXVオリーブオイル -
 ふわもち食感 サンドイッチ チャバタ 130g×1個
ふわもち食感 サンドイッチ チャバタ 130g×1個 -
 焼くだけ!大きなクロワッサン 発酵バターが香るフランス産 Bake up生地 60g×4個入り
焼くだけ!大きなクロワッサン 発酵バターが香るフランス産 Bake up生地 60g×4個入り -
 ポテトニョッキ 1kg
ポテトニョッキ 1kg -
冷凍 ポム アリュメット (フレンチフライポテト) 450g
-
 訳あり バゲット ルヴィノワーズ
訳あり バゲット ルヴィノワーズ -
 【送料込み】欧州パンとこだわりのバターを愉しむ欲張りセット
【送料込み】欧州パンとこだわりのバターを愉しむ欲張りセット -
 【送料込み】ヨーロッパ ちょい呑みセット
【送料込み】ヨーロッパ ちょい呑みセット
真夏のリフレッシュメント、生アーモンドジェラート|スタッフ海外体験記
朝から快晴で南イタリアの強い日差しが照りつける7月のある日、新商品の生産立ち合いに行きました。

そこはカラブリア州。イタリアの地図で言うと爪先にあたり、向かいはシチリアです。
工場は爪先の中でも足裏の指の付け根ぐらいのところにあってイオニア海に面したビーチがある場所です。ビーチから車で10分ほど、高台にある工場の前には自社のバジル農園があり、遠くにイオニア海が見渡せます。
今回のお目当てはセミドライチェリートマトのオイル漬けとパスタソース。
(あいにく昨年のトマトの不作でオイル漬けの方は欠品中ですが、今頃現地では今年生産分を作ってくれているハズ!来年頃には再入荷のお知らせができることと思います。)

真赤に熟したミニトマトがカゴいっぱいになって工場に運び入れられる光景は夏本番。

それらを洗って半分に切ったら、オーブン(といってもコンベア状の長~いもの)でじっくり水分を飛ばしてセミドライに加工していきます。
すでに暑い。。。とても暑い。。。
一通りの工程を見たら次は別棟のパスタソース工場へ。
ここは更に暑く、湿度が高い。
この工場では地元の女性たちが中心となって、丁寧に商品を作っていきます。自宅で作るのと同じようにまずはオリーブオイルにニンニクを入れて香りを出し、次に玉ねぎを入れて甘みを出し・・・そんな丁寧なお仕事です。詳しくは別の機会にお話しするとして。。。
工場内はとにかく暑い。
せっかくの立ち合いなので全ての工程を見なければ! 働いている方々は暑さを気にせず(そのように見えた)、丁寧な仕事を続けます。
暑い。まるでサウナのように汗が体をしたたり落ちるのを感じながら工程を見守ります。
暑い。
生産を途中で止めるわけにもいかないので、結局終わったのは午後2時を回ったころ。見学用のビニールコートを脱いで外に出た時にはホッとしました。外も真夏の晴天下なので体感40℃ぐらいですが湿度が低い分まだ快適。冷房の効いた部屋で一休みしていたとき、「ランチに行く?」と誘われました。
翌朝一番のフライトで戻る予定にしていたので、その日は最終日です。
立ち合いの後は空港近くのホテルへ送ってもらうことになっていたので、このランチは今回イタリアでの最後の食事。
でも。。。
あれだけの汗をかいた後で全く空腹を感じません。
それを伝えると、「オッケー。じゃ別のところに行こう。」ということで連れて行かれたのは工場から車で3分ほどの村の中心地。

日曜になると露店が並んでにぎわう一画ですが、この日に向かったのはジェラート屋さん。
イタリアには美味しいジェラートがあった♪
そういえば前に来たときに食べたジェラート、美味しかったな、と思いだして嬉しくなったものの、たっぷり汗をかいた後であまり食欲がありません。

そこで注文したのがアーモンドジェラートです。
注文すると聞かれるのは「ブリオッシュは?」
そうです、ここは南イタリア。
ジェラートとブリオッシュは定番の組み合わせなのです。

メーカーの担当者は切り込みを入れたブリオッシュに2種のジェラートを挟んで生クリームをたっぷり添えた定番スタイル。

私はアーモンドジェラートをグラスに入れてもらって横にブリオッシュを添えた別スタイル。これが大正解!
日本ではローストされたアーモンドが一般的ですが、イタリアでは夏になると生アーモンドを楽しみます。
フランチャコルタ(イタリアの高級スパークリングワイン)と生アーモンドを食前に楽しむ、というのもイタリアの夏の一場面です。
アーモンドミルクは日本でも少し前に流行りましたね。
南イタリアでは生アーモンドをアーモンドミルクにして、それをジェラートにしたものが有名です。生アーモンドミルク特有の爽やかな香りとほのかな甘み。
ジェラートは他の国のアイスクリームに比べると軽めなのが特徴ですが、このアーモンドジェラートは特に軽く、シャーベットに近い食感です。
砂糖の加減はお店によって違いますが、概して甘さ控えめです。口に運ぶと冷たくサラッと溶けてなくなり、口の中にアーモンドの爽やかな香りが残ります。
暑さにばてていた身体に染みわたるような美味しさです。

さらに南イタリアらしさを見せていたブリオッシュ。
フランスの上品でリッチなブリオッシュとは全くの別物。
ぷっくりとふくれて小麦色の健康的な焼き色のついたブリオッシュは遠慮ない大きめサイズ。「ブリオッシュは?」と聞かれて見せられた時には一瞬「要らない」と言いかけたのですが、南イタリアを楽しもうと思いなおして「スィ(はい)」と言ったのが正解。
ずっしりした大きさとは違い、軽い食感です。
何てことのないシンプルな味わい。見た目はコッペパンのようにも見えますが、コッペパンより甘みは少なく、もう少し軽い。これ自体が驚く美味しさ、というわけではないのに、ジェラートの名脇役となって主役を引き立てているのです。
勝手に表現するなら・・・
清楚なお嬢さんの横に体の大きな男の子が肩をすくめて佇んでいる感じ。
そんなことを思いながら染みわたるランチを楽しんだひと時でした。
<ダイニングプラスについて>
2001年事業開始の輸入食品通販サイト。「読売テレビ」「関西テレビ」「ダンチュウ」や「エル・ジャポン」など、メディア紹介多数。だれもが知る高級ホテルやレストランが採用する高品質な輸入食品を、どなたでも1パックから購入できます。商社直営。
-
 セミドライ チェリートマトのオイル漬け 180g
セミドライ チェリートマトのオイル漬け 180g -
 完熟チェリートマトが丸ごと入ったトマトパスタソース 280g
完熟チェリートマトが丸ごと入ったトマトパスタソース 280g -
 ダッテリーノトマトのトマトジュースづけ (皮なし)400g
ダッテリーノトマトのトマトジュースづけ (皮なし)400g -
 ポテトニョッキ 1kg
ポテトニョッキ 1kg -
 ミニ シリアルロール 44g×5個
ミニ シリアルロール 44g×5個 -
 薔薇のハーブソルト(ミル付き)
薔薇のハーブソルト(ミル付き) -
 2種チーズのバスクチーズケーキ
2種チーズのバスクチーズケーキ -
 3種のチーズのキッシュ(タルトフロマージュサレ)
3種のチーズのキッシュ(タルトフロマージュサレ) -
 6種のベリー 北欧カフェデニッシュ 2個入
6種のベリー 北欧カフェデニッシュ 2個入 -
 りんごとカスタードのタルト 約21cm10カット フランス製 (タルトノルマンディー)
りんごとカスタードのタルト 約21cm10カット フランス製 (タルトノルマンディー) -
 プチパン プレーン 35g×5個入り
プチパン プレーン 35g×5個入り -
 モデナ産 バルサミコ酢 IGP 5グレープ 250ml (オリタリアブランド)
モデナ産 バルサミコ酢 IGP 5グレープ 250ml (オリタリアブランド) -
 パッションフルーツ 冷凍ピューレ 1kg
パッションフルーツ 冷凍ピューレ 1kg -
 【送料込み】ヨーロッパ ちょい呑みセット
【送料込み】ヨーロッパ ちょい呑みセット -
 【送料込み】週末ご褒美プチセット
【送料込み】週末ご褒美プチセット
上野万梨子さんとダイニングプラスの出会い
上野万梨子さんが東京滞在中に開かれた料理の会から何とも素敵なメールが届きました。
そのタイトルは、
「バターがなければはじまらないフランス料理」試食会のお知らせ
なんと!フランスのいろんなバターのお話しだけでなくその食べ比べや、バターを使ったお料理までいただけるというではないですか!
当時、ダイニングプラスではブレス産バターを取扱いし始めた頃。早速上野万梨子さんにご連絡して、ぜひ、ブレスのバターも皆さまで食べ比べをしてみてください!と申し出ました。

>>【ブレス産 AOP発酵バター 250g】はこちらから
上野万梨子さんとはずいぶん前に一度一緒にお仕事をさせてもらったことがあり、以来、メールニュースをいただいていました。いつも素敵な食の発信に、ひとときフランスを旅するような気分を味わうだけだったのですが、その時のメールには体が反応して思わずそんな申し出をしていた、というわけです。
ダイニングプラスからの申し出に対して、上野万梨子さんはすぐに返事をくださり、「是非ブレス産バターも加えましょう!」と快諾をいただいたのです。
そして私もその会に参加させてもらうことになりました!
興味津々です!!
さて当日。会場は東京都内某所の樹木に囲まれた素敵なカフェ。
足を踏み入れると、長いテーブルの真ん中にずらっと置かれたバター各種、その数にびっくりです。

バター15種の他、当時話題のフレーバーバター、タルティネ用バター(冷蔵庫から出してすぐに使っても柔らかくパンに塗り広げられるように加工されたバター)、ギー(澄ましバター)、そしてバターの原料にも近いクレーム・フレッシュ・エペッス(発酵クレーム)まで!!

こんなにたくさんのバター、見たことない!
会場を訪れた全ての方がそう感嘆し、それを今から試食できるんだ、という興奮の息遣いが聞こえてきそうな雰囲気でした。
いよいよ時間になり、上野万梨子さんの講義が始まります。
バターの成分のお話し、フランスのバター分類についてのお話しに始まり、簡単なバターの歴史まで、興味深いお話が続き、締めくくりは、やはりフランスが世界一のバター消費国である、ということ。
フランスの食とバターは切り離せないものである!
再認識をするとともに、ますますフランスバターへの興味は深まってきます。
そしてお待ちかねの試食の時がやってきました。
15種類のバターがパッケージと共にテーブルの中央に置かれ、それぞれを試食するのです。
バターの食べ比べなんて初めての経験!
作る地域、作る人、原料の違いによってやはり少しずつ味が違います。
バター奥深し!!
バターそのものの試食が終わると続いてバターを生かしたお料理の登場です。
せっかくなので、そのお料理の写真をご覧いただきましょう。(当時の携帯電話で撮った写真なので画像があまり良くなくてごめんなさい!)

Radis au beurre
生野菜のラディッシュに有塩バターを塗っていただく
ラディッシュのちょっとした辛みと水分がバターのミルキーさと出会って口の中でマイルドに絡み合います。

Endives au beurre
アンディーブ(チコリ)に有塩バターと一緒にレーズンとクルミ入りのグラノーラをトッピング。チコリのほろ苦さをバターが引き立て、クルミとレーズンが加わることで食感や味わいが複雑にマッチ。

Tartines de fraises au beurre
薄切りバゲットに無塩バターを厚めに載せ、いちごとグラニュー糖をトッピング。
シンプルなのにフレッシュで手の込んだ洋菓子のよう!

Soupe a la salade verte(本来は a はアクソン・グラーヴ付き)
葉野菜とじゃがいものスープにカリッと焼いた薄切りバゲットにバターをたっぷり塗ってクルトンのようにスープに浸していただきます。
パンに塗ったバターの味わいを楽しむため、スープは牛乳などを加えずすっきりとした味わいに! 葉野菜スープであって、ポタージュでないところが上野さんらしく気の利いた演出!

Merlan Colbert
本来のこの名前の料理とは少しアレンジして、トラウトサーモンに細かいパン粉をまぶして揚げたものにハーブバターをのせたもの。
このハーブバターの色がきれいで魚の味わいにもぴったり!

まぐろのミディアムステーキ かぼちゃとトマトの焦がしバターソース
メインにもなり、手軽にバゲットにのせて前菜でも、という優れもの。焦がしバターを使うことでバターのミルクっぽさが一気に香ばしさへと変身の驚きソース!

バターでしっとり、りんごのケーキ
いわずもがな、見ただけで美味しさが伝わるバターの力。飽きのこないシンプルな美味しさです。
前菜からデザートまで全てがまさに今回の勉強会のタイトル通り、「バターがなければはじまらないフランス料理」であり、そして紹介されたお料理は全て、素材を生かす和食の延長線上にあるように感じました。
上野万梨子さんは「フランス料理」の小難しいイメージをくつがえして「家庭で楽しめるフランス料理」を開拓してきた先駆者です。その神髄をバターを通じて感じた参加者は多いのではないでしょうか。
数年経った今でも鮮明に覚えているあの勉強会の光景はこの先もずっと忘れることはないでしょう。
上野万梨子さんとダイニングプラスとの出会いのお話しでした。
<ダイニングプラスについて>
2001年創業、商社が直営する輸入食品通販サイト。日本を代表する高級ホテル、ミシュラン星付きレストランが採用する高品質な業務用食品を、どなたでも1パックから購入できます。テレビ各社や「ダンチュウ」、「エル・ジャポン」など、メディア紹介多数。
-
 ブレス産 AOP発酵バター 250g
ブレス産 AOP発酵バター 250g -
 ブレス産 発酵バター ドゥミセル (加塩) 250g
ブレス産 発酵バター ドゥミセル (加塩) 250g -
 ビーフ100% ひき肉ステーキ(ステークアッシェ) 100g×2
ビーフ100% ひき肉ステーキ(ステークアッシェ) 100g×2 -
 信州サーモン 冷燻仕立て
信州サーモン 冷燻仕立て -
 ハーフバゲット 140g×2個入り
ハーフバゲット 140g×2個入り -
 薔薇のハーブソルト(ミル付き)
薔薇のハーブソルト(ミル付き) -
 セミドライ チェリートマトのオイル漬け 180g
セミドライ チェリートマトのオイル漬け 180g -
 ごろっと大粒ほたて(青森産 黄金ほたて)のコキーユ(グラタン) 8個入り
ごろっと大粒ほたて(青森産 黄金ほたて)のコキーユ(グラタン) 8個入り -
 ベーコンとチーズのキッシュ(キッシュ ロレーヌ)
ベーコンとチーズのキッシュ(キッシュ ロレーヌ) -
 りんごとカスタードのタルト 約21cm10カット フランス製 (タルトノルマンディー)
りんごとカスタードのタルト 約21cm10カット フランス製 (タルトノルマンディー) -
 紫いちじくジャム
紫いちじくジャム -
 爽やかオレンジマーマレード
爽やかオレンジマーマレード -
 パテ ド カンパーニュ ブロック (田舎風豚のパテ) スタンダード
パテ ド カンパーニュ ブロック (田舎風豚のパテ) スタンダード -
 【送料込み】欧州パンとこだわりのバターを愉しむ欲張りセット
【送料込み】欧州パンとこだわりのバターを愉しむ欲張りセット -
 【送料込み】ヨーロッパ ちょい呑みセット
【送料込み】ヨーロッパ ちょい呑みセット
ダイニングプラス20年の思い出

2001年5月インターネット通販サイト ダイニングプラスが誕生しました。
支えてくださったたくさんの皆さま、心よりありがとうございました。
この機会にダイニングプラスのこれまでを振り返ってみたいと思います。
>感謝の20周年記念イベント開催中!特設ページはこちら
【通販というキーワード】
ダイニングプラスは1970年創業の食品輸入卸専門商社、トップ・トレーディング㈱の中の直販部として船出しました。大阪万博でニュージーランドパヴィリオンの手伝いをした創業者が『これからの日本は洋食の時代、ラム肉が売れる』という思いから起業したのが今に繋がっています。
洋食も高級店だけでなくカジュアル店も増えてきた1990年代になり、今のダイニングプラスに繋がるきっかけとなる出来事がありました。某婦人雑誌に人気シェフのおすすめ食材としてラム肉が載ったのです。すると「どこで買えるのですか?」という読者からの声がたくさん寄せられました。その頃から創業者の頭に『通販』の2文字がちらついて離れなかったそうです。
その後、職域販売のようなことをしていたのですが、本格的に通販と呼べるようになったのは2000年頃のことです。いろんな方の紹介で少しずつ増えてくるお客様に対して、「金曜市」と名付けた簡単なカタログを作って配布するようになりました。
(写真/ ダイニングプラスになる前の「金曜市」パンフレット)

驚くのはそのラインナップ。クロワッサン、プチパン、石窯パン、パイシート、ピザ、生ハム、鴨肉などなど。どれも今でも人気の定番商品です。作ったカタログを郵送して郵送かファックスでご注文を受け、冷凍倉庫の一部を2坪ほど借りて、1週間に1回金曜日に発送する。だから金曜市と呼んでいました。
【ダイニングプラス誕生】
その頃普及し始めたのがインターネットです。事務所では一人1台のパソコンが支給され、Email が一般的になってきていました。楽天市場が新聞やTVで取り上げられて脚光を浴びてきた頃、今後の通販はインターネットだ、ということで取り組みが始まりました。社内でこの新規ビジネスを担当したのは3名。システム兼販売担当、販売兼カスタマーサポート担当、物流担当。
(開業当時のダイニングプラス通販サイト トップ画面)
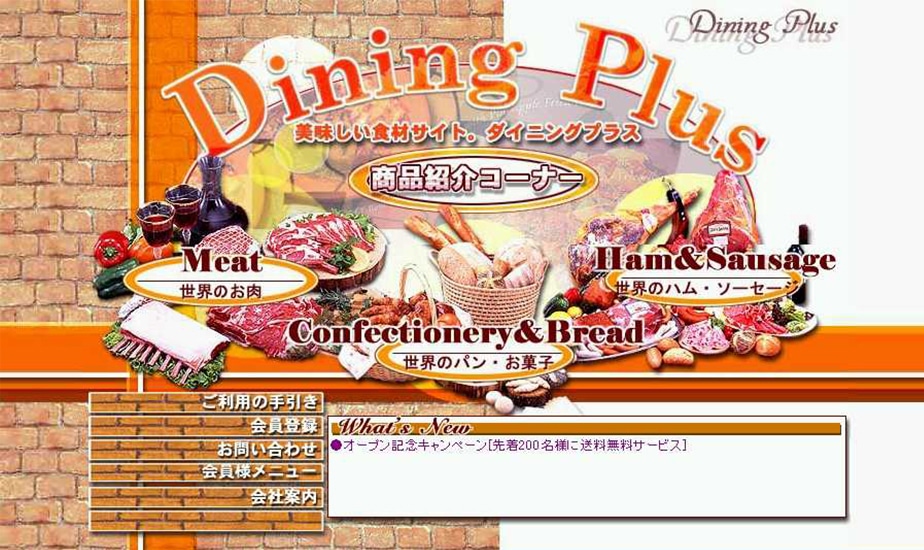
今も昔も通販で困るのは写真です。当時、社内の写真をかき集め、足りないものは撮影して準備しました。当時の撮影は販売担当2名が商品担当を決め、それぞれの自宅でデジタルカメラを使って撮影しました。撮影用のテントやライトもなかったので、何枚も撮っては確認して、コーディネートが崩れたら作り直して、と結構大変な作業でした。後からお互いに画像を確認して「太陽光がちょうどいい具合だった」「室内の暗さが案外よかった」などと、たまに見つかる奇跡の1枚を褒め合ったものです。
このダイニングプラス誕生と同時に物流拠点も当時としては本格的に作ることになりました。とはいえ、倉庫会社の建物の中にあった寮代わりに使われていた間取り1Kの部屋を借りて事務所兼、スタッフ休憩室とし、その倉庫会社の一部に冷凍商品保管スペースと梱包スペースを作って出荷体制を整えました。事務所にはオフィスデスク1つとプリンターを置いただけの簡素さながら当時は大いなる進歩でした。
(創業時のちいさな事務所)

【紙のカタログ論争】
ダイニングプラスは会社初のインターネット通販事業です。ここで問題になったのが紙のカタログが要るか、要らないか、の論争です。
「インターネット通販」と言うからにはお客様は画面をご覧になる。だから要らない。
いやいや、インターネットの画面があっても紙で確認したいと思うのが人情じゃないか、だから要る。
これでかなり議論になりました。当時スマートフォンはまだありませんから、ホームページを見るのはパソコン画面が前提です。インターネット回線も不安定だったり高額だったりしたので、画面だけでは販促活動ができない。というのが要る派の意見。一方、将来を見据えたら逆にカタログにお金をかけるべきではない、という要らない派の意見。
この論争でかなり時間をかけましたが、結局要る派がお金を極力かけない方向で半ば勝手に金曜市の延長線の手作りカタログを作って落ちつきました。
【驚きのお試しセット】
サイトオープンから1年経過した頃。今となっては考えられないような驚きのセットが登場します。名前は今もある「お試しセット」なのですが、驚きはその内容と価格。クロワッサンやチーズケーキなど総額5000円近くするものを580円で売り出したのです。
ダイニングプラスはモール出店をせず、自社サイトで運営することを決めてスタートしました。そうなると課題があります。
インターネットの森にころがった石ころ、いえ、砂粒のようなダイニングプラスをどうやって見つけてもらうのか?
当時の日本のインターネット使用状況を考えると広告で名もない砂粒を見つけてもらって買ってもらうことは難しいと考えました。
そこで、クチコミを狙う作戦としてこのびっくりお試しセットを考えたわけです。
これが大当たり。それまで1日の受注件数が10件を超えると「今日はすごいね」なんて言っていたのが一気に平均で30件を超え、多い日は100件を超えたのです。
当時のダイニングプラスにしては大変な事件とも言える毎日でした。
赤字のセットだったので2か月で販売が終わってしまいましたが、今でも伝説のお試しセットです。
このお試しセットがきっかけでお客様になってくださった方の中には19年たった今でも継続してご利用をいただいている方もいてくださいます。
>楽しい企画がいっぱいの20周年記念イベント開催中!特設ページはこちら
【株式会社ダイニングプラスへ】
2003年9月、トップ・トレーディング株式会社から分社して株式会社ダイニングプラスになりました。それと同時にサイトのリニューアルをし、本格的なカタログを作りました。
写真が大切であり、撮影に手間がかかるのはその当時から変わりません。販売担当者が撮影まで行なうためにはクオリティの問題と時間がかかります。その問題を考え続けた結果、ある食品専門スタジオと提携をして撮影をお願いすることになりました。そのスタジオ内にはデザイナーの方がデスクを持たれていて、そのご縁で立派なものができました。今では撮影をお願いすることもなくなりましたが、当時は大変お世話になりました。
(まるで雑誌のようだった紙カタログ)
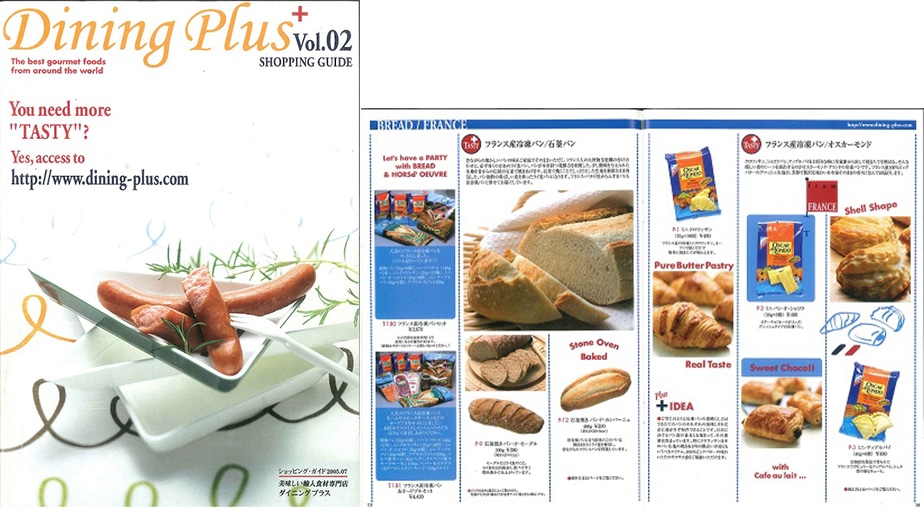
【フリーダイヤルつながらない事件】
こうして20年を振り返るといろんなことがありました。
あるとき、関西ローカルTV局の午後の情報番組でパンセットが取り上げられました。10分ほどの結構長い時間でダイニングプラスのパンが紹介され、TV画面にはパンセットの内容や問い合わせ先などが映りました。その瞬間です。フリーダイヤルの電話が鳴り始めたと思ったら、それはTVを見た方からのご注文でした。2回線しかないフリーダイヤル回線は切ったら鳴る、切ったら鳴る、を繰り返し、お客様からは「電話がつながらない」とお小言をいただく始末。その状態は3日ほど続きました。ホームページにもご注文は殺到して、たくさんのご注文をいただきました。2007年頃だったと思います。当時はまだ電話注文をされる方も多かったですね。
つい先日、別のTV局ですが、関西ローカル局の夕方の情報番組からパンセット取材の依頼を受け、放送されました。電話番号は出ず、ダイニングプラスという名前とホームページの画像の紹介。芸人さん達の実感こもった「美味しい」という言葉に反応されたお客様からかなりのご注文をいただきました。でもそこは2021年。ほとんどの方がホームページからご注文をくださり、時代の変化を感じました。
【新倉庫へ】
2011年9月。倉庫を移動し、より広いスペースで出荷に対応することができるようになりました。センター事務所も広い部屋になり設備も充実しました。
梱包、出荷の作業や小分け作業を外注するという選択肢もありますが、ダイニングプラスでは商品の輸入から検品、梱包、出荷を一貫して行なうことで、ひとつひとつのお荷物を見届けたいという思いから、創業時からかわらず、自社で出荷作業までを行なっています。現場のスタッフは直接販売作業に関わるわけではありませんが、梱包のプロです。自社のスタッフ同士が意見を出し合って、商品形態や梱包方法、それをどのようにご案内するかを決めます。時には箱や商品が潰れた状態で届いてしまってご迷惑をおかけすることもあります。そんなときも配送業者さんだけのせいにするのではなく、必ず情報を現場と共有して、改善点はないか、を常に考えます。ダイニングプラスの20年にとって、このセンター事務所は大切な役割を持っています。
【2019年リニューアルへ】
2019年4月。ホームページを大幅にリニューアルしました。
めまぐるしく進化するインターネット通販のさまざまなサービスを取り入れ、より魅力的な企画をご提供するためのリニューアルでした。
そして今年、ダイニングプラスは皆さまのおかげ様で20周年を迎えることができました。
インターネット通販の会社では古い方かもしれませんが、一般的にはまだヒヨッコで、未熟な点がたくさんあります。ご迷惑をおかけすることもあると思います。
リニューアル以降、より多くのお客様とホームページを通して繋がることができるようになりました。
皆さまからのご意見を参考にこれからも「美味しさを皆さまの食卓へ」届けられるよう精進してまいりますので、お気づきの点がありましたら是非、お寄せいただければと思います。
今後ともどうぞ、よろしくお願いします。
>感謝イベントがいっぱい!20周年記念特設ページはこちら
<ダイニングプラスについて>
2001年事業開始の輸入食品通販サイト。「読売テレビ」「関西テレビ」「ダンチュウ」や「エル・ジャポン」など、メディア紹介多数。だれもが知る高級ホテルやレストランが採用する高品質な輸入食品を、どなたでも1パックから購入できます。商社直営。
-
 【送料込み】欧州パンとこだわりのバターを愉しむ欲張りセット
【送料込み】欧州パンとこだわりのバターを愉しむ欲張りセット -
 【サンプル セット】7種類のお食事パンお味見用セット
【サンプル セット】7種類のお食事パンお味見用セット -
 【まるで高級ホテル】な早起きが楽しみになる朝食セット
【まるで高級ホテル】な早起きが楽しみになる朝食セット -
 【送料無料】ベルデンソ 無ろ過EXVオリーブオイル 3本セット
【送料無料】ベルデンソ 無ろ過EXVオリーブオイル 3本セット -
 薔薇と和紅茶のティーバッグ
薔薇と和紅茶のティーバッグ -
 ベラミーズパイシート フレッシュバター100% 300g
ベラミーズパイシート フレッシュバター100% 300g -
 2種チーズのバスクチーズケーキ
2種チーズのバスクチーズケーキ -
 ハーブ香るブラートヴルスト ドイツ職人の絹引き焼きソーセージ
ハーブ香るブラートヴルスト ドイツ職人の絹引き焼きソーセージ -
 【電子レンジ対応】 エスカルゴ XLサイズ 12個入(殻付き/ガーリックバター入り)
【電子レンジ対応】 エスカルゴ XLサイズ 12個入(殻付き/ガーリックバター入り) -
 焼くだけ!パンオショコラ 発酵バターが香るフランス産 Bake up生地 75g×3個入り
焼くだけ!パンオショコラ 発酵バターが香るフランス産 Bake up生地 75g×3個入り -
 焼くだけ!大きなクロワッサン 発酵バターが香るフランス産 Bake up生地 60g×4個入り
焼くだけ!大きなクロワッサン 発酵バターが香るフランス産 Bake up生地 60g×4個入り -
アップルパイ 100g×2個
-
 ブルターニュ産 クッキー(ガレット)3種アソート缶(オレンジフラワー)
ブルターニュ産 クッキー(ガレット)3種アソート缶(オレンジフラワー) -
 贅沢いちごジャム (プレザーブスタイル)
贅沢いちごジャム (プレザーブスタイル) -
 パテ ド カンパーニュ ブロック (田舎風豚のパテ)オーセンティック
パテ ド カンパーニュ ブロック (田舎風豚のパテ)オーセンティック
マジパンの町、リューベックで食べたソーセージとラード|スタッフ海外体験記
目的は展示会とココアメーカーの訪問。
ドイツのココアメーカーとの出会いとそのお勧めポイントはまた別の機会に語るとして・・・
ココアメーカーはハンブルグから車で北東に小一時間のところにあります。
日本だったらもっとかかるかもしれませんが、時速制限のないアウトバーンを良い車ですっ飛ばしてくれるので、体感的には30分程度のドライブです。

ちなみに、メーカー担当者のHansが運転してくれる横の助手席でおしゃべりしながら向かうのですが、時々速度メーターを見てぎょっとします。
ちら見すると180㎞/hを超えていたので思わず写真を撮ったところ、Hansが調子に乗ってにやにやしながら速度を上げてきました。恐々と手振れしながら199㎞/hまでは写真に撮ったのですが、これ以上調子に乗せてはいけない!と自粛したので、200㎞/h越えは撮れませんでした。。。
さて、無事に工場に到着し、メーカーとの打ち合わせはお昼過ぎまでかかりました。ランチも取らず、何とか終えたのは14時頃。
そこでHansから提案が。。。
このままハンブルグに戻っても良いけど、近くに素敵な町があるから行ってみない?
この日は出張最終日で、商談も無事に終わったのでその提案を歓迎してその町に向かいました。


リューベック
中世期にバルト海交易の主要都市として栄えた都市だそうです。地図で見るとドイツの北端に近く、デンマークやスウェーデンはすぐ近くです。旧市街は中世の雰囲気を残していて、ユネスコの世界文化遺産に登録されています。
その名物はマジパン。ニーダーエッガーという有名なマジパン屋さんが市庁舎の近くにあります。

店内はマジパンのミニ美術館とでも言いたくなるような光景。テーブルコーディネートされたきれいな食卓にはステーキや生ガキが盛り付けられ、それらが実はマジパン細工で作られているのです。冷蔵のショーケースにはマジパンを使ったケーキが並び、たくさんの人たちが並んで買い求めています。

また別のコーナーには小さなカフェカウンターがあり、そこにはマジパンクリームのベニエ(揚げパン)。マジパン独特の杏仁のような香りはほのかで、とても上品にベニエの生地とマッチしていました。
このマジパン屋さんで人気のチョコレートコーティングされた代表的なお菓子はドイツのお土産としても定番ですが、お店にはお土産品だけでは表せないマジパンの奥深い世界が広がっていたのでした。
さて、散策の途中で良い匂いがしてきました。匂いに釣られて歩みを進めて見つけたのはソーセージの屋台。

2月なのでまだ寒い時期なのですが、屋台からは熱気と美味しい香りが漂ってきます。ランチを抜いていたので、ここで食べないわけがありません。
大きな円形の炭焼きグリルではソーセージがこんがりと焼かれ、隣には真ん中に切れ込みの入った半焼成のプチパンが一緒に焼かれています。
ほんのりと色づいたパンにソーセージを挟むと紙でくるんで「はい!」と手渡されます。 せっかくなのでホットワインと一緒に。。。

ソーセージはドイツらしくお肉の旨みにあふれ、しっかりしたボリューム。パンは添え物程度にも見えますが、シンプルな味わいなのでソーセージにはぴったりです。そしてほんのり甘くてスパイスの効いたホットワインが体を更に温めてくれます。
寒い季節のこの組み合わせは何と言っても最高!

お腹も心も満足して散策を続けているとnice place で一休みしよう、と連れて行かれたのは町角の古い建物。重い扉をあけて入ると大きな空間が広がっていました。天井には昔の帆船の模型がつるされ、そのお店の名前が「船員組合」であること聞いて納得。
かつては本当に船員組合として使用されていたこの建物からもリューベックが交易で栄えていたことが垣間見えます。
店内は広く、私たちが腰を落ち着けたスペースは広いホールのようになっていて、ピカピカに磨かれた木製の長椅子と黒光りするような天井が印象的。
ここに座って各国の船乗りが会話したのかな、などと空想が膨らみます。
こんな時にはやっぱり昔もビールを飲んだのではないでしょうか。

そしておつまみにも伝統を感じる1品Brot & Schmalz(パンとラード)
作り方ははっきりとわからないのですが、ラードには飴色の玉ねぎとジュニパーベリーが混ざっています。

そのラードを薄切りのライ麦パンに塗っていただくのです。
このラードに似たようなものをポーランドのレストランの前菜でも見たことがあり、おそらく北ヨーロッパのものなのでしょう。
そしてこんな時はやっぱりライ麦パンですよね。白い柔らかいパンよりもライ麦のほんのりとした酸味と香りがラードに合わせた時にはぴったり!
思いがけず出会った旅の思い出でした。
<ダイニングプラスについて>
2001年事業開始の輸入食品通販サイト。「読売テレビ」「関西テレビ」「ダンチュウ」や「エル・ジャポン」など、メディア紹介多数。だれもが知る高級ホテルやレストランが採用する高品質な輸入食品を、どなたでも1パックから購入できます。商社直営。
-
 ドイツ職人シリーズ 4種のソーセージ
ドイツ職人シリーズ 4種のソーセージ -
 ヴァイスヴルスト ドイツ職人の白ソーセージ
ヴァイスヴルスト ドイツ職人の白ソーセージ -
 ハーブ香るブラートヴルスト ドイツ職人の絹引き焼きソーセージ
ハーブ香るブラートヴルスト ドイツ職人の絹引き焼きソーセージ -
 ふわもち食感 サンドイッチ チャバタ 130g×1個
ふわもち食感 サンドイッチ チャバタ 130g×1個 -
バタープレッツェル 79g×2個入り
-
 三角 プレッツェル 85g×2
三角 プレッツェル 85g×2 -
 エキストラホット グルメソース カレー(カレーケチャップ辛口)
エキストラホット グルメソース カレー(カレーケチャップ辛口) -
 タスマニア産マスタード ホールシードタイプ
タスマニア産マスタード ホールシードタイプ -
 りんごとカスタードのタルト 約21cm10カット フランス製 (タルトノルマンディー)
りんごとカスタードのタルト 約21cm10カット フランス製 (タルトノルマンディー) -
石窯焼き パン オ セーグル (ライ麦パン)
-
 プチパン プレーン 35g×5個入り
プチパン プレーン 35g×5個入り -
 贅沢いちごジャム (プレザーブスタイル)
贅沢いちごジャム (プレザーブスタイル) -
 ブレス産 AOP発酵バター 250g
ブレス産 AOP発酵バター 250g -
 【送料込み】欧州パンとこだわりのバターを愉しむ欲張りセット
【送料込み】欧州パンとこだわりのバターを愉しむ欲張りセット -
 【送料無料】ベルデンソ 無ろ過EXVオリーブオイル 3本セット
【送料無料】ベルデンソ 無ろ過EXVオリーブオイル 3本セット
フランスの春を告げる卵|上野万梨子さんのフランスレポート

鳥の雛が殻を割って誕生する姿から復活のシンボルと考えられるのが卵です。毎年春分の日を過ぎて初めての満月の日の、そのまた次の日曜日と決まっている復活祭が近づくと(2021年は4月4日の日曜日)卵型のショコラや鳥の巣に卵のデザインのお菓子がウィンドーに並びはじめます。そんなことからフランスで卵といえば、イースターに向かって春の訪れを象徴するものなのです。

春の訪れが近いことを告げる満開のミモザと、パリ7区、グルネル通りのお惣菜屋さん、Lastre の「グリーンアスパラガスのミモザ」
とはいえ、鶏卵 Oeuf de pouleは一年中のものですが、季節の訪れを感じさせてくれるのが鵞鳥の卵 Oeuf d’oie です。花屋の店先にフサフサに開花したミモザが並ぶ頃、冬から春に移り変わる限られた期間のみ朝市に並びます。

気候変動からでしょうか、ひと昔前に比べて、近年はお目見えの時期が早まりつつあるようです。写真は家の近く、グルネルの朝市のスタンド。鶏卵の三倍ほどの大きさで、一個ずつ縦にして新聞紙でくるみ、包み終わりの紙の先端を指でひねっただけで手渡してくれるのですが、両手がすでに荷物でいっぱいでは持ち帰るのも危なっかしいものなのです。
食べ方を尋ねれば誰もが同じ答え。「鶏の卵と同じよ。目玉焼き、ゆで卵、オムレツ、お菓子、なんでも、普通の卵と同じように」。
ということで、まずは目玉焼きと考えましたが、この大きな卵を最初に割った時にはちょっと勇気がいったものです。鵞鳥の卵とわかってはいても、何か得体の知れないものが出てきたらどうしよう、、、と。
さて結果は、鶏卵の方がはるかに美味しい。ネタッと舌に張り付くような黄身のテクスチャーも香りもちょっと苦手です。ということで、私にとって鵞鳥の卵は春を告げてくれる風物詩のようなもの。食べたいとは思わないけれど、季節のめぐりを感じて気持ちを浮き立たせてくれるものなのです。

フランスの鶏卵は雌鶏の生きる環境に応じて4段階に分けて流通されます。殻に“0FR”(ゼロFR)とスタンプされていたら、それはBIOの卵である証です。屋内外を自由に行き来し、国のBIO認定を受けた草や餌を食べて育った鶏の卵。屋内でぎゅうぎゅう詰めの、それこそ密な環境ではなく、「戸外で羽をバサバサと広げてホコリをはらうことができ、ストレスなく眠りにつけて、自分の巣で卵を産むことができる」鶏が産んだ卵、それがゼロFRなのです。そして1FR、2FR、3FRと、環境や餌、鶏同士の密度に応じて、卵の質レベルは明確に示されているのは素晴らしいことです。
日本の鶏卵は、いつの頃からか、黄身が濃い色をしているほど栄養価が高く美味しいと誤解されてきたようです。そのため餌にパプリカなどを混ぜ、黄身の色が濃くなるように調整した卵が多いようです。

ナチュラルな餌を食べて育った鶏が産んだ卵の黄身は、透明感のある薄い黄色をしているものです。加熱した後では卵の鮮度や黄身の色がわからなくなりますから、上の写真は蒸す前の状態。健康な卵の美しさがよくわかることでしょう。
こんな簡単な卵料理も、家庭ではメイン料理前の一品になります。
焼き皿にバターを薄く塗り、薄切りハムをのせ、生クリームを適量、塩少々、そこに卵を割り落とします。オーブンで湯せん焼きでは時間がかかりますが、フライパンの底1センチ弱に湯を沸かしたところに器を置いて、蓋をかけて蒸せば、ほんの数分で出来上がります。このような平皿ですと調理時間は短くすみますが、プリン型やココットでも。
ところで、後ろに見えるグリーンの箱に入っている卵は、普通のBIO卵の倍以上の価格です。その理由は、卵を産まなくなった雌鳥を殺処分せずに、自然に死ぬまで農家で見届けることをしているためなのです。これは大衆的なスーパーの棚にも並び、価格が高い理由に納得し、志高い生産者を応援する気持ちで購入する人が少なくないことがわかります。
こういう卵なら、割りほぐしてオムレツを作る前に、まずは茹で卵で味わいたいものです。とろりと半熟の黄身に、小さなスプーンの先にほんの少々のメープルシロップをとってたらし、塩をふって。
パリに暮らして嬉しいのは 「普通のものが当たり前に美味しい」ということ。普通のものとは高級だったり珍しい食材ではない、毎日の料理に使うもののことで、卵もその一つです。コロナが落ち着いてフランスに旅する時が来たら、ホテルやカフェの朝食で半熟卵を注文してみましょう。焼きたてにバゲットをちぎって、それで柔らかな黄身をツンツンして!

<ダイニングプラスについて>
2001年事業開始の輸入食品通販サイト。「読売テレビ」「関西テレビ」「ダンチュウ」や「エル・ジャポン」など、メディア紹介多数。だれもが知る高級ホテルやレストランが採用する高品質な輸入食品を、どなたでも1パックから購入できます。商社直営。
-
石窯焼き風 ライ麦パン(パン・オ・セーグル)
-
 そのまま食べられるグリーンアスパラガスカット120g
そのまま食べられるグリーンアスパラガスカット120g -
 優しい味わいのホワイトハム (ジャンボンプティ ブラン)
優しい味わいのホワイトハム (ジャンボンプティ ブラン) -
 ブレス産 発酵バター ドゥミセル (加塩) 250g
ブレス産 発酵バター ドゥミセル (加塩) 250g -
 薔薇のハーブソルト(ミル付き)
薔薇のハーブソルト(ミル付き) -
 3種のチーズのキッシュ(タルトフロマージュサレ)
3種のチーズのキッシュ(タルトフロマージュサレ) -
 焼くだけ!大きなクロワッサン 発酵バターが香るフランス産 Bake up生地 60g×4個入り
焼くだけ!大きなクロワッサン 発酵バターが香るフランス産 Bake up生地 60g×4個入り -
 カヌレ ド ボルドー 60g×2個
カヌレ ド ボルドー 60g×2個 -
 ブルターニュ産 クッキー(ガレット)3種アソート缶(オレンジフラワー)
ブルターニュ産 クッキー(ガレット)3種アソート缶(オレンジフラワー) -
 りんごとカスタードのタルト 約21cm10カット フランス製 (タルトノルマンディー)
りんごとカスタードのタルト 約21cm10カット フランス製 (タルトノルマンディー) -
 スモーク オイルサーディン ラトビア産
スモーク オイルサーディン ラトビア産 -
 パテ ド カンパーニュ ブロック (田舎風豚のパテ) スタンダード
パテ ド カンパーニュ ブロック (田舎風豚のパテ) スタンダード -
 【送料込み】欧州パンとこだわりのバターを愉しむ欲張りセット
【送料込み】欧州パンとこだわりのバターを愉しむ欲張りセット -
 【送料無料・ギフト包装】ベルデンソ 無ろ過EXVオリーブオイル 2本セット(箱入り)
【送料無料・ギフト包装】ベルデンソ 無ろ過EXVオリーブオイル 2本セット(箱入り) -
 【送料込み】週末ご褒美プチセット
【送料込み】週末ご褒美プチセット
女性にうれしい!ヘルシー豪華なおうちごはん(国際女性デー)
ダイニングプラスでは昨年、今年と国際女性デーをとりあげ、大反響をいただきました。
2021年国際女性デーのテーマはぐっと気軽に
\「女性におすすめのゴージャス簡単ヘルシーおうちごはん」(長い)!/
ジューシーなお肉、ぶあついサンドイッチ、あつあつピザ…。おうちごはんは自分の好きなものを思いっきり楽しみたい! そんな願いをかなえる、よりヘルシーで満足できる「おうちごはん」tipsをお届けします。
_spring party2.jpg)
【お肉】
がっつりお肉を楽しみたいけれどダイエットが気になる…そんな女性におすすめしたいのが脂肪の少ないお肉。おすすめの一つ、Tボーンステーキはその名の通りT字型の骨が左右のお肉を分けている形でおなじみです。実はこのステーキ、骨をはさんで左右がサーロインとフィレ肉という、なんとも贅沢な牛肉なんです。

Tボーンステーキは脂質の少ない赤身肉なので、カロリーが低めなのはもちろん、お肉の旨みを味わいながら胃もたれしにくいのもうれしいポイント。あまり扱っているお店はありませんが、 放牧された仔牛肉なら淡い赤身で柔らかく、おいしいお肉を存分に味わえます。 ダイニングプラスでお取扱いしているTボーンステーキは、しかも仔牛の中でもスタークと呼ばれる、餌に草を食べているタイプなので牛肉に近い歯ごたえと旨み、仔牛の柔らかさを併せ持つ美味しさ!
また温かい料理がおいしい時期なら仔牛のチークミート(ほほ肉)もおすすめ。一般のお肉屋さんでもあまり扱いがなく、聞きなれないかもしれませんが実はお料理はとっても簡単。こちらも脂質が少なく、コトコト煮込むだけで高級レストランのようなカレーやシチューが手間なくできあがります。
保温鍋に入れておくだけで極上の煮込み料理が味わえるので、忙しい女性のおうちごはんにもおすすめですよ。
(おすすめ)<ほろほろくずれるお肉の幸せ>仔牛 チークミート (ほほ肉)

【ピザ】
なぜか急に食べたくなるピザ。せっかく食べるなら生ハムを山盛りにオンして贅沢な生ハムピザはいかがでしょう。生地がふっくらと軽めでヘルシーなナポリ風ピザにはイタリア産生ハムがぴったり。 さらにルッコラをプラスすれば、栄養バランスもぐっとよくなりそう。ピザでふんわり温まった生ハムのとろける美味しさは格別ですよ。また日本ではまだ珍しいですが、白トリュフの香りを贅沢に移した「白トリュフオイル」を使えば豊かな風味と香りでまさに高級店のトリュフピザ!おいしいものを食べた満足感にお腹も心も満たされます。
(おすすめ)関西テレビで紹介!グルメ芸能人もおすすめのイタリア オリタリア社白トリュフオイル

(おすすめ)品質と価格に自信あり!豚肉と塩だけで作った生ハム切落とし
(おすすめ)日本初!認可の栄誉 フランス産 ジャンボン ド バイヨンヌ IGP
【パン・パスタ】
「おうちごはん」ではたくさんのお野菜やたんぱく質もとりたいもの。そこでおすすめなのがフランス産のお食事パン。ヨーロッパの小麦は甘みがあり、かむほどに味わいがあるので満足感もぐんとアップ。発酵商品でもある生ハムをたっぷりはさんでいただけば、旨味のハーモニーでグルメな女性も大満足の簡単サンドができあがります。
(おすすめ)<読売テレビで紹介>ヨーロッパ冷凍パンセットのお食事パンバージョン

満腹感を満たすなら温かいスープ系のニョッキもおすすめ。もちもちしたニョッキはかむことでおうちごはんの満足感が得られます。トマトやクリーム系のパスタソースだけではなく、スープやおみそ汁に入れる方もおられ、意外と便利な万能食品です。
(おすすめ)イタリア・パスタ専門メーカーの冷凍もちもちニョッキ

国際女性デーを祝って、こんなごちそうをおうちで試すのも楽しそう。
普段のおうちごはんにいつもとちょっと違う食材を組み合わせると、お店のような美味しいごはんが簡単にできあがります。おいしい輸入食品が、あなたの毎日に優しい潤いをもたらしますように。
こちらもどうぞ:(反響をいただいた、2020年の国際女性デー記事です)
「ブログ100年前の女性のくらし(国際女性の日)」
<ダイニングプラスについて>
2001年事業開始の輸入食品通販サイト。「読売テレビ」「関西テレビ」「ダンチュウ」や「エル・ジャポン」など、メディア紹介多数。だれもが知る高級ホテルやレストランが採用する高品質な輸入食品を、どなたでも1パックから購入できます。商社直営。
-
 【サンプル セット】7種類のお食事パンお味見用セット
【サンプル セット】7種類のお食事パンお味見用セット -
 【送料込み】欧州パンとこだわりのバターを愉しむ欲張りセット
【送料込み】欧州パンとこだわりのバターを愉しむ欲張りセット -
 薪窯ナポリ風ピザ マルゲリータ 200g
薪窯ナポリ風ピザ マルゲリータ 200g -
 生ハム切り落とし ボリュームパック スペイン産
生ハム切り落とし ボリュームパック スペイン産 -
 ビーフ100% ひき肉ステーキ(ステークアッシェ) 100g×2
ビーフ100% ひき肉ステーキ(ステークアッシェ) 100g×2 -
 仔牛 チークミート1.5kg (ミルクフェッドヴィ―ル ほほ肉)
仔牛 チークミート1.5kg (ミルクフェッドヴィ―ル ほほ肉) -
 フランス伝統生ハム IGP ジャンボン ド バイヨンヌ 200g
フランス伝統生ハム IGP ジャンボン ド バイヨンヌ 200g -
 ポテトニョッキ 1kg
ポテトニョッキ 1kg -
 薔薇の花びら茶
薔薇の花びら茶 -
 2種チーズのバスクチーズケーキ
2種チーズのバスクチーズケーキ -
 トリュフ香るエキストラバージンオリーブオイル
トリュフ香るエキストラバージンオリーブオイル -
石窯焼き パン オ セーグル (ライ麦パン)
-
 薪窯ナポリ風ピザ 3チーズ 200g
薪窯ナポリ風ピザ 3チーズ 200g -
 ダッテリーノトマトのトマトジュースづけ (皮なし)400g
ダッテリーノトマトのトマトジュースづけ (皮なし)400g -
 【20%OFF!送料無料】みんなが集まる休日わいわいセット
【20%OFF!送料無料】みんなが集まる休日わいわいセット
おうちで手軽にガレットデロワ
今年は本場フランスの「焼くだけミニアップルパイ」で試してみませんか?

「今年のフェーヴは何ですか?」
子供たちがパン屋、お菓子屋を尋ねて回る、年が明けるとフランス各地で見られる光景です。フェーヴとはそら豆を意味するフランス語ですが、子供たちが知りたいフェーヴはガレット・デ・ロワに入っているオマケのことです。

ガレット・デ・ロワとは日本でも最近は知られるようになっていますが、キリスト教を代表するお祝いのひとつ、公現祭(エピファニー)の日に食べられるお菓子です。
公現祭とはイエスが3賢人の訪問を受け、洗礼を受けたとされる日で、この「3賢人」は「3人の王(Three Kings)」と言われることもあり、この「王」にちなんで王様のガレット、というお菓子の名前に繋がったようです。 王様のガレットにフェーヴを入れるようになったのは年始に行なわれた別のお祭りと組み合わされたということなのですが。。。
歴史の話はさておき、現代のガレット・デ・ロワの話。
ご存知の方も多いと思いますが、このガレット、地方によって違いはあるようなのですが、一般的には折りパイ生地で作られる丸いパイ菓子です。中にはアーモンドクリームを入れ、表面はいろんな模様を付けて溶き卵をぬってこんがりときれいな焼き色を付けて作られます。サイズは各お店でまちまち。7~8号(21~24㎝)ぐらいが多かったように思います。そのパイ菓子のアーモンドクリームの中にはこっそりフェーヴが仕込まれていて、切り分けてそれぞれがお皿に取り、食べている最中にフェーヴが出てくると「僕が王様!」「私が王女様!」と申告し、王冠をかぶってその日一日は皆がその人に従って遊ぶのです。
元は当たりを示すフェーヴとして豆や金貨を入れていたようですが、今では陶器の小さなフィギュアを入れて作られます。 クリスマスが終わると同時に『待ってました!』とばかりにガレット・デ・ロワが店頭に並び、お店ごとに自慢のガレットに入っているフェーヴのシリーズを貼りだしたり、貼られなかったり。。。
私がいたストラスブールのBoulangerie Patisserie(ブーランジェリー・パティスリー/パンとお菓子のお店) にはポスターが貼られていなかったので、子供たちが数人単位でやってきては「今年のフェーヴは何ですか?」と聞くのです。
そこで例えば「今年はLe Petit Prince(星の王子様)シリーズですよ」などと答えると子供たちはガヤガヤしながら楽しそうに帰って行くのです。いろんなお店に聞いて回ってお母さんに「今年は〇〇パン屋のガレットにして!」などとリクエストするのでしょう。
また、このガレット・デ・ロワは1月いっぱい売られているので、今日は○○パン屋のガレット、明日はXX菓子屋のガレット、と日替わりで楽しむ人も多いのでしょう。
ダイニングプラスでも一時期、焼くだけで出来上がるフランスのガレット・デ・ロワを販売していたのですが、「フェーヴが危険」という意見に負けて今は取扱いをしていません。 (いつか再販売画策中!)
そこで今回おすすめしたいのは、安全にガレット・デ・ロワ気分を味わう方法です!

ダイニングプラスで人気のミニアップルパイ。
フランス産のバターをリッチに使ったパイ生地で甘酸っぱいりんごピューレを包み、小さなシェル型に成形して冷凍したアップルパイです。大きなサイズもあるのですが、特に今年はこのミニがおすすめ!
切り分ける手間なく、ひとつひとつ自分で手に取ることができるのですから!!
>>【フランス産ミニアップルパイ】
では、どのように楽しめば良いか?

準備するもの:
*ミニアップルパイ(人数分)
*フェーヴ(なければ水に浸す前の硬い豆やコインなど何でもOK!)
*王冠(最近は紙のきれいな王冠がお菓子材料のお店などで売られています!)
①ミニアップルパイを天板に並べ、少し解凍する
(表面に少し汗をかくぐらいがベスト。特に冬は室温が低いので解凍した方がきれいに焼けます。冬なら20~30分程度)
②180℃に予熱したオーブンで20~25分焼き、取り出して粗熱が取れるのを待つ
③待つ間にフェーヴをきれいに洗って乾かしておく
④熱がとれたアップルパイの裏側にバターナイフなどで穴をあけ、フェーヴを忍ばせる


(奥にぎゅっと押し込んでおいてください。)
⑤きれいに並べて食卓へ!

家族や仲間が集まったら一人1つ取ってもらいます。
この時、「裏見るの厳禁!」と周知しておいてください。
あとは全員で割ってみます。
\残念!はずれ~/

\やった~♪当たり!!/

今回使ったのはホンモノのフェーヴだったので、少し重さがあって、実は持ったらわかってしまいました。
大豆とか1円玉とかの小さいものだと仕込むのも簡単で持ってもわからないかも!
この遊び、結構盛り上がるので是非試してみてくださいね!
<ダイニングプラスについて>
2001年事業開始、「dancyu」や「日経プラス1」など取材多数。一流プロ愛用の海外食品を1パックからお届けする通販です。商社直営。
-
 【サンプル セット】12種類のデニッシュ&パイお味見用セット
【サンプル セット】12種類のデニッシュ&パイお味見用セット -
 【送料込み】欧州パンとこだわりのバターを愉しむ欲張りセット
【送料込み】欧州パンとこだわりのバターを愉しむ欲張りセット -
 ベラミーズパイシート フレッシュバター100% 300g
ベラミーズパイシート フレッシュバター100% 300g -
 ブレス産 AOP発酵バター 250g
ブレス産 AOP発酵バター 250g -
 クリスマス シュトーレン 500g
クリスマス シュトーレン 500g -
 【電子レンジ対応】 エスカルゴ XLサイズ 12個入(殻付き/ガーリックバター入り)
【電子レンジ対応】 エスカルゴ XLサイズ 12個入(殻付き/ガーリックバター入り) -
アップルパイ 100g×2個
-
ミニアップルパイ 40g × 5個
-
 6種のベリー 北欧カフェデニッシュ 2個入
6種のベリー 北欧カフェデニッシュ 2個入 -
 りんごとカスタードのタルト 約21cm10カット フランス製 (タルトノルマンディー)
りんごとカスタードのタルト 約21cm10カット フランス製 (タルトノルマンディー) -
 ハーフバゲット 140g×2個入り
ハーフバゲット 140g×2個入り -
 贅沢いちごジャム (プレザーブスタイル)
贅沢いちごジャム (プレザーブスタイル) -
 箱入り薪窯ピザ マルゲリータ 200g
箱入り薪窯ピザ マルゲリータ 200g -
冷凍 ポム アリュメット (フレンチフライポテト) 450g
-
 パテ ド カンパーニュ ブロック (田舎風豚のパテ)オーセンティック
パテ ド カンパーニュ ブロック (田舎風豚のパテ)オーセンティック
2020年パリのクリスマス|フランスレポート
COVID-19に始まり、そして終わろうとしている2020年ですが、
皆様ご無事にお過ごしでしょうか。
春から初夏にかけて、フランスでの1回目のロックダウンはパリで過ごした私ですが、
10月末には一時帰国し、フランスの状況を案じつつ今は東京で過ごしています。
フランス人にとって家族との絆を深める大切な行事であるノエルですが、
この状況下で今年はどのように過ごすのか、そして街の様子が気になります。
そこで、シネマ、ガストロノミー、そしてフランスの生活文化を主なフィールドとして活躍なさる
ジャーナリスト、魚住桜子さんに、2020年12月のパリをレポートしていただきました。
桜子さんは、同じくジャーナリストのフランス人のご主人と、15歳の娘さんとパリ16区に在住。
私のレシピ本を活用して料理を作っては感想を寄せてくださる友人です。
それでは桜子さん、よろしくお願いいたします!
上野万梨子
【特別ブログ】|文・写真:魚住桜子

街路樹の葉がすっかり落ちて、グレーの雲がパリの空を覆う頃。 夜がいっそう深まり、人々の心にどんよりとした影を落とす、少し辛い時期がやってきました。 それにしても今年のパリは異例づくしです。 急速に拡大した第2波の到来で10月30日からフランス全土は2回目のロックダウンに入りました。 例年なら10月中旬以降にはクリスマスの特設コーナーが設けられ、街中が沸き立つような高揚感に包まれるのに……。 秋から冬にかけてのパリの風物詩、美術館や画廊のレセプション・パーティー、バレエ、オペラ、観劇やコンサートなど、華やかな社交ライフはひっそりと息を潜めました。

(左:フランス、パリ16区ラヌラグ公園の11月頃の様子 /右:16区パッシー地区ショッピングモール「パッシープラザ」内の店舗シャッターがしまっている様子)
今回のロックダウンは当初、1カ月間の予定でしたが、一時は一日の感染者が8万人を超えるほど拡大して、長引くことが予想されています。 じわりじわりとロックダウンの成果は現れているものの、まだ収束の見通しは立っていません。 今回は前回と違って保育園から高校まで授業が行われているので、自然を求めてメゾン・ド・カンパーニュ(田舎のセカンドハウス)に移動するファミリーもいません。 通常どおりに営業できない花屋やブティックは「クリック&コレクト」と呼ばれる事前に電話やインターネットで予約して店頭で引きとるシステムで営業を続ける店もありました。

(クリック&コレクトで営業を続ける花屋の様子)
11月28日からは3段階に分けて規制が緩和されることになりました。 「クリスマス商戦」をかけて、すべてのブティックの営業再開が認められ、買い出し運動のための外出は1時間以内から3時間に、自宅から1キロ圏内は20キロ圏内に拡張。 21時から翌朝7時までの夜間外出禁止は継続され、反すると罰金135ユーロ(初回)が課せられる規制はしばらく続く模様です。
感染の状況が落ちつけば12月15日からは映画館、美術館、劇場などが再開。 年を越しても休業を余儀なくさせられるのはレストラン、カフェ、ジムなどのスポーツ施設で1月20日頃まで待たねばならない厳しい状況が続いています。
フランスでクリスマスは家族と一緒に過ごす、かけがえのないひととき。 日本のお正月が家族で集まる一年で最も大切な行事であるように、クリスマスイヴは家族が集まり夕食をともにするビックイベントです。 コロナ禍でも今年は特別措置で12月24日と31日は自由に行動することができると発表されたばかり。 フランス人は少しほっとした様子をみせています。 普段は倹約家として知られるパリジャンたちもクリスマスには散財します。 家族のメンバーひとりひとりに贈り物を用意する習慣があるので、準備も大変です。

11月後半、シャンゼリゼのイルミネーションが一斉に輝きだすと、クリスマスの食材が店頭にお目見えします。 ブレス産のチキン、トリュフ入りのブーダンブラン、フォアグラ、キャビア、スモークサーモン、ビッシュ・ド・ノエルetc。

魚屋さんの店頭ではとびきり新鮮な生牡蠣、ランギュスティーヌ、数種の貝を盛った「海の幸の盛り合わせ」が堂々と鎮座します。

ショコラティエもクリスマスシーズンは年間最大のかき入れ時で、詰め合わせボックスや高価なマロングラッセが飛ぶように売れていくのです。
この時期になると私の自宅近くのパッシー通りは大変な賑わいになり、大きなもみの木を抱えたムッシューや、孫へのプレゼントを車に運び込むパピー(祖父)たちの奮闘ぶりが見られます。

(パッシー界隈のクリスマスショップの様子)
クリスマス・イヴをどこで過ごすか。フランスの家族や恋人たちは悩みます。 近距離に親が暮らす場合は24日のイヴは妻の実家で、25日の昼食は夫の実家で、そして翌年は交代する家族もあれば、どんなに離れていても、クリスマス前後を妻側と夫側の家族の実家で数日ずつ分けて過ごすファミリーもいます。 友人のクリスチーヌはパリ19区の実家でイヴの夕食を過ごした翌朝、夫の実家があるグルノーブルへ旅立つのが習慣。そして友人たちと過ごす大晦日までにパリに戻ってきます。 離婚率が50パーセントを超えるパリでステップファミリーはまったく珍しい光景ではありません。 元妻や元夫が昔のファミリーと夕食を共にしたり、新しいパートナーや新しくできた子供を伴う場合もあり、十人十色の複雑さ。 クリスマスの時期になるとフランスはカトリックの国の素顔を取り戻して家族中心主義になりますが、たとえ数日だけでも太陽を求めて南の島へ旅立ってしまうファミリーもいます。 我が家はパリ郊外に住む義理の両親とパリ20区に暮らす義理の弟一家、そして私たち一家の三世代が一つの家族の集合体を構成しています。

(クリスマス料理をつくっているキッチンの様子)
毎年クリスマスシーズンに弟一家はマルチニークやグアドループといった南国にエスケープするので、イヴの夜は義理の両親と私たち夫婦と娘の五人で過ごすのが恒例です。 では、クリスマスの家族の集いがないかといえばそうではないのです。我が家では1月1週目のランチが“レヴェイヨン”(クリスマスやお大晦日の晩餐)と決まっていて、不在の罪滅ぼし(?)なのか、料理はすべて義理の弟が拵えます。

(ウニと帆立貝のクリーム添え)

(ウニとスクランブルエッグの前菜)

(クリスマスの飾り付けをしたパリブレスト)
星付きシェフの料理講座に通っていたこともあるほど、食いしん坊の義弟はウニと帆立貝のクリーム添え、一本釣りのスズキのシャンパーニュ蒸し、モリーユ茸とブレス鶏の黄ワイン(ヴァン・ジョーヌ)煮込みなど、毎年、趣向を凝らした料理を作ってくれます。 フランスの伝統的なレヴェイヨンは前菜に生牡蠣、スモークサーモン、フォアグラなどの後に、メインは七面鳥、去勢鶏、ホロホロ鶏、若鶏など家禽類のローストや煮込みが多いといわれますが、実際は家庭によって三者三様。 それぞれの出身地やルーツによって献立は変わってくるのです。

(グランド・エピスリー右岸店と店内の様子)
今年のクリスマスはかつてないほどサスペンス色を帯びています。
地方の実家でクリスマスを過ごしたり、あるいはフレンチアルプスのシャレーで休暇を過ごすことができるのか。 どのような方法で人とつながり楽しみを分かちあっていくのか。 例年とは異なるクリスマスになりますが、平常心とモチベーションを保ちながら心豊かに生きていく術を、だれもが模索しています。
<ダイニングプラスについて>
2001年事業開始、「dancyu」や「日経プラス1」など取材多数。一流プロ愛用の海外食品を1パックからお届けする通販です。商社直営。
-
 クリスマス シュトーレン 500g
クリスマス シュトーレン 500g -
 ベビーターキー 皮なしむね肉 (ターキーブレスト) 700g
ベビーターキー 皮なしむね肉 (ターキーブレスト) 700g -
 【電子レンジ対応】 エスカルゴ XLサイズ 12個入(殻付き/ガーリックバター入り)
【電子レンジ対応】 エスカルゴ XLサイズ 12個入(殻付き/ガーリックバター入り) -
 パテ ド カンパーニュ ブロック (田舎風豚のパテ) スタンダード
パテ ド カンパーニュ ブロック (田舎風豚のパテ) スタンダード -
 薔薇の花びら茶
薔薇の花びら茶 -
 プレミアム タルト オ ショコラ(直径約21cm 8カット)
プレミアム タルト オ ショコラ(直径約21cm 8カット) -
 鴨のスモーク スライス 60g
鴨のスモーク スライス 60g -
 信州サーモン 冷燻仕立て
信州サーモン 冷燻仕立て -
 ごろっと大粒ほたて(青森産 黄金ほたて)のコキーユ(グラタン) 8個入り
ごろっと大粒ほたて(青森産 黄金ほたて)のコキーユ(グラタン) 8個入り -
 3種のチーズのキッシュ(タルトフロマージュサレ)
3種のチーズのキッシュ(タルトフロマージュサレ) -
 ミニ カヌレ 50個入り
ミニ カヌレ 50個入り -
 箱入り薪窯ピザ 4チーズ 200g
箱入り薪窯ピザ 4チーズ 200g -
 ブレス産 AOP発酵バター 250g
ブレス産 AOP発酵バター 250g -
 【20%OFF!送料無料】みんなが集まる休日わいわいセット
【20%OFF!送料無料】みんなが集まる休日わいわいセット -
 【送料込み】週末ご褒美プチセット
【送料込み】週末ご褒美プチセット
クリスマスモードのチェコ・プラハ|スタッフ海外体験記
ダイニングプラスのすりおろしリンゴはチェコの生果のりんごを使い、洗った丸ごとのりんごを特別な機械で一気にすりおろされる、という魔法のような製法でできます。
赤いりんごと黄色いりんごを「あーでもない」「こーでもない」と配合を繰り返し、絶妙な美味しいサンプルができたので、初回生産の立ち合いに行ったわけです。
>「なめらか食感のすりおろしリンゴ」はこちら
その生産の詳細は別の機会にお伝えするとして、今回は別のお話し。

日本からパリを経由してプラハに到着したのは夜10時近く。
翌日に備えて、プラハから車で1時間半、工場のある村のホテルにチェックインできたのは日付が変わる頃でした。
小さい村で、実は最初に予約したホテルはチェックインが遅くなることを知るや、「うちの門限は9時だからダメです」と断わられました。家族経営なんだそうです。
そこで何件か確認をして、深夜になっても良い、というホテルを見つけたので安心して向かったのですが、まぁ、ホテルの周りは真っ暗、ホテルの中も我々を待ってくれていたレセプションのデスクにわずかに明かりがついているのみ。
町の様子をうかがい知ることもできず謎のまま、部屋は快適でぐっすり寝て、翌朝のこと。
朝食場所に行って気づいたのです。
ホテルは村の中心にある広場に面していて、小さな教会の前にクリスマスツリーがあります。 それを見るや、朝食を早々に切り上げ、メーカー担当者が迎えにくるまでの15分ほど、散歩に出ることにしました。

深緑色のツリーにシルバーのオーナメント、黄金色の電球の小さな輝き。とてもシンプルながら教会を背にしたその姿は凛と立派に見えました。
横の小道を進むと小さな雑貨店のようなカラフルな八百屋さんの店先に小さなモミの木が並び、横には金や銀でコーティングされたデコレーション用の枝や葉がぎっしりと積まれ手に取ってもらえるのを待っています。
この小さな村にもクリスマスは確実に近づいている!短い散歩の中でワクワクするひと時でした。

さて、無事に生産が終了し、その日のうちにプラハまで戻ることにしました。
プラハに着いたのは、これまた夜。
前日とは違い、夜でもたくさんの人でにぎわっているのはさすが、観光都市のプラハ!
ホテルは比較的にぎやかな通りに面していて、その時間はすでに車は立ち入り禁止になっている歩道の両側はきらびやかなショーウィンドーがずらり!
荷ほどきもそこそこに早速部屋を飛び出て散策してみました。
クリスマスプレゼントの候補たちがところ狭しと並び、きょろきょろしながら道なりに進んだところに突如現れた目を見張る光景。
それは広場のクリスマスマルシェでした。

広場の横にある教会の前に置かれた大きなクリスマスツリーは色とりどりの華やかな装飾の間に天使が笛を吹くオーナメントがきらめき、ここがマルシェの中心であることを物語っています。

そこから縦横に広場中に広がる屋台の数々。教会の反対側の時計台の前には白い馬の2頭立ての馬車が待機しています。
黒い衣装に黒いハットをかぶった御者は中世感あふれています。背景にマルシェを従え、教会の2つの塔とその横に光る満月。幻想的な光景。
プラハの夜は長いようです。
生産立ち合いが無事1日で終わってくれたおかげで一日空きました。せっかくなのでプラハ市内のスーパーを数件まわってりんご製品を見て回りました。
すると市内のあちらこちらにクリスマスマルシェがあります。
ちょっとスペースがあると屋台が出店して様々なものを売っています。

オーナメントやマフラー、帽子を売っているお店の他に必ずあるのがホットワインの屋台。お店ごとにスパイスの配合などが違って人気のあるところ、そうでもないところ。。。

食事時間になると流行っているのはホットドッグの屋台。
大きなソーセージをジュウジュウと鉄板で焼いて、半分に割られたパンの真ん中にどーんとソーセージを載せる。カウンターに置かれた波打ったディスプレイはホットドッグを置くためのもののようです。
そのサイズ感は日本ではみかけません。

焼きチーズというのも見つけました。
ハードタイプの大きなチーズを切り分け、ホットプレートに並べてこんがり焼いただけのシンプルなものですが、そこにかけるのはベリーソース。いちごではなく、ブルーベリーやブラックベリー系の濃い紫色のジャムのようです。
なんだか東欧らしい。

豚もも肉の丸焼きもありました。
大きな塊のお肉の真ん中に長い鉄の棒をグサリと刺して火にかざしてぐるぐる回しながら丸焼きにしていくようです。あまりの豪快さとお肉が焼ける美味しそうな匂いについ引き寄せられていきました。チェコビールとよく合うんだろうな。。。

プラハらしさで言うとゴーフルでしょうか。
現地では英語で「スパ・ウェイファー」と呼ばれているようで、お土産用のものはスーパーでも売られているのですが、屋台ではひとあじ違います。薄く焼かれた丸い生地でヘーゼルナッツクリームなどを挟んだシンプルなお菓子ですが、屋台では最後にプレスしてくれるのです。プレスすることで両生地がほんのり温かくパリッと仕上がります。寒い屋外でパリッとほの温かいこの素朴なスイーツは嬉しい。

プラハの名物と言えばもうひとつあります。
それは「トゥルデルニーク」と呼ばれるパンのようなものです。特に観光客が集まるエリアには10メートルおきにこのお店があると思われるほどたくさんあります。
細長く伸ばした小麦粉の生地(おそらくイースト入り)を直径5㎝ほどの鉄の棒に巻きつけ、火であぶってこんがり焼きあげ、シナモンシュガーをたっぷりまぶした菓子パンです。
何度か歩いていくつか食べるとどこが美味しそうか鼻がきいてきます。
やはり直火で焼いた焼き立てが良いよね~、なんて思っていたら、見つけちゃいました。薪で焼いているお店を。。。私が通りかかった時はすでに薪は炭化して灰色の中に赤い火を蓄えた状態で端に寄せられていました。遠火でじっくり焼いていくのでしょう。
当然、食べないという選択肢はありません。
端からちぎって口に入れるとシナモンの香りとグラニュー糖のジャリっとした食感、そして噛み進めると香ばしい外生地と内側のふっくらしたパンの食感がグラニュー糖の甘さと絡んで程よい美味しさを醸し出します。

チェコの最後の食事を広場のクリスマスツリーの前でプラハ名物のトゥルデルニークでしめくくった旅でした。
<ダイニングプラスについて>
2001年事業開始、「dancyu」や「日経プラス1」など取材多数。一流プロ愛用の海外食品を1パックからお届けする通販です。商社直営。
-
 ドイツ職人シリーズ 4種のソーセージ
ドイツ職人シリーズ 4種のソーセージ -
バタープレッツェル 79g×2個入り
-
 ヴァイスヴルスト ドイツ職人の白ソーセージ
ヴァイスヴルスト ドイツ職人の白ソーセージ -
 三角 プレッツェル 85g×2
三角 プレッツェル 85g×2 -
 なめらか食感のすりおろしリンゴ 200g
なめらか食感のすりおろしリンゴ 200g -
 なめらか食感のブルーベリージャム (プレザーブスタイル)
なめらか食感のブルーベリージャム (プレザーブスタイル) -
 ふわもち食感 サンドイッチ チャバタ 130g×1個
ふわもち食感 サンドイッチ チャバタ 130g×1個 -
 ロングブラートヴルスト ドイツ職人のスモーク焼きソーセージ
ロングブラートヴルスト ドイツ職人のスモーク焼きソーセージ -
 スティック プレッツェル 70g×2個入り
スティック プレッツェル 70g×2個入り -
 プレミアム タルト オ ポワール (直径約 21cm 8カット)
プレミアム タルト オ ポワール (直径約 21cm 8カット) -
 エキストラホット グルメソース カレー(カレーケチャップ辛口)
エキストラホット グルメソース カレー(カレーケチャップ辛口) -
 タスマニア産マスタード ホールシードタイプ
タスマニア産マスタード ホールシードタイプ -
 フランス産 マカロン レッドフルーツ アソート 12個 (4種×各3個)
フランス産 マカロン レッドフルーツ アソート 12個 (4種×各3個) -
 【20%OFF!送料無料】みんなが集まる休日わいわいセット
【20%OFF!送料無料】みんなが集まる休日わいわいセット -
 【送料込み】週末ご褒美プチセット
【送料込み】週末ご褒美プチセット
フランスのバターその2|上野万梨子さんのフランスレポート
その他のバター

■ 味付けバター

Bordier のバターに代表される近年の流行。海藻やスパイス、柑橘の果汁、アンチョビ、トリュフなどを加えたもの。調理用からアペロのたのしみまで。
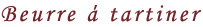
■ タルチネ用バター

パンにぬりやすいように、冷蔵状態でも普通のバターほどは固くならないように作られている。乳脂肪は硬質、軟質、そして液状、以上3種の脂質で成り立っているが、これを特殊な処理で三つに分離し、硬質と液状の脂肪のみを合わせて混ぜると、冷蔵庫に入れても一般のバターのようには固くならないものになるのだそう。マーガリンのようなケースに入って販売されているため、一見植物性オイルなどの混ぜ物があるように思えるが、100%ナチュラルな自然食品。

■ 低脂肪バター

一般のバターの乳脂肪が80~82%であるのに対して、これは41%~62%
脂肪分41%以下のものはバターとはいわない。
パッケージの表示
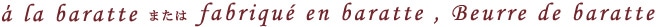


コンピュータ管理された大工場では、生乳を通称カノン(大砲)と呼ばれるラインに注入してからバターが出来上がるまでに1時間たらず。それに対して、昔ながらの製法に則ったチャーン方式の機械で、クレームをバター粒とバターミルクに分離させて造ったものであることを示すための表示。


昔の農家産のように、バターを木型にはめて(ムーレ)仕上げたもの。あるいは、そのようにバターの側面にカヌレ模様を入れて手作り風にデザインされたバター。
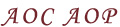

AOC原産地管理呼称統制の起源は15世紀のフランス。その後ヨーロッパ各国がフランスのこの制度を参考に、各国それぞれに基準を定めてきたが、1999年のEU統合を機に欧州各国共通基準の法を制定することとなり、フランスのAOCとは区別させる必要から、AOP原産地名称保護制度 が生まれた。したがってAOCはフランス主体、AOPはEU主体。
■ フランスバターAOPは3地域
西の海側のバター
1)Le Poitou et la Charente ポワトゥー シャラント
2)La Normandie le beurre d’Isigny ノルマンディー イジィニ

東の山側のバター
3)La Bresse (無塩のみ)ブレス
*AOP基準では、その製品に使用される素材のすべては認定地域内で産するものでなくてはならない。ブレスでは海塩も岩塩も採れないため、有塩バターには隣りの県の岩塩を使っている。したがってブレス産バターのAOPは無塩バターに限る。

フランス産のバターを理解するには、パッケージに書かれているこれだけの言葉の意味を知らなくてはならないので一見複雑に思えますが、といって原料や製造方法が特別なものでもなんでもないのがバターです。
原料は牛の乳と、有塩バターの場合は塩。それ以外に添加を認められているのはクレームに風味と個性を与えるフェルマン・ラクチック(乳酸菌)のみ*。
これだけシンプルな食材でありながら、これだけ厳しい品質基準で価値が守られているとは、バターがフランス人にとっていかに重要な食材であるかの証というものでしょう。
(*原料のミルクは、季節による牛の餌の違いで色が変わります。そこでバターの色を年間通じて安定させるために、天然由来のカロチン系着色剤の使用も認められていますが、どのバターにも使われているわけではありません)
COVID-19 によるロックダウンで、平時のようには食材が手に入らなくなった時、「でもパンとバターがちゃんとあるからな」 とは誰もが思ったことだったのではないでしょうか。 最後の晩餐に食べたいものは何?と尋ねられたとき、私は迷うことなく答えたものでした。「美味しいパンとバター」。
<ダイニングプラスについて>
2001年事業開始、「dancyu」や「日経プラス1」など取材多数。一流プロ愛用の海外食品を1パックからお届けする通販です。商社直営。
-
 ブレス産 AOP発酵バター 250g
ブレス産 AOP発酵バター 250g -
 ブレス産 発酵バター ドゥミセル (加塩) 250g
ブレス産 発酵バター ドゥミセル (加塩) 250g -
 とろニシン レモンじめ 2フィレ(100g~160g)
とろニシン レモンじめ 2フィレ(100g~160g) -
 信州サーモン 冷燻仕立て
信州サーモン 冷燻仕立て -
石窯焼き パン ド カンパーニュ (田舎風パン)
-
 ハーフバゲット 140g×2個入り
ハーフバゲット 140g×2個入り -
 【限定入荷】 季節のフリーズドライフルーツミックス from 明日香村
【限定入荷】 季節のフリーズドライフルーツミックス from 明日香村 -
 爽やかオレンジマーマレード
爽やかオレンジマーマレード -
 ベラミーズパイシート フレッシュバター100% 300g
ベラミーズパイシート フレッシュバター100% 300g -
 ラズベリーマスカルポーネデニッシュ 3個入り 焼くだけ
ラズベリーマスカルポーネデニッシュ 3個入り 焼くだけ -
 ミニ メープルピーカン デニッシュ 5個入り 焼くだけ
ミニ メープルピーカン デニッシュ 5個入り 焼くだけ -
 ミニ カヌレ 7個入り
ミニ カヌレ 7個入り -
 りんごとカスタードのタルト 約21cm10カット フランス製 (タルトノルマンディー)
りんごとカスタードのタルト 約21cm10カット フランス製 (タルトノルマンディー) -
 【送料込み】欧州パンとこだわりのバターを愉しむ欲張りセット
【送料込み】欧州パンとこだわりのバターを愉しむ欲張りセット -
 【サンプル セット】12種類のデニッシュ&パイお味見用セット
【サンプル セット】12種類のデニッシュ&パイお味見用セット
フランスのバターその1|上野万梨子さんのフランスレポート
四人家族なら単純計算でひと月2.6キロにもなるのですから、そう考えると驚きです。
しかし家で消費するばかりでなく、外食の料理やお菓子、加工品に使われるものも含めてと考えれば理解できる数字ではあります。日本人のバターの使い道は、まずはパンにつけて、そしてお菓子作りが主ですが、フランスでは料理に欠かせないのがバターなのですから。

フランス風パンとバターの楽しみ方
フランス料理にバターがいかに重要であるかについては、また別の機会にお話しするとして、まずはバターといえばパン、パンといえばバター、そのフランス的食べ方をご紹介しましょう。どれにも共通するのは、柔らかくなったバターをパンに薄く塗るのではなく、バターはパンの上で厚みがなくてはいけないということでしょう。
■ サーディンバター
パンに無塩バターを厚めに塗り、オイルサーディンをのせ、ナイフで潰し、レモンを絞って食べる。
これはアペロの定番ですが、サーディン以外にスモークニシンも好まれます。 またなめらかに練ったバターに、つぶしたサーディンと、玉ねぎとディルを細かく切ったものを加え混ぜたタルチナード(パンに塗って食べるペースト状のもの)も人気です。
■ ロックフォールバター
ミルキーな牛乳製のチーズやハードタイプの山のチーズにバターを合わせて食べることはまずありませんが、ロックフォールチーズと無塩バターは黄金の関係です。ブルーチーズならではの塩気の強さと青カビの風味は、バターのミルキーさと合わせることで美味しさが何倍にも増すものです。好みで胡桃や蜂蜜をトッピングして。
■ ラディッシュバター
スライスしたバゲットにバターをぬり、薄切りににしたラディッシュと塩の華で。
かすかに苦味のあるラディッシュと、ミルキーなバターとの組み合わせは、フランス人が こよなく愛するアペロ向きの一品です。塩の代わりにプロシュート少々をあしらっても。

■ コーヒーシュガーのバタータルチーヌ
これは私流のバタータルチーヌの食べ方で、お勧めすればどなたにも大好評。細めのバゲットの切り口に、冷たさが残る有塩バターを厚めに塗り、香り高いエスプレッソを染み込ませた角砂糖をバターの上でつぶしながらのばして食べる、というもの。
■ 苺のタルチーヌ
無塩バターをパンに厚めに塗って、半分にカットした苺をおき、砂糖をふりかけたら2~3分おき、 少し染み出した果汁と砂糖で上面にツヤが出たところをいただきます。
バタークリームと苺のお菓子、フレジエールを好きな人は多いと思いますが、 こんなに簡単にその魅力を十分に楽しめると、どなたにも喜ばれるタルチーヌです。
 (パり左岸のLa Grande Epicerie de Parisのバター売り場)
(パり左岸のLa Grande Epicerie de Parisのバター売り場)フランスに旅したらお土産にはバターを。そう考える方は多いのではないでしょうか。
そこで種類が多そうな高級スーパーマーケットに行ってみると、想像していたよりもはるかにバターの種類が多いことに驚き、そしてパッケージに書かれた情報を読み取りきれずに悩むのではないでしょうか。そんな時のために、以下にバター豆知識をまとめてみました。
生バターと殺菌バター

■ 生バター

搾乳後常に4度に保った牛乳から分離させたクレームを、殺菌によって加熱せずに、搾乳後72時間以内に作られたバター。非加熱のため、ミルクの風味豊かなバターになる。またクレームの発酵をどこで止めるかで、作り手による風味の違いが生じる点で、コンピューター管理され安定した工場生産バターにはない個性が生まれるとされる。殺菌していないので賞味期限は製造後2~3週間と短い。長期保存を目的としないため、多くの場合乳白の紙による簡易な包装である。
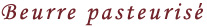
■ 殺菌バター
殺菌されたクレームを使用して作られたバター。パスツールによる1862年の実験で低温殺菌法が発見されたことから “パストゥリゼ “といわれる。生バターと明確に分けるため、パッケージには Beurre pasteurise と書かれる場合もある。


搾乳後72時間以内、かつ生乳からクレームを分離させ、発酵過程に入ってから48時間以内に仕上げられたバター。 賞味期限は平均3~4ヶ月。

使用するクレームの30%までの範囲内で、冷凍あるいは冷蔵保存クレームを使うことができる。賞味期限は平均3ヶ月から4ヶ月。
但し、すべてのバターに表示されているものではない。
無塩バター、薄塩バター、塩バター


■ 無塩バター 脂肪分82%

■ 薄塩バター 脂肪分80%
日本の有塩バター程度の塩気、100gのバターに対して塩 0.8g~3g

■ 塩バター 脂肪分80%
日本の有塩バターより塩気はかなり強い、100gのバターに対して3g以上の塩。
ゲランドの粗塩やクリスタルソルト(岩塩)などを使用。
パッケージには、このどちらかの塩であることが表示されている場合が多い。
なお海の自然塩は旨味の元である不純物も含むので、バターの日持ちはやや悪くなる。
それに対してクリスタルソルトは不純物がほとんど無いため日持ちは良い。
<ダイニングプラスについて>
2001年事業開始、「dancyu」や「日経プラス1」など取材多数。一流プロ愛用の海外食品を1パックからお届けする通販です。商社直営。
-
 ブレス産 AOP発酵バター 250g
ブレス産 AOP発酵バター 250g -
 ブレス産 発酵バター ドゥミセル (加塩) 250g
ブレス産 発酵バター ドゥミセル (加塩) 250g -
 信州サーモン 冷燻仕立て
信州サーモン 冷燻仕立て -
 スモーク オイルサーディン ラトビア産
スモーク オイルサーディン ラトビア産 -
石窯焼き風 ライ麦パン(パン・オ・セーグル)
-
 ハーフバゲット 140g×2個入り
ハーフバゲット 140g×2個入り -
 2種チーズのバスクチーズケーキ
2種チーズのバスクチーズケーキ -
 【電子レンジ対応】 エスカルゴ XLサイズ 12個入(殻付き/ガーリックバター入り)
【電子レンジ対応】 エスカルゴ XLサイズ 12個入(殻付き/ガーリックバター入り) -
 3種のチーズのキッシュ(タルトフロマージュサレ)
3種のチーズのキッシュ(タルトフロマージュサレ) -
 贅沢いちごジャム (プレザーブスタイル)
贅沢いちごジャム (プレザーブスタイル) -
地中海クリスタル フレークソルト ナチュラル
-
 フランス伝統生ハム IGP ジャンボン ド バイヨンヌ 200g
フランス伝統生ハム IGP ジャンボン ド バイヨンヌ 200g -
 【送料込み】欧州パンとこだわりのバターを愉しむ欲張りセット
【送料込み】欧州パンとこだわりのバターを愉しむ欲張りセット -
 【サンプル セット】7種類のお食事パンお味見用セット
【サンプル セット】7種類のお食事パンお味見用セット -
 【送料無料】ベルデンソ 無ろ過EXVオリーブオイル 3本セット
【送料無料】ベルデンソ 無ろ過EXVオリーブオイル 3本セット
パリ発『教えて!万梨子先生』|バター保存術
料理や食材についての疑問にパリ在住のフランス料理家、上野万梨子さんに教えていただく、というコーナーです。
【 第1回 バター保存術 】

Q:ダイニングプラスからの質問
買ってきたバターを使い始めたら、どのように保存したら良いのでしょうか?
またフランスならではのバター保存豆知識などもあれば、教えてください!
A:上野さんのお答え
◆ 未開封で冷凍保存する場合

ダイニングプラスのバターは冷凍した状態で皆さまの元に届きますが、家庭の冷凍庫でそのまま保存する場合は二枚重ねのペーパータオルで包んで、冷凍用の保存袋に入れた上で、冷凍保存するのがよいでしょう。
また、フランスに旅をしたら、バターを買って帰りたくなりますよね。
多めに購入した場合は同じようにして冷凍庫に入れておけば、2ヶ月くらいは問題ありません。
(冷凍庫の開閉の多さなどによって変わるので、あくまで目安としてお考えください。)
※ご注意: ダイニングプラスで販売しているブレスのバターの冷凍賞味期限はパッケージに記載のものをご参照ください。
◆ 開封後に冷蔵保存する場合

切ってから冷蔵庫に入れておくと便利ですね。
この場合用途によって切り方を変えるのがオススメです。
例えば毎朝のパンに使いやすいように、8ミリくらいの厚さに切ってから冷蔵保存。そのときは硫酸紙(クッキングシート)などをバターの切り口に当てて、容器に入れて保存できれば、一切れを取り出しやすく、なおよいでしょう。紙ではなくラップを当てることもできますが、この場合はクシャクシャになって使いにくさはあるものです。
クッキングシートがない場合は、バターを包んでいた紙を利用するのも一法です。

また、私は料理教室や撮影などで、調理用のバターの使用量が多いときは、1センチ角くらいのキューブにし、容器に入れています。ブレスバターの場合1センチ5ミリ弱の厚さに切って6等分の角切りにすると、キューブ1個が5グラムになります。
この状態で何週間も冷蔵保存するわけではないので、容器に蓋をするだけで保存性に全く問題ないと思います。
フランスでは・・・
フランスの地方の家庭では、冷蔵庫が普及していなかった時代の名残がまだあるようで、食材を冷蔵庫に入れずにガルドマンジェ*や温度が安定した納屋や地下に保存している例はよくあります。バターも真夏以外は台所の常温に置いていることが少なくないでしょう。程よい硬さで使いやすいのですが、バターの使用頻度が高いので、常温のまま1週間も2週間も出しっ放しということがないから可能なのでしょうね。また食卓にバターを出す場合、テラコッタのバターケースや壺に水を染み込ませて冷蔵庫で冷やしておき、そこにバターを入れてテーブルに出すことがあります。(*乾物や、小麦粉、砂糖といった食材ではなく、チーズや野菜などの生鮮食材をしまっておく、扉付き、空気穴付きのスペースのことです。)
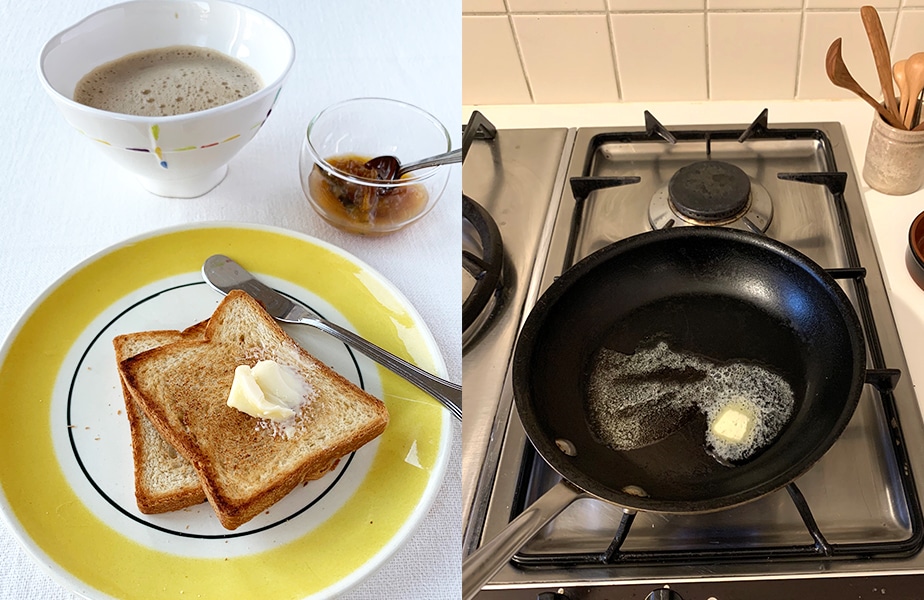
皆さんも万梨子先生に聞いてみたい!というご質問があれば、次のリンクからお寄せくださいませ。
>> お問い合わせフォームへ
万梨子先生のバターを使ったレシピ公開中

>> 焦がしバターが決めてトマトとシャンピニオンのごちそうタルティーヌ(レシピはこちら)

>> 海藻バターとスモークサーモン(レシピはこちら)

>> チーズのように楽しむモンディアン風(レシピはこちら)
<ダイニングプラスについて>
2001年事業開始、「dancyu」や「日経プラス1」など取材多数。一流プロ愛用の海外食品を1パックからお届けする通販です。商社直営。
-
 ブレス産 AOP発酵バター 250g
ブレス産 AOP発酵バター 250g -
 ブレス産 発酵バター ドゥミセル (加塩) 250g
ブレス産 発酵バター ドゥミセル (加塩) 250g -
 信州サーモン 冷燻仕立て
信州サーモン 冷燻仕立て -
 訳あり バゲット ルヴィノワーズ
訳あり バゲット ルヴィノワーズ -
 ベビーターキー 皮なしむね肉 (ターキーブレスト) 500g
ベビーターキー 皮なしむね肉 (ターキーブレスト) 500g -
 【電子レンジ対応】 エスカルゴ XLサイズ 12個入(殻付き/ガーリックバター入り)
【電子レンジ対応】 エスカルゴ XLサイズ 12個入(殻付き/ガーリックバター入り) -
 3種のチーズのキッシュ(タルトフロマージュサレ)
3種のチーズのキッシュ(タルトフロマージュサレ) -
 焼くだけ!大きなクロワッサン 発酵バターが香るフランス産 Bake up生地 60g×4個入り
焼くだけ!大きなクロワッサン 発酵バターが香るフランス産 Bake up生地 60g×4個入り -
アップルパイ 100g×2個
-
 ミニ カヌレ 7個入り
ミニ カヌレ 7個入り -
 フランス産 マカロン レッドフルーツ アソート 12個 (4種×各3個)
フランス産 マカロン レッドフルーツ アソート 12個 (4種×各3個) -
石窯焼き パン オ セーグル (ライ麦パン)
-
 ポテトニョッキ 1kg
ポテトニョッキ 1kg -
 【送料込み】欧州パンとこだわりのバターを愉しむ欲張りセット
【送料込み】欧州パンとこだわりのバターを愉しむ欲張りセット -
 【送料込み】ヨーロッパ ちょい呑みセット
【送料込み】ヨーロッパ ちょい呑みセット
ラトビアのオイルサーディン工場に行ってきました!

ソ連の解体という衝撃が世界を駆け巡ったころ、学生だった私は地理が好きだったこともあって、バルト3国を地図で確認しながら遠い異国に思いを馳せ、ロマンチックな気持ちになったことを覚えています。
ラトビアとの出会いはヨーロッパで開かれたシーフードショーという展示会。 燻製のオイルサーディンに出会ったのです。
柔らかい身質に燻製の香り。新しい美味しさに出会ってこれは是非輸入しなければ、という強い思いに駆られました。
その年の9月、ラトビアの首都リガへ。
それは早朝のことでした。
まだ暗い9月の朝5時にホテルのロビーで待ち合わせをしました。
なぜ、そんなに早朝なのか?
毎年9月から始まるバルト海のスプラット(小イワシの1種)漁は深夜から始まり、陸揚げされて工場に運び込まれるのは早朝だからです。

リガの中心部にあるホテルから車で30分ほど、リガの港エリアにその工場はあります。
スプラット(小イワシ)の加工では世界でもトップクラスのそのメーカーでは獲れたての新鮮なスプラットを使うのですが、まずはロットごとにサンプルを抜き取ってラボに運び、魚の品質を確認します。
品質管理部からお墨付きの出た魚は工場内に運び込まれ、待ち構えていた女性スタッフが一斉に串刺しにしていきます。ざっとみて約30人。黙々と魚を手に取ってきれいに串に刺していきます。

ラトビアのオイルサーディンは生魚をオイル漬けにする一般的なオイルサーディンではなく、一度燻製にして臭みを落としてからオイル漬けにするのが特徴です。
鮮度を保つためには、この工程の手早さがとても大切。
整然と串刺しにされた小イワシはラックに並べられて長いトンネル状の燻製機に入れられます。
ここがポイント!

この燻製トンネルの工程はクーリングという冷却工程を含めて約85分あり、じっくり時間をかけて燻製するのですが、使用するウッドチップが大切です。
このメーカーでは丸太状の木を買って、工場内の設備でその日に使う分だけをウッドチップに加工します。
だから!香りが違う!
ブナの木を使うのですが、あまりの良いチップの香りを会社の仲間にも見せたくて、持って帰ったのですが、数日後に日本に帰った時にはあの香りは消え、ただの木クズになっていたのでした。。。(涙)
それぐらい、木の香りは飛びやすい!
それを知っているからこそ、ウッドチップで妥協をしないのがこのメーカーのこだわりです。
さて、工程に戻ります。
銀色のピチピチの状態で燻製トンネルに入った小イワシは出てきた時にはキラキラと金色に光り輝いて、それは美しい光景です。(加えて良い香り~)

小イワシが完全に冷めると、思い切って頭を切り落とし、また丁寧に手作業で缶に入れていきます。小イワシたちは言わば、無選別なので、大きさはマチマチです。それを瞬時に見極めて、大小組み合わせて所定の重さになるように缶に詰めていく様子は熟練の技。
その後、塩とオイルを充填して蓋をし、レトルト加工をしていきます。

このメーカーの製品はRiga Goldという名前で地元では有名です。
「リガの黄金」という名に恥じないような燻製のきれいな色合いと香ばしい香り。
だから私たちも名づけました『黄金燻製』
工場を訪問した後は会議室で味わいの確認です。
実はシーフードショーと町のスーパーで買った何社かのサンプルを持ち帰り、味の確認をして一番美味しかったこのメーカーに決めたのですが、現地の伝統の味のままでは、日本の食卓でいただくには少しクセがありました。
このメーカーの美味しさの秘密は新鮮な原料と作りたてのウッドチップにあることが工場訪問でわかりました。
ここからが味の調整をするための大切な会議です。

微妙な燻製の加減と塩味の加減。
ラトビアを含めた北欧地域は強い燻製をして保存食とする文化があります。
その現地の伝統の味は美味しいのですが、「お酒のおつまみ」というイメージがどうしても強くなります。
そこで、日本のオイルサーディンも持ち込んでメーカーの担当者と工場長と一緒に試食をし、日本人の好む味わい加減を理解してもらった上で、塩加減、スモーク加減を少しずつ変えて、いくつかサンプルを作ってもらい、絶妙なバランスの現在の商品が出来上がったのです。

燻製の香りと程よい塩加減。
だからお醤油をタラッと数滴垂らした時の味の広がりが楽しめる!
もちろんパスタやサラダなどの洋風アレンジもできる!
この数年後に登場したオーブンドライタイプの旬仕込は、燻製トンネルをオーブンに変えて、スモークを入れずにじっくり加熱をしながら臭みだけを落とした一夜干しに近い製法で作られています。
だから!
魚の臭みが取れて、旨みが凝縮した美味しさ!
スモークが苦手な方のために作ったこちらも優しい味わいの自信作です!

<ダイニングプラスについて>
2001年創業、ミシュラン星付きレストランや有名高級ホテル愛用の上質な食材を1パックからお届けする食品通販です。商社直営。
-
 スモーク オイルサーディン ラトビア産
スモーク オイルサーディン ラトビア産 -
 ハーフバゲット 140g×2個入り
ハーフバゲット 140g×2個入り -
石窯焼き風 ライ麦パン(パン・オ・セーグル)
-
 レモン香るエキストラバージンオリーブオイル
レモン香るエキストラバージンオリーブオイル -
 ブレス産 AOP発酵バター 250g
ブレス産 AOP発酵バター 250g -
 2種チーズのバスクチーズケーキ
2種チーズのバスクチーズケーキ -
 【電子レンジ対応】 エスカルゴ XLサイズ 12個入(殻付き/ガーリックバター入り)
【電子レンジ対応】 エスカルゴ XLサイズ 12個入(殻付き/ガーリックバター入り) -
 肉厚の旨味 大粒ほたて貝(青森産 黄金ほたて) Lサイズ
肉厚の旨味 大粒ほたて貝(青森産 黄金ほたて) Lサイズ -
 ごろっと大粒ほたて(青森産 黄金ほたて)のコキーユ(グラタン) 8個入り
ごろっと大粒ほたて(青森産 黄金ほたて)のコキーユ(グラタン) 8個入り -
 3種のチーズのキッシュ(タルトフロマージュサレ)
3種のチーズのキッシュ(タルトフロマージュサレ) -
 ふわもち食感 サンドイッチ チャバタ 130g×1個
ふわもち食感 サンドイッチ チャバタ 130g×1個 -
 三角 プレッツェル 85g×2
三角 プレッツェル 85g×2 -
 ダッテリーノトマトのトマトジュースづけ (皮なし)400g
ダッテリーノトマトのトマトジュースづけ (皮なし)400g -
 【送料込み】欧州パンとこだわりのバターを愉しむ欲張りセット
【送料込み】欧州パンとこだわりのバターを愉しむ欲張りセット -
 【送料込み】週末ご褒美プチセット
【送料込み】週末ご褒美プチセット
ダイニングプラスの無ろ過エキストラバージンオリーブオイルをお勧めする5つの理由
お店に行くと高いものから安いものまでいろいろありますよね。。。
高い方が体にいいのでは?と思って高いものを買ってみたけれど、味にクセがあって続けられない。
安いとニセモノじゃないの?といろいろ考えた結果、真ん中ぐらいの値段のものを買ってみたものの、良いのか悪いのかよくわからず、次もまた同じように迷ってしまう。。。
そんな方にこそ、おすすめしたいのがダイニングプラスの無ろ過エキストラバージンオリーブオイルなのです。
その理由をいくつかのポイントに分けてご説明したいと思います。

1.【エキストラバージンオリーブオイルだから】
これって、今や当たり前ですよね?でも実は日本の基準(日本農林規格/JAS規格)では「オリーブ油」と「精製オリーブ油」の2種しか規定がありません。その「オリーブ油」であるための規定はいくつかありますが、一番有名な酸価を例にすると「2.0以下」という規定です。
いわゆるエキストラバージンオリーブオイルの酸価は「0.8以下」と決められているため、極端な例を出すと酸価が0.8を超えた「バージンオリーブオイル」のグレード(エキストラではない!)でも同じ「オリーブ油」として括られてしまいます。それぐらいオリーブオイルについての日本の基準はおおざっぱなのです。
とはいえ、オリーブオイルがあふれ、国内でもオリーブ生産農家さんが頑張っている日本のこと、日本独自の協会もできて、良いオリーブオイルとは何か、という啓蒙活動が熱心に行なわれるようになっており、私もそんな協会のひとつで勉強をしている一人です。
現在、日本の市場で紹介されているほとんどのオリーブオイルはIOCの基準を元にした製品がほとんどです。
IOCとはヨーロッパ諸国を中心に世界のオリーブ生産国の多くが加盟するInternational Olive Councilという組織で、このIOCが決めた基準が世界基準として認められています。先ほど「いわゆるエキストラバージンオリーブオイル」と書いたのはこのIOCの基準を元にしたものです。
ただ、最近ではこのIOCに非加盟のアメリカやオーストラリアなどでのオリーブオイル生産が活発になってきて、基準もこれから変わっていく可能性も指摘されていますが、今のところはIOC基準がいちばん一般的なものとなっています。
(ちなみに日本も国産オリーブオイルを作っていますが、IOCには参加していません。)
さて、難しい話はさておき、ダイニングプラスでご紹介する無ろ過オリーブオイルは、そのIOC基準を満たしたエキストラバージンオリーブオイルです。メーカーはイタリアの食用油専門メーカーのオリタリア社で、イタリアで瓶詰されています。
あとで出てきますが、この商品は毎回特注で作ってもらっています。
なので、ラベルは日本語でわかりやすいように書かれていますが、英語でもExtra Virgin Olive Oilと書かれていて、きちんとIOCの基準をクリアしているものです。
輸入のときには毎回ロット毎に化学分析結果が添付されて、エキストラバージンオリーブオイルであることがすぐにわかります。
ここで詳しい方はピンときますね。
IOC規定でエキストラバージンオリーブオイルと呼ばれるためには化学検査だけではダメなのです。
官能検査、つまり鼻や舌、喉を使った味わいの検査も重要な要素です。
オリタリア社には世界最古とも言われるオリーブオイルテイスターの学校、ONAOOの先生が顧問として週に数日勤務していて、官能検査を日々行なって問題がないことを確認しています。
全てのオリーブオイルの中のいちばん美味しいものがエキストラバージンオリーブオイル、つまりピラミッドの頂点です。
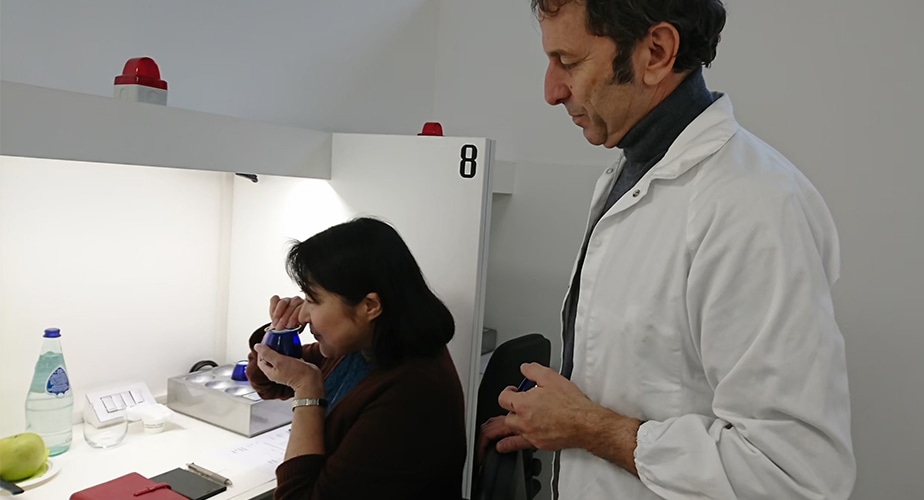
(イタリアに訪問した際の様子)
2.【無ろ過の果汁だから】

オリーブの果実を絞ったジュースがオリーブオイル。
食用油にはたくさん種類がありますが、ほとんどが種に用剤を加えて抽出するものです。
一方、オリーブオイルは果実をつぶして練り込んで絞り出すタイプです。
つまり、オリーブの果汁なのです。
その絞り出す工程を見るとちょっと感動します。実はもっと簡単にオイルが出てくるものかと思ったのですが、実際には大量に投入されるオリーブに対して、出てくるオリーブオイルは「ちょろちょろ」といった感じ。出てくる液体は濁っていて、黄金色の美しい濃厚なオイルです。
いつも数万本単位でオーダーするので、少し麻痺してしまっていたのですが、この絞る現場を見て、自然の恵みをいただいているんだな、とより強く実感しました。

この後、このオリーブオイルは一般的にはフィルターにかけられ、丁寧に澱を取り除いていきます。澱を取り除くことでオリーブオイルが安定して、長期間の保存に適しているからです。
今回ご紹介するオリーブオイルはこのフィルター工程をあえてしていません。つまり、澱をそのまま残している無ろ過タイプです。
なぜ無ろ過なのか。
澱はオリーブの成分で、この澱の中にもオリーブの美味しさが詰まっていて、何よりオリーブオイルが持つポリフェノールがフィルターをかけたものより多く入っているからです。
例えば、オリタリア社で2018年度に生産された同じオリーブオイルの無ろ過タイプとフィルターをかけたタイプで比較してみると、無ろ過タイプの方が28.8%も多くのポリフェノールを含んでいることがわかっています。1㎏あたりのポリフェノール量はフィルタータイプが240.62㎎に対し、無ろ過タイプは310㎎です。
これを聞くとなぜ無ろ過タイプをあまり見かけることがないのかな?と不思議に思われるかもしれません。
その理由は、無ろ過タイプは澱が含まれる分、よりデリケートだからです。
店頭に並んでいるオリーブオイルは毎日お店の蛍光灯に照らされています。夏や冬はお店の営業時間は冷暖房が効き、営業外時間はそれが切れるため、温度が毎日上下します。そんな環境の中でも安定して美味しいオリーブオイルを流通させるため、メーカーではフィルターを通して澱を取り除き、できるだけ光を通さない暗い色の容器、そしてできるだけ温度変化を少なくするために瓶に入れて販売されることがほとんどです。
何度も言いますが、今回ご紹介したいのは無ろ過タイプです。
そして色をより楽しんでいただくために、透明のボトルに入れています。
だから! 通販限定での販売です。
オリーブオイルは一般的には1年を通して常温のコンテナに入れて輸入されますが、ダイニングプラスでは、イタリアの暑い時期(6~9月頃)に出荷される商品は可能な限り温度管理のされたリーファーと呼ばれるコンテナに積んで輸入しております。その分お金はかかりますが、無ろ過タイプを楽しむためには必要なコストです。
ダイニングプラスの無ろ過エキストラバージンオリーブオイルは通販でしかお求めいただくことができません。(TV通販1社とダイニングプラスのみでの販売)
3.【和食にもあうブレンドだから】

オリーブオイルは主な栄養成分は脂質です。脂質は3大栄養素のひとつで、私たちの体に必要な大切な栄養素です。いくらダイエットをしていても脂質を抜くことはできません。毎日摂るのであれば、体に良い脂質、そして美味しく摂ることがとても大切だと思いませんか?
オリーブオイルは地中海式ダイエットという体に良い食事の基本となる食材のひとつです。 でも、体に良いからオリーブオイルを買ってみたけれど、クセが強すぎて好きになれない。というお声もよく耳にします。
そこでおすすめしたいのが、和食にも合うブレンドなのです。
オリーブオイルのブレンドというとあまり耳慣れないかもしれません。 コーヒーやワインを思い浮かべてください。 コーヒーは産地や品種ごとに数種類を組み合わせて自分好みのブレンドを作ったり、お店のオリジナルブレンドっていうのもありますよね。
ワインも畑や品種を組み合わせて味わいを作っていきますよね。それと同じです。
ヨーロッパで代表的なオリーブの栽培国と言えば、スペイン、ギリシャ、イタリアです。中でもイタリアの地形は他の2国と比べて起伏が多く、昔から斜面が変わると品種が変わる、と言われるぐらい、オリーブの品種も多岐にわたります。一般的にイタリアだけで500を超えるオリーブの品種があると言われています。それはつまり、1品種あたりの生産量が少ないことも意味します。今のように交易が盛んではない昔から、イタリアでは近隣のオリーブオイルを集めてブレンドする、ということを当たり前のように行なってきました。
だから、イタリアではオリーブオイルの品種による違いにいち早く気づき、世界初のオリーブオイルテイスター学校がイタリアにできたことに繋がったのでしょう。
話を元に戻して・・・
お勧めする無ろ過エキストラバージンオリーブオイルは「和食に合うブレンド」を目指して、毎年、メーカーと味を決めています。味を作るときにはONAOOの先生も一緒に加わって微妙な加減を決めていきます。
和食に合うブレンド、とは何か?
一般的にヨーロッパの人が好きなオリーブオイルの味は、芝を刈ったようなグリーンな香りと苦み、ピリピリ感の全ての要素を強く持っています。オリーブオイルが好きでいろいろ試したい方にはとっても嬉しいオリーブオイルです。でも、日本人の中にはその鮮烈なオリーブオイルの香りや味わいを苦手に思う方も多いようです。 体に良いからと初めてオリーブオイルを買って苦手、と思った方はそのようなヨーロッパタイプを買われたのではないかと思います。
食文化は国によって違いますから、お肉を中心とした塩味の濃いヨーロッパの食事にはそのような濃い味わいのオリーブオイルが適しています。でも私たち日本人の家庭では洋食、中華などのメニューも取り入れた、独自の和食を楽しみます。ご家庭でもできるだけ素材の味を生かして、味付けは控えめで、という方は多いのではないでしょうか。
そんな私たち日本人の毎日の食生活の中で楽しむためにはヨーロッパタイプより、苦みやピリピリ感が少なくて香りもマイルドな方が良く合うのです。
せっかく摂る栄養なら、体に嬉しいだけはなく、美味しく楽しんで長く続けたい。
だからこそ、「和食に合うブレンド」の無ろ過エキストラバージンオリーブオイルをおすすめしたいのです。
4.【シェフに選ばれてNo.1のオイル専門メーカーが作っているから】
オリーブオイルっていろんなブランドがあってどれを選べばいいのか、迷ってしまいますよね。よく聞くブランドだから、パッケージがきれいだから、など決め手はそれぞれありますし、そんな中で自分に合ったオリーブオイルに巡り合えたら、とってもラッキーですね!でも失敗したくない人はどうすればいいのでしょう?例えば、時計はDCブランドより時計メーカー、という方も多いと思います。
オリーブオイルでも有名なブランドの中には自社設備で生産せず、毎年価格比較をして委託会社を決める、というのは良く耳にします。もちろん品質は確認しているでしょうけれど、その専門家と言う意味ではやはりオイルメーカーがお勧めです。
また、オリーブ農家が独自にボトリングしている商品もあり、日本にもたくさんの種類が輸入されています。最近の農家さんの中にはきちんとした設備を導入して、実を絞るところからボトリングまで一貫してされている素晴らしい方々がたくさんいらっしゃいます。味も素晴らしいものが多いですが、概してお値段が高いことが多いです。
そこで毎日のオリーブオイルとしておすすめしたいのがオリタリア社のオリーブオイルなのです。
オリタリア社は50年以上にわたってオリーブオイルを作ってきた家族経営のオイル専門メーカーです。自社農場は持っていないものの、その購買力を生かして、世界のオリーブ生産地に自社社員や契約社員を配置して、世界のオリーブの生育状況や、絞る設備の状態などの最新情報を把握し、できるだけ新鮮な状態でボトリングして出荷ができるよう、常に品質管理をしています。
そんなオリタリア社が数年前から第3者機関に依頼をして始めたのがイタリアのシェフへのアンケート調査です。「あなたが料理に使っているオイルのブランドは?」という問いにたいして最も多かったのが「オリタリア」だったのです。

プロも認めるブランド、それが「オリタリア」
「品質と価格」この2つの重要なポイントを実直に実現してきたからこその、プロからの信頼。シェフに選ばれてナンバーワンのオリタリアを是非お試しください。
5.【アレンジ自在だから】

和食にも合う、というのをコンセプトにブレンドをしたのがこのノンフィルタータイプですが、この「和食」はいわゆるお豆腐や納豆という伝統食だけでなく、スパゲッティやラーメン、オムレツといった洋食や中華の要素もたくさん取り入れた広義の和食です。
せっかく体に良くても、口に合うものでなければ続きません。
このノンフィルタータイプはそんな広義の和食に合わせてマイルドにブレンドしてありますから、「かける」「いためる」「和える」「揚げる」など私たちの食生活のいろんなシーンでアレンジ自在にたのしんでいただけます。
* お豆腐に塩と一緒にかけて大豆の甘みを引き出す!
* 納豆にかけて納豆嫌いを克服!
* 梅干しにかけて梅がフルーツだったと再認識!?
* お刺身にかけて魚の臭みを取って美味しさアップ!
* 卵かけごはんにかけて卵がグレードアップ!?
* 野菜ジュースにかけてポリフェノールチャージ!
* パンには断然オリーブオイル派!
* 多めのオイルでスクランブルエッグがふっくら!
* とんかつもオリーブオイルでカラッと!
* シフォンケーキに使ってふっくらしっとり!
* サラダには直接かけて和えるだけ、ドレッシング要らず!
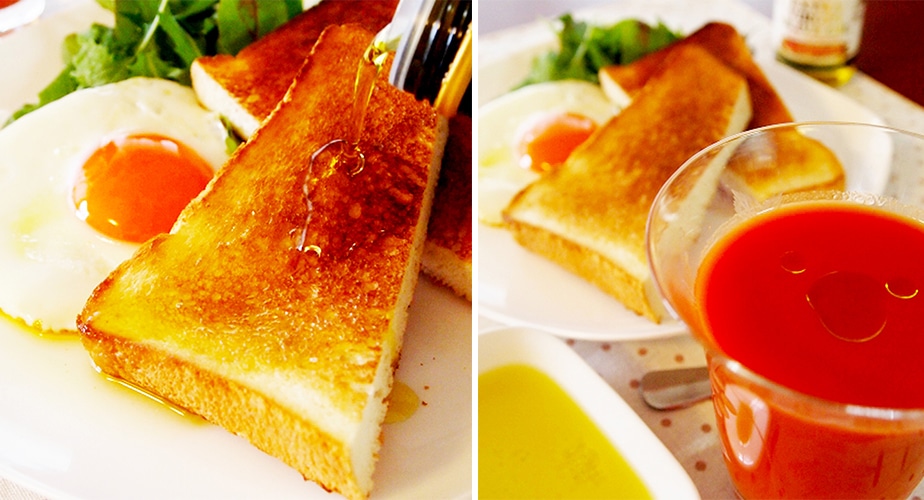

<ダイニングプラスについて>
2001年事業開始、「dancyu」や「日経プラス1」など取材多数。一流プロ愛用の海外食品を1パックからお届けする通販です。商社直営。
-
 【送料無料・ギフト包装】ベルデンソ 無ろ過 EXVオリーブオイル&ジャムギフト
【送料無料・ギフト包装】ベルデンソ 無ろ過 EXVオリーブオイル&ジャムギフト -
 【送料無料】ベルデンソ 無ろ過EXVオリーブオイル 3本セット
【送料無料】ベルデンソ 無ろ過EXVオリーブオイル 3本セット -
 ベルデンソ 無ろ過 エキストラバージン オリーブオイル 500ml オリタリア
ベルデンソ 無ろ過 エキストラバージン オリーブオイル 500ml オリタリア -
 モデナ産 バルサミコ酢 IGP 5グレープ 250ml (オリタリアブランド)
モデナ産 バルサミコ酢 IGP 5グレープ 250ml (オリタリアブランド) -
 2種チーズのバスクチーズケーキ
2種チーズのバスクチーズケーキ -
 2kg テルエルポーク 肩ロース ブロック
2kg テルエルポーク 肩ロース ブロック -
 ベビーターキー 皮なしむね肉 (ターキーブレスト) 600g
ベビーターキー 皮なしむね肉 (ターキーブレスト) 600g -
 信州サーモン 冷燻仕立て
信州サーモン 冷燻仕立て -
 肉厚の旨味 大粒ほたて貝(青森産 黄金ほたて) Lサイズ (1㎏)
肉厚の旨味 大粒ほたて貝(青森産 黄金ほたて) Lサイズ (1㎏) -
 ミニ シリアルロール 44g×5個
ミニ シリアルロール 44g×5個 -
 りんごとカスタードのタルト 約21cm10カット フランス製 (タルトノルマンディー)
りんごとカスタードのタルト 約21cm10カット フランス製 (タルトノルマンディー) -
石窯焼き パン オ セーグル (ライ麦パン)
-
 贅沢いちごジャム (プレザーブスタイル)
贅沢いちごジャム (プレザーブスタイル) -
 ブレス産 発酵バター ドゥミセル (加塩) 250g
ブレス産 発酵バター ドゥミセル (加塩) 250g -
 【送料込み】欧州パンとこだわりのバターを愉しむ欲張りセット
【送料込み】欧州パンとこだわりのバターを愉しむ欲張りセット
カラブリアの甘い朝食|スタッフ海外体験記
今回はそんなとびきり甘い朝食のお話しです。
「カラブリア」ってどこかわかりますか?
イタリアの州のひとつで、イタリアの地図をブーツに例えると爪先の部分がカラブリア州です。その向こうはシチリア島で、爪先からはシチリアのメッシーナを結ぶ連絡船が出ています。
>>特別な日にふさわしい輸入食品セール「クリスマス 2020」はこちら
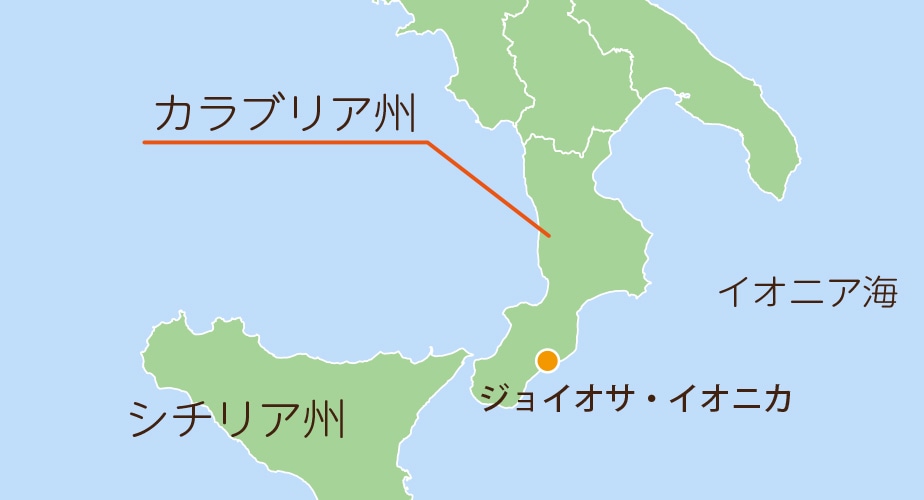
縁があって、何度か訪問しているのですが、中でも良く行くのがジョイオサ・イオニカというイオニア海に面した町、地図の爪先で言うと足指の付け根あたりでしょうか。南部の海辺の田舎町で、繁華街と言えば全長300メートルほどの商店がぽつりぽつりとある通り。
現地のメーカーの人と「ジョイオサ銀座」と呼んでおります。通り沿いの中心となる交差点には教会があり、そのお店は教会の隣にあります。
人気のお店らしく、銀座がにぎわいを見せる夜に遠りかかるとひときわ明るく、人々の楽しそうな声があふれているのがそのお店です。
夜にはあれだけのにぎわいを見せるお店ながら、実は早朝からあいていて、朝は朝で仕事前にコーヒーを飲む近所の人たちがたくさん集まってきます。

お店に着くとまず何よりもクロワッサンコーナーに行くのです。
イタリアのクロワッサンですから、中にクリームの入った甘いものが主流です。
>>バター100% 冷凍クロワッサンもお買得!輸入食品セール「クリスマス 2020」はこちら

お目当てはピスタチオのクロワッサンです。日本ではまだ珍しくて、あったとしてもとても高価でリッチなピスタチオクリームがたっぷり入っているのです!
現地でも人気があって、一番最初に売り切れるので、まずはそれを確保に行くのです。
続いて向かうのはスイーツカウンター。


4mくらいの大きめのウィンドーの中にはぎっしりとスイーツが並んでいます。ひとつひとつは小さめで、ナポリ名物スフォリアテッラやパスティエーラ、シチリア名物カンノーリもあります。どれもとっても甘そう!
私はあまり甘いものは得意ではないので、躊躇していると、メーカーの担当者はスイーツ大好きで、おすすめを次から次へと熱心に説明してくれるので、初回は仕方なくおすすめを注文したことを覚えています。
さて、席に着くとまずは飲み物が運ばれてきます。この日はオレンジマーマレードを作りに行ったので、現地のオレンジジュースも注文しました。

カラブリアでオレンジと言えば、ネーブル種かタロッコ種。タロッコ種はブラッドオレンジの品種ですが、果肉の色はオレンジよりから赤っぽいものまでひとつひとつ異なります。出てきたオレンジジュースの色のバリエーション、どれも同じものがなくて、まさに絞たて!
甘いもの好きの現地の人たちの中には絞たてオレンジジュースにお砂糖を加えて飲む人が多いらしく、1杯あたりしっかり2パックのグラニュー糖がついてきました。 新鮮なオレンジの香りと自然な甘みがあって、口中に広がるオレンジの果汁はほんのりとした苦みがタロッコらしさを出しています。
しっかりビタミンチャージをして、甘いスイーツに向きあいます。
まずはピスタチオクロワッサン。

バター生地のクロワッサンですが、ここはあえてのバター控えめな感じです。ダイニングプラスのクロワッサンはフランス系なので、バターのジュワっとした感じも楽しめるリッチなバタークロワッサンですが、濃厚なピスタチオクリームと合わせる甘いクロワッサンは生地のバター感は比較的少なめです。そこに濃厚なピスタチオクリームが、噛むとはみ出る程にたっぷり入っています!
この段階ですでに満足度マックス。。。と思いつつ・・・
目の前にはまだまだ甘~いかわいいものが並んでいます。
全てを1個まるごと食べてしまうと、きっと後悔することになるだろう、と思い、1個を二人でシェアします。
とは言え、3種あるのです。

カンノーリ(写真上/左のスイーツ)
カンノーリは普通はくるっと筒状に成形して揚げるところ、上を開けたU字状に成形してあります。これは上にたっぷりのピスタチオをまぶすために違いない!と思いつつ、確認はしなかったのですが、ラードで揚げた香ばしい皮は香りだけ残し、油のギトギト感は一切残っていません。中にたっぷり入ったクリームはリコッタチーズを使って重さが全くない!甘ったるくなく、ピスタチオの食感と共にすんなりお腹に収まりました。
ピスタチオクリームたっぷりのチョコタルト(写真上/右のスイーツ)
メーカー担当者の超オススメなので、毎回必ず食べる(食べさせられる・・・)ものなのですが、見た目に比べて以外とあっさり、後口が甘すぎないミニタルトです。
キラキラのチョココーティングの中にはピスタチオクリームがいっぱいで、このクリームが意外と軽いのです。きっと無糖のホイップクリームと混ぜてあるのかな。。。下はチョコのタルト生地とチョコクリーム。
カッサータ風のお菓子(写真上/上のスイーツ)
これもシチリア風ですね。
Cassatella di Sant’Agata(カッサテーラ・ディ・サンタガタ)のアレンジ版のようです。シチリアでは聖アガタのお祭りを2月にするらしく、行ったのがちょうどその頃だったからでしょう。スポンジ生地で(たぶん)リコッタクリームを挟み、上側の生地はマジパンでくるんで上にチェリーの砂糖漬けを載せています。このクリームが軽いからか、見た目ほどに甘くなく、日本人が苦手なマジパンのくどさもなく、とっても美味しいです!
少なくとも1か月分ぐらいのスイーツを堪能した朝に大満足で、この後は幸せな気持ちで工場、農場を回った一日になりました。
<ダイニングプラスについて>
2001年事業開始、「dancyu」や「日経プラス1」など取材多数。一流プロ愛用の海外食品を1パックからお届けする通販です。商社直営。
-
 焼くだけ!ミニクロワッサン 発酵バターが香るフランス産 bake up生地 25g x8個入り
焼くだけ!ミニクロワッサン 発酵バターが香るフランス産 bake up生地 25g x8個入り -
 焼くだけ!クロワッサン 発酵バターが香るフランス産 Bake up生地 40g×5個入り
焼くだけ!クロワッサン 発酵バターが香るフランス産 Bake up生地 40g×5個入り -
 焼くだけ!大きなクロワッサン 発酵バターが香るフランス産 Bake up生地 60g×4個入り
焼くだけ!大きなクロワッサン 発酵バターが香るフランス産 Bake up生地 60g×4個入り -
 ベラミーズパイシート フレッシュバター100% 300g
ベラミーズパイシート フレッシュバター100% 300g -
 爽やかオレンジマーマレード
爽やかオレンジマーマレード -
 2種チーズのバスクチーズケーキ
2種チーズのバスクチーズケーキ -
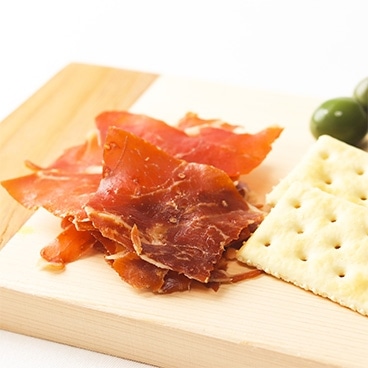 新食感!旨み凝縮生ハムジャーキー 30g
新食感!旨み凝縮生ハムジャーキー 30g -
 信州サーモン 冷燻仕立て
信州サーモン 冷燻仕立て -
 3種のチーズのキッシュ(タルトフロマージュサレ)
3種のチーズのキッシュ(タルトフロマージュサレ) -
アップルパイ 100g×2個
-
 りんごとカスタードのタルト 約21cm10カット フランス製 (タルトノルマンディー)
りんごとカスタードのタルト 約21cm10カット フランス製 (タルトノルマンディー) -
 薪窯ナポリ風ピザ マルゲリータ 200g
薪窯ナポリ風ピザ マルゲリータ 200g -
 モデナ産 バルサミコ酢 IGP 5グレープ 250ml (オリタリアブランド)
モデナ産 バルサミコ酢 IGP 5グレープ 250ml (オリタリアブランド) -
 【送料込み】欧州パンとこだわりのバターを愉しむ欲張りセット
【送料込み】欧州パンとこだわりのバターを愉しむ欲張りセット -
 【まるで高級ホテル】な早起きが楽しみになる朝食セット
【まるで高級ホテル】な早起きが楽しみになる朝食セット
Withコロナのパリ生活|上野万梨子さんのフランスレポート
段階を踏むタイミングに長けるということなのか、それに先立つ3月12日、週末に入る直前の木曜日夜にはマクロン大統領がテレビ演説で準備に入るよう国民に呼びかけ、その翌日以降の朝市やスーパーマーケットは買いだめ目的の人出で賑わいました。日頃はあからさまに慌てて行動するのはみっともないことと思っているフシがあるパリジャンが、前代未聞のロックダウンを前にさすがに準備に入るのは早かったようです。
都市封鎖前夜の、このたった数日間で、すでに人々は社会的距離をおいて店頭に並び、ファーマシーでは消毒ジェルやマスクが品薄になる事態になりました。

(上:人々が店頭に並ぶ様子)
3月7日、私が一時帰国からパリに戻ったときには、空港でマスクをかけて歩こうものなら、病気持ちの怪しい東洋人と間違えられるのではないかと本気で心配したものです。
出迎えの車のドライバーに、パリでコロナはどんな状況かと尋ねたら、昨日メトロの6号線に乗った人の感染が確認されましてね、、、というレベルだったものが、たった数日でこの事態になったのでした。
このいわば準備期間中に人々が買いだめしたものは、日本と同様にトイレットペーパーやペーパータオルといった紙製品。そして食品ではまず最初にパスタが売れ出し、そしてポテトチップスの棚もスカスカになったものです。ただ棚に補充されるのは早く、在庫は十分とわかると売り場はやがて元の状態に戻っていきました。
その頃市民に配られたイラスト入りチラシには、「手をマメに洗いましょう」 「咳をするときには腕で口をふさぎましょう」 そしてこれは日本人には驚きですが 「ティッシュを使ったら一度で捨てましょう」 「体に触れる握手やビズは避けましょう」 。それが2週後にはマスクが奨励されることになったのですから、これには驚いたものです。
「カフェやレストラン、劇場や映画館は国の生命にとって不可欠ではない」として直ちに営業を禁止されましたが、花屋も当然不要不急の職種として営業禁止に。ロックダウン前に鉢植えを買っておくべきだったと思った人は多かったことでしょう。
いざ花が買えなくなるとさみしいもので、外に出ると街路樹の足元の雑草の花が目につくようになり、コロナ前とは違う視点で外を歩く自分に気づいたものです。

(左:立ち入り禁止テープの張られたエッフェル塔の公園/右:街路樹の足元に咲いていた雑草の花)
閉店している花屋の店内をガラス越しに覗くのは女性ばかりでなく男性も。花のある暮らしを愛する人たちが多いことがうかがわれたものです。
そんな中でも朝市がオープンしていたのは喜びでした。社会的距離が守られているかポリスがまめに巡回しながらの営業でしたが、それも翌週末までで、ロックダウン後早々、10日ほどで朝市も閉鎖となったのでした。カフェ、レストランばかりか日常生活に不可欠なマルシェが消えて、パリの行動規制はますます厳格化。私の家から近い二ケ所のマルシェで週4回買い出しが可能だった暮らしがどれだけ豊かなことだったかを思い知ることになったのでした。
ロックダウン中、運動や買い物のために行動できるのは家から1キロ、1時間以内。外出理由申告書を持って家を出ます。街のあちこちでポリスの検問もありますから、マップに自宅からの距離がわかるメモリをつけたカード(写真下)を挟んで行動したものです。

その後、更に厳しい制限が設けられ、国民の我慢もこれ以上はとなった頃、政府は段階的、効果的規制緩和に着手。
いよいよ5月11日以降、待ち望んだマルシェは再開されたのでした。スタンドでは透明シートで商品と客を隔て、売り子は皆マスク着用(写真下)。

社会的距離はほぼ守られ、ほとんどの人がマスクをつけて並びます。買い物の行列はパリの風物詩のようなものですが、しかしその有り様はコロナ前とはすっかり変わりました。詰めて並べないので遠くからでは商品がよく見えず、待ちながら品定めすることが難しくなったのです。お金のやりとりもできるだけ避けたいと、わずか数ユーロでもカード決済するように。
それにしても、監禁生活明けが陽光降り注ぐ初夏でどれだけ良かったことか。
朝市にはハーブはじめプリムール - 初もの野菜- が山積みにされ、心浮き立つ季節だったことでどれだけ皆の気持ちが癒されたことでしょう。

(左:透明シートで商品と客を隔てた様子/右:山積みにされたハーブや野菜)
そして街では正常に戻る前の一段階を踏むために、カフェのテラス席での営業が許可されました。
歩道にテーブルや椅子を積み上げて準備する店があちこちに(写真下)。

近所のスターバックスが店頭に赤白テープで印をつけると、そこにスッポリと収まって飲食するパリジャンなのです(写真下)。

久しぶりに入ったいつものカフェのテラスに座って、つい先日まで見事に閑散としていた街に人が溢れ行き交うのを見ていると、一種感無量な気持ちになったものです。
ロックダウン中この人々は無数の窓の向こうで街を見下ろしながら耐えていたのですから。自由を愛するフランス人が、このパリジャンたちが、みんなよく頑張ったなと思うのです。
7月1日以降、カフェやレストランでは屋内営業も許可され、街はすっかり活気を呼び戻しています。街のいたるところでマスク着用を促すパリ市の広告が目につき、店頭にもマスクをつけて入店することを要請する張り紙がよく見られます。

(左:パリでは決してマスクなしで外出しません/右:パリではタッチ(接触)することなく挨拶しましょう)
(下:お花屋さんの扉の張り紙(ピング文字)には「マスクの着用必須です。ありがとう。」と書かれています)

スーパーの出入り口には消毒ジェルが置かれ、警備係が脇に立ってチェックするのも日常の光景になりました。
新型コロナウィルスとの戦いはまだ続いていますが、ロックダウンに際してフランスは誰に対しても平等に義務と責任を負わせたことで、国民を連帯させることには成功したと言ってよいのではないでしょうか。この国の運命には自分自身も関わっているのだという自覚あるフランス国民に敬意を評したいと思うのです。
<ダイニングプラスについて>
2001年事業開始、「dancyu」や「日経プラス1」など取材多数。一流プロ愛用の海外食品を1パックからお届けする通販です。商社直営。
-
 ビーフ100% ひき肉ステーキ(ステークアッシェ) 100g×2
ビーフ100% ひき肉ステーキ(ステークアッシェ) 100g×2 -
 ハーフバゲット 140g×2個入り
ハーフバゲット 140g×2個入り -
 【電子レンジ対応】 エスカルゴ XLサイズ 12個入(殻付き/ガーリックバター入り)
【電子レンジ対応】 エスカルゴ XLサイズ 12個入(殻付き/ガーリックバター入り) -
 りんごとカスタードのタルト 約21cm10カット フランス製 (タルトノルマンディー)
りんごとカスタードのタルト 約21cm10カット フランス製 (タルトノルマンディー) -
 薔薇の花びら茶
薔薇の花びら茶 -
 ベラミーズパイシート フレッシュバター100% 300g
ベラミーズパイシート フレッシュバター100% 300g -
 ベビーターキー 皮なしむね肉 (ターキーブレスト) 500g
ベビーターキー 皮なしむね肉 (ターキーブレスト) 500g -
 信州サーモン 冷燻仕立て
信州サーモン 冷燻仕立て -
 焼くだけ!大きなクロワッサン 発酵バターが香るフランス産 Bake up生地 60g×4個入り
焼くだけ!大きなクロワッサン 発酵バターが香るフランス産 Bake up生地 60g×4個入り -
 ラズベリーパイ 100g x 2個
ラズベリーパイ 100g x 2個 -
アップルパイ 100g×2個
-
 フランス産 マカロン レッドフルーツ アソート 12個 (4種×各3個)
フランス産 マカロン レッドフルーツ アソート 12個 (4種×各3個) -
 ブレス産 AOP発酵バター 250g
ブレス産 AOP発酵バター 250g -
 【送料込み】欧州パンとこだわりのバターを愉しむ欲張りセット
【送料込み】欧州パンとこだわりのバターを愉しむ欲張りセット -
 【送料込み】ヨーロッパ ちょい呑みセット
【送料込み】ヨーロッパ ちょい呑みセット
ここなら住める!ギリシャの美味しい食事|スタッフ海外体験記
美味しい黄桃瓶詰の開発でギリシャを訪問した時のお話です。
黄桃の産地はオリンポスの山の麓から広がるテッサリア平原にあります。
>>特別な日にふさわしい輸入食品セール「クリスマス 2020」はこちら

テッサロニキ空港から車で2時間半。エーゲ海と山との間をドライブしてたどり着いたテッサリア平原にあるメーカーでの商談の合間、ランチに連れて行ってくれたのはラリッサという町のレストランでした。

ラリッサはテッサリア地方の中心都市で、そんなに大きくないもののショッピングエリアもあって、大きすぎず、小さすぎない住みやすそうな町でした。
町に着くと車を止めて歩いてレストランまで5分ほど。
その途中に素敵な古代遺跡が何とも自然に目の前に広がって、ギリシャに居る実感を呼び戻してくれます。(それまでは工場と農場に居たので。。。)

レストランは他のヨーロッパ諸国と変わらない雰囲気です。
真夏の暑い日差しがありますが、とてもカラッとしていて、扉を開け放していても暑くはありません。少し遅めの時間に行ったのでお店は空いていて、店内でありながら外に一番近いベストな席に落ち着きました。
おすすめのお料理を少しずつ適当に注文するね、と言われ、全てお任せで出てくるのを待ちます。おしゃべりしながら待つそんな時間もギリシャの風に吹かれながら心地いいな、と考えているとあっという間にお料理が次々と運ばれてくるのも、せっかちな日本人には嬉しいポイント!

何といってもまずはフェタチーズのドーンとのったサラダ!
ホリアティキサラダとも言われるみたいで、定番野菜のキュウリ、トマト、玉ねぎ、ピーマンがざっくりとカットされて、その上にフェタチーズがあります。このフェタチーズの塩味とほろほろと崩れる食感が野菜をかむたびに一緒に広がって何とも美味しくクセになります。

1㎝ぐらいでカットされたゆでダコを香味野菜と一緒にオリーブオイルとレモンでマリネしたタコサラダ。唐辛子を入れて少しピリッとさせてあてとっても暑い季節にぴったり。
 タコと言えば、足を1本まるごと焼いた一皿も香ばしくてギリシャでは定番。
タコと言えば、足を1本まるごと焼いた一皿も香ばしくてギリシャでは定番。
チーズを揚げたサガナーキはカリッと揚がったものにレモンを少しかけると味が引き締まってまた美味しい。
そしてお魚はシンプルに焼くか揚げるで決まり!


この日出てきたのは小イワシを開いたグリル焼きと、中サイズのイワシのお腹にトマトを積めて焼いたもの、アジを丸ごと揚げたもの。
青魚の大好きな私にとってはとっても嬉しいお魚3連発!
小さなグリル焼きは柔らかくてしっかりした味わいでオリーブオイルが良く合います!
イワシのトマトグリルはハーブの香りがギリシャっぽく、しっとりといただける!
アジのまる揚げはカリッと骨まで火が通っていて香ばしい!
このお魚が美味しいというのは日本人にとって、嬉しいですよね。
翌日、アテネの市場に行ってみたのですが、そこで納得!
市場には新鮮できれいな魚がたくさんありました。
そして魚だけが集まったところでも臭くない!これは新鮮な魚がきちんと管理されている証です!ギリシャの人たちも魚が好きなんだな、と実感しました。


桃を見に来て出会った美味しいギリシャ料理の数々。
どれもとっても美味しくて、ここなら住める!と思わず声に出して言ってしまったほど。
美味しいものが繋ぐ文化、大切にしたいですね。
>>特別な日にふさわしい輸入食品セール「クリスマス 2020」はこちら
<ダイニングプラスについて>
2001年事業開始、「dancyu」や「日経プラス1」など取材多数。一流プロ愛用の海外食品を1パックからお届けする通販です。商社直営。
-
 黄桃のシロップ漬け (瓶詰) 550g
黄桃のシロップ漬け (瓶詰) 550g -
 スモーク オイルサーディン ラトビア産
スモーク オイルサーディン ラトビア産 -
 プチパン プレーン 35g×5個入り
プチパン プレーン 35g×5個入り -
石窯焼き風 田舎風パン (パン ド カンパーニュ )
-
 【電子レンジ対応】 エスカルゴ XLサイズ 12個入(殻付き/ガーリックバター入り)
【電子レンジ対応】 エスカルゴ XLサイズ 12個入(殻付き/ガーリックバター入り) -
 とろニシン レモンじめ 2フィレ(100g~160g)
とろニシン レモンじめ 2フィレ(100g~160g) -
 解凍するだけ カナダ産 ムール貝
解凍するだけ カナダ産 ムール貝 -
 レモン香るエキストラバージンオリーブオイル
レモン香るエキストラバージンオリーブオイル -
 ベーコンとチーズのキッシュ(キッシュ ロレーヌ)
ベーコンとチーズのキッシュ(キッシュ ロレーヌ) -
 りんごとカスタードのタルト 約21cm10カット フランス製 (タルトノルマンディー)
りんごとカスタードのタルト 約21cm10カット フランス製 (タルトノルマンディー) -
 ブレス産 AOP発酵バター 250g
ブレス産 AOP発酵バター 250g -
 ダッテリーノトマトのトマトジュースづけ (皮なし)400g
ダッテリーノトマトのトマトジュースづけ (皮なし)400g -
 【送料込み】欧州パンとこだわりのバターを愉しむ欲張りセット
【送料込み】欧州パンとこだわりのバターを愉しむ欲張りセット -
 【送料無料】ベルデンソ 無ろ過EXVオリーブオイル 3本セット
【送料無料】ベルデンソ 無ろ過EXVオリーブオイル 3本セット -
 【送料込み】週末ご褒美プチセット
【送料込み】週末ご褒美プチセット
簡単豪華カフェランチ!ダイニングプラスの食材でやってみました!
おうちで食事をする機会も増えますよね。
時にはカフェに行ったような素敵なランチができると家族の食事時間も盛り上がるのではないでしょうか?
でも、忙しい日常に準備するのはちょっと大変。。。
そこでダイニングプラスの食材を使って、ほんの少しの手間をかけることでカフェランチができる、というお話です。

最大のポイントはダイニングプラスのキッシュ。
キッシュはパイやタルトの生地に好みの具材と卵と牛乳や生クリームなどを混ぜた卵液を加えてオーブンで焼いたもので、
キッシュ・ロレーヌというフランス、アルザス・ロレーヌ地方のお料理として有名ですね。
今ではフランスだけではなく、イギリスやアメリカなど他の国々でも軽食メニューとして定番の人気料理です。
そういう私もキッシュは大好きなのですが、実際に作るとなると、けっこう面倒です。。。
ダイニングプラスには素晴らしいバターのパイ生地があるので、それを使うと存外簡単なのですが、
今回は『焼くだけ』で簡単に出来上がるタイプのキッシュを使います。
ダイニングプラスのキッシュは2種類あります。
3種のチーズのキッシュ と 地中海野菜のキッシュ


1個が大きめで、例えると今は懐かしいCDぐらいの大きさがあって、
ランチなら、まるまる1個でとっても満足感があります。
大きいのですが、オーブンなら4~5個、
トースターでも3~4個を入れられる絶妙な大きさです。
だから、家族4人分のランチをつくるのにオーブンに入れておけば、
おおよそ20分でその間に付け合せの準備ができて、とってもお手軽なのです!
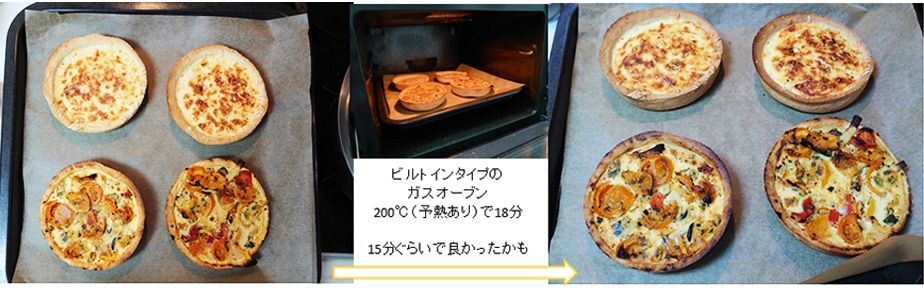
葉野菜をオリーブオイルとバルサミコ酢で和えたものを準備しますが、
そこで、盛り付けた時の華やかさを演出するためのポイント!
葉野菜は事前にお水に1~2時間浸してしゃっきりさせ、水を切っておきます。
今回はベビーリーフを使いましたが、この水に浸すと圧倒的に見栄えが良くなります。
しかも、増量して見えます!
水気をしっかり切った葉野菜にはオリーブオイルとバルサミコ酢をかけて全体を和えてから盛り付けます。
美味しいオリーブオイルとバルサミコがあれば、買い置きのドレッシングは要りません。

今回使っているのは、無ろ過のエキストラバージンオリーブオイルと、
5グレープグレードのバルサミコ酢。
オリーブオイルもですが、このバルサミコ酢は特別♪
丁寧に煮詰めたぶどう果汁を原料の60%使って、小さいオーク樽で熟成させているので、
香りがとっても良いのです!
トロッとシロップのような食感と甘みのあるスペシャルグレード!
これをたっぷりかけて、お好みで塩を少量足して仕上げます!
サラダをお皿に盛りつけたら、あとはキッシュの焼き上がりを待つだけです。

今回は合わせて3品を準備しました。
☆具だくさんトマトスープ

このスープに使ったダイニングプラスの食材は・・・
・ドイツソーセージのオーバークライナー(5㎜厚に切って使用)
・ダッテリーノトマトのトマトジュース漬け
あとはセロリ、玉ねぎ、ニンニク、チキンストックに塩・コショウでシンプルに煮たスープ。
事前にに作っておくと温めるだけで便利!
☆トマトサラダ

こちらは生の大きいトマトをカットして、
葉野菜にも使った無ろ過のオリーブオイルとバルサミコ酢をたっぷりに塩を少々だけ!
☆ピーチヨーグルト

黄桃のシロップ漬けを4等分に切って、小皿にヨーグルトと一緒に盛り付けただけ!
黄桃だけでもしっかり食感でデザートとして美味しいのですが、
ちょっとヘルシーにヨーグルトも♪
あると便利な食材で是非おうちカフェを楽しんでくださいね!
<ダイニングプラスについて>
2001年事業開始、「dancyu」や「日経プラス1」など取材多数。一流プロ愛用の海外食品を1パックからお届けする通販です。商社直営。
-
 3種のチーズのキッシュ(タルトフロマージュサレ)
3種のチーズのキッシュ(タルトフロマージュサレ) -
 地中海風 野菜のキッシュ (タルトメディテラネ)
地中海風 野菜のキッシュ (タルトメディテラネ) -
 ベーコンとチーズのキッシュ(キッシュ ロレーヌ)
ベーコンとチーズのキッシュ(キッシュ ロレーヌ) -
 薔薇の花びら茶
薔薇の花びら茶 -
 ウィンナー ドイツ職人の謹製ウィンナー
ウィンナー ドイツ職人の謹製ウィンナー -
 信州サーモン 冷燻仕立て
信州サーモン 冷燻仕立て -
 肉厚の旨味 大粒ほたて貝(青森産 黄金ほたて) Lサイズ
肉厚の旨味 大粒ほたて貝(青森産 黄金ほたて) Lサイズ -
 焼くだけ!クロワッサン 発酵バターが香るフランス産 Bake up生地 40g×5個入り
焼くだけ!クロワッサン 発酵バターが香るフランス産 Bake up生地 40g×5個入り -
 りんごとカスタードのタルト 約21cm10カット フランス製 (タルトノルマンディー)
りんごとカスタードのタルト 約21cm10カット フランス製 (タルトノルマンディー) -
 ベルデンソ 無ろ過 エキストラバージン オリーブオイル 500ml オリタリア
ベルデンソ 無ろ過 エキストラバージン オリーブオイル 500ml オリタリア -
 モデナ産 バルサミコ酢 IGP 5グレープ 250ml (オリタリアブランド)
モデナ産 バルサミコ酢 IGP 5グレープ 250ml (オリタリアブランド) -
 ダッテリーノトマトのトマトジュースづけ (皮なし)400g
ダッテリーノトマトのトマトジュースづけ (皮なし)400g -
 訳あり バゲット ルヴィノワーズ
訳あり バゲット ルヴィノワーズ -
 【送料込み】欧州パンとこだわりのバターを愉しむ欲張りセット
【送料込み】欧州パンとこだわりのバターを愉しむ欲張りセット -
 【送料込み】週末ご褒美プチセット
【送料込み】週末ご褒美プチセット
ここまで来たダッテリーノトマト進化形 |「そのまま食べて美味しいトマト缶」開発秘話(後編)
今回は『そのまま食べて美味しいトマト缶』を目指したトマト缶開発のお話しの後編です。
4.産地へ。トマト缶生産の現場って?
5.ダッテリーノ(ダッテリーニ)トマトとの出会いと更なる開発への思い
6.皮をむきタイプの誕生!
2014年夏、到着したのはナポリ。当時、トマトを輸出してくれていた会社がナポリにあったのです。その時の目的はトマトの生産現場に立ち会って、美味しさのヒントを探ること。
(このときはその後、トマトのために4度この地を訪れることになるとは夢にも思っていませんでした。)

まずはトマトの栽培農家のあるプーリア州へ。
ナポリのあるカンパニア州からプーリア州への道中、よくすれ違うのはトマトがぎっしり入ったカゴをいっぱい載せたトラック。一気に美味しいトマトへの期待が膨らみます。
プーリア州に入って下りの坂道にさしかかると正面に見えるのは一面の乾いた大地。
実際にその場に入ると、そこには灼熱の太陽の日差しが降り注ぎ、カラッカラの大地がただただ広がっています。 車から一歩外に出ると「暑い」ではなく「痛い」という体感。そのカラッカラの大地には乾きかけた緑が広がり、地平線まで続いていて、よく見ると地面がなんだか赤っぽい。それがトマトでした。
一般的にホールトマトと呼ばれる通常サイズのトマトはベルトコンベアを備えた専用のトラクターで収穫します。一方、ミニトマトはより壊れやすいので、手作業で収穫します。手作業とはいえ、かなりの量ですから、房を大地から持ち上げて、カゴの上にかざして一気に振ってカゴの中に入れていきます。

収穫が終わると今度は加工場へ。
この時に向かったのはカンパニア州にある小さな加工工場。
トマトは7月下旬~9月にかけて2か月間で収穫し、加工されます。一貫して作る大規模なメーカーもある一方、栽培農家、加工工場、出荷工場とそれぞれが大中小の規模で分業しているのがほとんどです。
そうした一連の流れの中で、朝、高速道路で見たのはプーリア州の農家で採れたトマトをカンパニア州の加工工場に運んでいる姿だったのです。
トマトの生産は見ました。皆さんが懸命に作ってくれたトマト缶。
どうしたらもっと美味しいものに出会えるか?
「チェリートマトを漬けるトマトジュースを同じ工場内で一貫生産し、トマトの糖度を指定して作ってください。 もちろん食塩やクエン酸は使わずに。」
そうしてチェリートマトデビュー2年目。
それなりに美味しいのですが、まだベストじゃない。。。
もう一度イタリアへ。
2015年夏、どうしても納得できず、向かったのは再びナポリ。
工場はたくさんあるので、今度は大規模な工場に連れて行ってもらいました。
そこで見つけたのがダッテリーノ(複数系でダッテリーニ)。

工場に行くと当然製品を試食するのですが、やっぱりダッテリーノ(ダッテリーニ)が美味しい。 値段が高くなると言われて一旦はあきらめたダッテリーノですが、再び工場を2社訪問して、ダッテリーノへの思いは強くなる一方です。
工場訪問のときは「ダッテリーノがいいなぁ」という気持ちを何度も声に出して先方に伝え、やっとダッテリーノ(ダッテリーニ)をリーズナブルに作ってくれることになりました!
もちろん、食塩やクエン酸は使用しないで!という条件も了承してもらってのことです。
そして実際に販売を始めたダッテリーノ(ダッテリーニ)。
「やっぱりダッテリーノ(ダッテリーニ)にして良かった。」という実感を得ながら販売を続けて2年目のこと。 商品をプレゼントした友達から言われた言葉。
「こないだもらったトマト缶。皮がついててびっくりした!あわてて取ったわ!」
そこで私の心の奥に潜んでいた(あえて気づかないふりをしていた・・・?)気持ちが沸き起こってきたのです。
「皮をむきたい・・・」
プーリアの大地でたくましく育ったトマトはとっても美味しいのですが、太陽をさんさんと浴びて皮が厚くなります。しかもクエン酸を使わずにシンプルに作ったトマト缶の中ではトマトの皮はあまり柔らかくはならない。。。
お料理する時に皮はツヤっとして見た目はきれいだし、自然な美味しさも持っているのですが、食べ物はやはり美味しくなくては。。。その原則に照らし合わせると皮は一方、雑味とも取れるのです。
そこで次の開発へと思いは強くなっていきました。
6. 皮むきタイプの誕生
2017年ヨーロッパ最大の展示会でのこと。
イタリアのコーナーでトマトを見かけると「ダッテリーノ(ダッテリーニ)の皮をむいてもらえませんか?」と聞いて歩きました。
ほとんどのメーカーは「ミニトマトの皮はむけないよ」と相手にしてもらえません。
「なんで皮がついていたらダメなの?」とやっぱりとても難しいようです。
何社目だったか・・・
とても混雑していて、ブースにある商談席は埋まっていました。
何回かそのブースの前を行き来して、やっと担当者と話をしたところ、「できるよ」とあっさり承知してくれたのです。
後からわかったのですが、このメーカーでもミニトマトの皮むきタイプを本格的に商品化するのは初めてのことだったようです。
なぜなのか?
今だからわかるのですが、大きなトマトの皮をむくこととミニトマトの皮をむくことは手間のかかり方が全然違うのです。


その手間をあえてかけて、「ダッテリーノトマト(ダッテリーニ) 皮なし」の初生産にこぎつけたのが2018年夏。日本に入荷したのはその年の年末。
とにかく気になるのは最終製品の味。
届いて試食してみたら・・・
やっぱり美味しい!
雑味がなくて、トマトジュースとのバランスも良く、「そのまま食べて美味しいトマト」の完成形とも思える満足のゆく味です。
しかも・・・
とても良いメーカーに出会うことができ、プーリア州のトマト畑の真ん中に工場があります。プーリア州で採れたトマトをプーリア州の工場でトマトジュースから一貫生産! だからとにかく新鮮なうちに加工することができるのです。
なんと収穫後6時間以内に加工。
そして何と言っても皮むきタイプ!
皮をむいたことで雑味のない仕上がり!
まさに「そのまま食べて美味しいトマト缶」が出来上がりました♪

ここでひとつだけ、おことわりしておきたいことがあります。
皮なしタイプのダッテリーノトマト(ダッテリーニ)はメーカーにとっても大変な作業で、100%の皮を除くことはまだできていません。
でも2年連続生産に立ち会わせてもらい、進化しております。
今年入荷分からは皮残りが半減以下!
「そのまま食べて美味しいトマト」を追い求めてここまで来た、皮なしタイプのダッテリーノトマト(ダッテリーニ)。皆さんにも食べてもらいたいなぁ。
<ダイニングプラスについて>
2001年事業開始、「dancyu」や「日経プラス1」など取材多数。一流プロ愛用の海外食品を1パックからお届けする通販です。商社直営。
-
 【送料込み】ダッテリーノトマトのトマトジュースづけ (皮なし)400g×48
【送料込み】ダッテリーノトマトのトマトジュースづけ (皮なし)400g×48 -
ダッテリーノトマトのトマトジュースづけ (皮なし)400g
-
 古代の穀物 もっちりスペルト小麦 北海道産
古代の穀物 もっちりスペルト小麦 北海道産 -
 ベラミーズパイシート フレッシュバター100% 300g
ベラミーズパイシート フレッシュバター100% 300g -
 2種チーズのバスクチーズケーキ
2種チーズのバスクチーズケーキ -
 セミドライ チェリートマトのオイル漬け 180g
セミドライ チェリートマトのオイル漬け 180g -
 ふわもち食感 サンドイッチ チャバタ 130g×1個
ふわもち食感 サンドイッチ チャバタ 130g×1個 -
 りんごとカスタードのタルト 約21cm10カット フランス製 (タルトノルマンディー)
りんごとカスタードのタルト 約21cm10カット フランス製 (タルトノルマンディー) -
 箱入り薪窯ピザ 4チーズ 200g
箱入り薪窯ピザ 4チーズ 200g -
 モデナ産 バルサミコ酢 IGP 5グレープ 250ml (オリタリアブランド)
モデナ産 バルサミコ酢 IGP 5グレープ 250ml (オリタリアブランド) -
 色とりどり3種のオリーブ
色とりどり3種のオリーブ -
 パテ ド カンパーニュ ブロック (田舎風豚のパテ)オーセンティック
パテ ド カンパーニュ ブロック (田舎風豚のパテ)オーセンティック -
 【送料込み】欧州パンとこだわりのバターを愉しむ欲張りセット
【送料込み】欧州パンとこだわりのバターを愉しむ欲張りセット -
 【送料無料】ベルデンソ 無ろ過EXVオリーブオイル 3本セット
【送料無料】ベルデンソ 無ろ過EXVオリーブオイル 3本セット -
 【送料込み】週末ご褒美プチセット
【送料込み】週末ご褒美プチセット
イタリアでトマト会議|「そのまま食べて美味しいトマト缶」開発秘話(前編)
アレンジ自在で、パスタやスープ、煮込み料理、カレーやトッピングなどキッチンの常備品の定番です。
最近ではトマト鍋も人気の定番鍋になっています。
でもトマトが大好きな人でもトマト缶のトマトをそのまま食べようとはあまり思わないのではないでしょうか?
今回は『そのまま食べて美味しいトマト缶』の記載がを目指したトマト缶開発のお話しです。

1.そのまま食べて美味しいトマト缶ってどんなの?
2.イタリアでトマト会議
3.チェリートマトにしよう
4.産地へ。トマト缶生産の現場って?
5.ダッテリーノ(ダッテリーニ)トマトとの出会いと更なる開発への思い
6.皮をむきタイプの誕生!

1.そのまま食べて美味しいトマト缶ってどんなの?
きっかけはTVショッピング会社のバイヤーさんとの話でした。
「トマト缶って、アレンジもきくし今や必需品のひとつだけど、そのまま食べようとは思えないよね、だったらそのまま食べても、もちろんアレンジ料理に使っても美味しいトマトがあったら嬉しいよね。」
トマトの旬は夏ですが、日本では1年を通して生果のトマトは手に入ります。品種改良もされて、農家さんに大切に育てられたトマトは見た目だけでなく、甘くて美味しいトマトもたくさん見かけるようになりました。でも生果のトマトは日持ちはしないし、値段も張る。そして夏の日差しを浴びた太陽の味がするようなトマトは1年のうちのほんの1時期しか手に入りません。
だったらアレンジ自在の缶詰のトマトで美味しくてリーズナブルなものが手に入ったら嬉しいのでは?
ということで開発が始まったわけですが、じゃ、缶詰のトマトでそのまま食べて美味しいものってどんなのだろう?
水っぽくなくて、トマトの味がしっかりして、生臭みがなく、甘みと酸味のバランスの良いもの。。。
いろいろ考えるうちに思いました。
そうだ、イタリアへ行こう!
トマト缶と言えば、やっぱりイタリアでしょう。
ということで、イタリアの知人の会社に協力してもらい、イタリアのトマト製品をたくさん集めてもらい、とあるお店でトマト会議を開きました。これが2013年のことです。
ずらっと並んだトマト製品。「美味しいトマト缶」と伝えてあったのですが、缶詰だけではなく瓶詰やソースになったものなどがずらっとテーブルに並びました。

まずはひとつずつ、そのまま試食。
ブランドや種類によってトマトでもいろんな味わいがあることに気づきます。そして当時の日本ではまだ見かけないミニトマトの缶詰もあり、テンションが上がります。
会場はレストラン、当然厨房が隣にあります。
美味しいと思ったら、それを調理してみてどうなるのか?
早速シェフがサラダやパスタなどの料理にしてくれます。

美味しくても値段が高すぎたら常備品として便利とは言えない!
だから各メーカーから取り寄せた価格についても一緒に検討です。
3.チェリートマトにしよう
当時、ダッテリーノトマトはありました。でも瓶詰が主流でとにかく高価。
高価すぎるものはトマト加工品には求めていません。
そこで、味わいも見た目も価格もぴったり来たのがチェリートマトだったのです。いわゆるミニトマトですが、2013年の段階ではまだまだ珍しい商品で、何よりころころとかわいらしくお料理にしたときの見栄えにテンションがあがりました!

これだったら見た目も良いし、アレンジの幅も広がって、スープやパスタにしても具材として見た目のかわいらしさも楽しめる!
もちろんトマト鍋だって煮込みだって・・・ とわくわくがとまりません。
「クエン酸も食塩も使わず、シンプルにトマトだけを使って作ってください。」
そう依頼をして、最終製品の見本を送ってもらい、一番美味しかったロットの発注!
そうして2014年、チェリートマトのジュース漬けがデビューしたのです。
実際に商品がコンテナで届いて検品をしました。

ころころとかわいい!
味も悪くない!
でもベストではない。。。というのが正直な感想でした。
どうしたらもっと美味しくなるんだろう。
そこでその夏、トマトの産地にプーリア州に向かいました。
後編へつづく >【ここまで来た!ダッテリーノトマト缶(後編)】
<ダイニングプラスについて>
2001年事業開始、「dancyu」や「日経プラス1」など取材多数。一流プロ愛用の海外食品を1パックからお届けする通販です。商社直営。
-
 【送料込み】ダッテリーノトマトのトマトジュースづけ (皮なし)400g×48
【送料込み】ダッテリーノトマトのトマトジュースづけ (皮なし)400g×48 -
ダッテリーノトマトのトマトジュースづけ (皮なし)400g
-
 モデナ産 バルサミコ酢 IGP 5グレープ 250ml (オリタリアブランド)
モデナ産 バルサミコ酢 IGP 5グレープ 250ml (オリタリアブランド) -
 ベルデンソ 無ろ過 エキストラバージン オリーブオイル 500ml オリタリア
ベルデンソ 無ろ過 エキストラバージン オリーブオイル 500ml オリタリア -
 ベラミーズパイシート フレッシュバター100% 300g
ベラミーズパイシート フレッシュバター100% 300g -
 ハーブ香るブラートヴルスト ドイツ職人の絹引き焼きソーセージ
ハーブ香るブラートヴルスト ドイツ職人の絹引き焼きソーセージ -
 仔牛 チークミート1.4kg (ミルクフェッドヴィ―ル ほほ肉)
仔牛 チークミート1.4kg (ミルクフェッドヴィ―ル ほほ肉) -
 【電子レンジ対応】 エスカルゴ XLサイズ 12個入(殻付き/ガーリックバター入り)
【電子レンジ対応】 エスカルゴ XLサイズ 12個入(殻付き/ガーリックバター入り) -
 解凍するだけ カナダ産 ムール貝
解凍するだけ カナダ産 ムール貝 -
 3種のチーズのキッシュ(タルトフロマージュサレ)
3種のチーズのキッシュ(タルトフロマージュサレ) -
 ポテトニョッキ 1kg
ポテトニョッキ 1kg -
 薪窯ナポリ風ピザ マルゲリータ 200g
薪窯ナポリ風ピザ マルゲリータ 200g -
 完熟チェリートマトが丸ごと入ったトマトパスタソース 280g
完熟チェリートマトが丸ごと入ったトマトパスタソース 280g -
 【送料込み】欧州パンとこだわりのバターを愉しむ欲張りセット
【送料込み】欧州パンとこだわりのバターを愉しむ欲張りセット -
 【送料込み】ヨーロッパ ちょい呑みセット
【送料込み】ヨーロッパ ちょい呑みセット
イタリアの大衆レストランの魅力(トリノ編)|スタッフ海外体験記
海外出張に行く楽しみの一つ(いやほとんどかも。。。)は食事であることは言うまでもありません。
我々は食品業界にいるため、サプライアーである現地の人に連れて行ってもらうお店はほぼ間違いありません。
(すみません、根が正直で「ほぼ」と入れたのは、たまにそうでない事があるからです。。。)
特に和食を愛する日本人にとって、イタリアの食事は合いますよね、と言ってご賛同いただける方も多いのでは?

イタリアにもリストランテ(高級レストラン)、トラットリア(大衆レストラン)、オステリア(居酒屋)などといろいろありますが、実際に行ってみると、この区別は意外とあいまいなことが多いように思います。
そして個人的な趣向としては、何と言ってもトラットリア、オステリア、つまり気取らないお店が素敵です。
>特別な日にふさわしい輸入食品セール「クリスマス 2020」はこちら

その日は、日本からトリノに着き、翌日の予定に合わせて空港近くに宿を取っていました。
午前中に到着したため、昼間の時間を使って、ピエモンテ州にある元サプライアー(残念ながらそこの商品は終売になったのですが…)の担当者とランチすることにしました。
夏の強い日差しが降り注ぐトリノ。日本からの長距離フライトの後なので、疲れた体にこの日差しはキツイな、と思いながらせっかくの機会だから、と出かけていきました。
ちょうどランチ時、暑いこともあって歩いている人はあまり見かけません。が、そこはヨーロッパ。カフェやトラットリアはこぞってテラス席を作り、そこにはたくさんの人たちが食事を楽しんでいるのです。

私たちもそんな広場のテラスに席を見つけて落ちつき、冷えた白ワインで一服。

座ってまず出てきたのは具なしピザのようなもの。
一気にテンションが上がります。。。(我ながらなんて単純。。。)
この具なしピザ、直前にタラッとフレッシュなオリーブオイルをかけて食べると何と美味しいこと!こんな暑い日の前菜にはヨーロッパ人が大好きな苦くてピリッとくるはっきりした味わいのオリーブオイルが良く合います。
でもこれを食べすぎると次が食べられない!とブレーキをかけながら噛みしめます。
>特別な日にふさわしい輸入食品セール「クリスマス 2020」はこちら

そしてメインに私が選んだのはラディッキオロッソのリゾット。
ラディッキオとはチコリとかトレビスとかいうこともあるようですが、これは、赤いタイプ。全く同じものは日本ではあまり見かけません。
ほんのり苦みのあるラディッキオロッソがたっぷり入って、色がきれい。
角切りのパンチェッタが入っているので、味わいも力強く、コクがある!回りには甘みと酸味のバランスの良いバルサミコのソースでデコレート。時々これを混ぜると酸味によって味が引き締まってより美味しい!!

お隣は・・・アサリのニョッキ。ニョッキとアサリの組み合わせは初めて!!
ということで一口もらうと・・・
ニョッキのもっちりした食感の周りにアサリの旨みが絡んで美味しい!
トリノの中心部の観光地である広場でたまたま見つけて入ったトラットリアでこんな美味に出会えるのはやっぱりイタリアって素敵!
<ダイニングプラスについて>
2001年創業の上質食品通販サイト。日本を代表する高級ホテル、ミシュラン星付きレストランが採用する高品質な業務用食品を、どなたでも1パックから購入できます。テレビ各社や「ダンチュウ」、「エル・ジャポン」など、メディア紹介多数。
-
 薪窯ナポリ風ピザ マルゲリータ 200g
薪窯ナポリ風ピザ マルゲリータ 200g -
 ポテトニョッキ 1kg
ポテトニョッキ 1kg -
 ダッテリーノトマトのトマトジュースづけ (皮なし)400g
ダッテリーノトマトのトマトジュースづけ (皮なし)400g -
 シチリア産大人のブラッドオレンジマーマレード
シチリア産大人のブラッドオレンジマーマレード -
 薔薇のハーブソルト(ミル付き)
薔薇のハーブソルト(ミル付き) -
 2種チーズのバスクチーズケーキ
2種チーズのバスクチーズケーキ -
 仔牛 チークミート1.3kg (ミルクフェッドヴィ―ル ほほ肉)
仔牛 チークミート1.3kg (ミルクフェッドヴィ―ル ほほ肉) -
 解凍するだけ カナダ産 ムール貝
解凍するだけ カナダ産 ムール貝 -
 トリュフ香るエキストラバージンオリーブオイル
トリュフ香るエキストラバージンオリーブオイル -
 ふわもち食感 サンドイッチ チャバタ 130g×1個
ふわもち食感 サンドイッチ チャバタ 130g×1個 -
 焼くだけ!クロワッサン 発酵バターが香るフランス産 Bake up生地 40g×5個入り
焼くだけ!クロワッサン 発酵バターが香るフランス産 Bake up生地 40g×5個入り -
 完熟チェリートマトが丸ごと入ったトマトパスタソース 280g
完熟チェリートマトが丸ごと入ったトマトパスタソース 280g -
 【送料込み】欧州パンとこだわりのバターを愉しむ欲張りセット
【送料込み】欧州パンとこだわりのバターを愉しむ欲張りセット -
 【送料無料】ベルデンソ 無ろ過EXVオリーブオイル 3本セット
【送料無料】ベルデンソ 無ろ過EXVオリーブオイル 3本セット -
 【送料込み】週末ご褒美プチセット
【送料込み】週末ご褒美プチセット
ライ麦パンを思う|ダイニングプラス

「ライ麦パン」と聞くと何となくそわそわする。
そんな方いらっしゃいませんか?私はそのそわそわする一人です。
最近、やっと日本でもライ麦パンを入手しやすくなってきました。
そこでいろいろと思い返してみました。
約20年前、フランスのパン屋さんで売り子をしていた頃、それはストラスブールというドイツとの国境の町だったので、マダムは毎日のようにドイツにライ麦パンをオーダーしていました。
私もいつしかオーダーを任されるようになり、とはいっても、商品名がずらっと書かれた専用のフォームに数を書き込むだけなのですが、ドイツパンの多さに驚いたものです。
国境とはいってもフランスのパン屋さんなので、もちろん売れ筋は圧倒的にお店で焼いたバゲットやクロワッサンです。
そんな中、ドイツパンの売れ筋のひとつはPain de Seigle、ライ麦が65%以上入った黒いカチカチのパンでした。

ちなみに他にも人気商品があり、ひまわりの種やかぼちゃの種がゴロゴロと中にも外にも入ったパンにも当然のようにライ麦を配合したパン生地がベースになっていました。
当時は黒いパンのおいしさにはあまり目覚めておらず、もっぱらプレッツェル生地のパンをよく食べていました。
今となってはもったいないことをしたなぁ、と反省しきりです。

その後、ダイニングプラスをオープンして数年、2008年ごろの人気商品のひとつがフィンランドのライ麦パン、
その名も「ライマックス」。
平べったい草履のような形、真ん中に切れ込みが入っていて、簡単にサンドイッチが作れて美味しいだけでなく、とても便利な商品でした。当時の社内ではランチにこのライマックスをお弁当に持ってくる女性社員の多かったこと!
ただ、当時のライ麦パンの評判はというと、「すっぱくて硬い黒いパン」と特に男性をはじめ、多くの日本人には好かれず、あえなく終売となってしまいました。
でも今でも古参社員からは「あのパンが食べたい」と熱烈なコールのある商品!
そして時代も変わってライ麦パンにそわそわする人が増えてきた!という思いで、現在、復活を画策しております。

さて、現在ダイニングプラスで取り扱っているパンの中でもサイトオープン前から20年以上、定番で人気のあるもののひとつがパン・オ・セーグルです。
こちらはライ麦粉を20%、小麦粉に混ぜて石窯で焼いて作っています。
なぜ人気なのか?
ライ麦パンの美味しさを取り入れ、ライ麦パンの評判の悪いところをなくした程の良いパンなのです。
すっぱいパン?
いいえ、すっぱくありません。ほんのりと香るライ麦が心地良いです。
硬いパン?
いいえ、中はふっくらしていて回りはカリッとなります。
黒いパン?
いいえ、ライ麦の色合いが程よくで、濃い茶色をしています。
すっぱくて黒いライ麦パンが好き!という方には物足りないかもしれません。
この商品はフランス人が作ったライ麦パン。
だから!
ライ麦のほのかな香りが楽しめて、何よりもパンとして美味しく、いろんな食材の味を引き立ててくれるパンなのです!!
今では市民権を得た感のある「ライ麦パン」
ダイニングプラスではこれからも「美味しいパン」を提供していきますね~♪
<ダイニングプラスについて>
2001年事業開始の輸入食品通販サイト。「読売テレビ」「関西テレビ」「ダンチュウ」や「日経プラス1」など、メディア紹介多数。だれもが知る高級ホテルやレストランの高品質な輸入食品をどなたでも1パックから購入できる食品通販です。商社直営。
-
石窯焼き パン オ セーグル (ライ麦パン)
-
石窯焼き パン ド カンパーニュ (田舎風パン)
-
 パテ ド カンパーニュ ブロック (田舎風豚のパテ) スタンダード
パテ ド カンパーニュ ブロック (田舎風豚のパテ) スタンダード -
 そのまま食べられるアボカドスライス130g
そのまま食べられるアボカドスライス130g -
 2種チーズのバスクチーズケーキ
2種チーズのバスクチーズケーキ -
 信州サーモン 冷燻仕立て
信州サーモン 冷燻仕立て -
 3種のチーズのキッシュ(タルトフロマージュサレ)
3種のチーズのキッシュ(タルトフロマージュサレ) -
 ラズベリーパイ 100g x 2個
ラズベリーパイ 100g x 2個 -
 紫いちじくジャム
紫いちじくジャム -
 ブレス産 AOP発酵バター 250g
ブレス産 AOP発酵バター 250g -
 ブレス産 発酵バター ドゥミセル (加塩) 250g
ブレス産 発酵バター ドゥミセル (加塩) 250g -
 フランス伝統生ハム IGP ジャンボン ド バイヨンヌ 50g
フランス伝統生ハム IGP ジャンボン ド バイヨンヌ 50g -
 【送料込み】欧州パンとこだわりのバターを愉しむ欲張りセット
【送料込み】欧州パンとこだわりのバターを愉しむ欲張りセット -
 【サンプル セット】7種類のお食事パンお味見用セット
【サンプル セット】7種類のお食事パンお味見用セット -
 【送料込み】週末ご褒美プチセット
【送料込み】週末ご褒美プチセット
【おうち時間を楽しもう】アフタヌーンティーへのお誘い
新型コロナウイルス対策、皆さんお疲れ様です。毎日大変ですよね。お疲れ出ていませんか?
気が張り詰めがちなときは自分自身をいたわって、気分転換にゆっくりお茶とプティスイーツでもいただきませんか。
ちょっと贅沢なご褒美に、日本でも楽しむ人が増えてきた「アフタヌーンティー」はいかがでしょう。やってみたいけどとっつきにくい、
そう感じている方もおられるのでは?今回ご提案するのは、手軽な「おうちアフタヌーンティー」。
優雅な午後のティータイムを自分で作る、工夫が楽しい趣味のひとつです。おうちで好きな雑貨を活用すれば、あなただけの特別な午後のひとときに気分も晴れやかになりそう。
季節感を取り入れて気軽にアレンジを楽しむ「アフタヌーンティー」のアイデアをご紹介します。

1.アレンジして楽しむ「おうちアフタヌーンティー」
1-1 「おうちアフタヌーンティー」をする場所は?
1-2 テーブルセッティングで上質な空間
1-3 食器選びはここがポイント
1-4 カトラリーと小物で手軽に季節感
1-5 「おうちアフタヌーンティー」におすすめのメニュー
【アレンジして楽しむ「おうちアフタヌーンティー」】
おうちでちょっと華やかに、リラックスできるお茶の時間を楽しみたい!
そこでダイニングプラスでは、ぐっとカジュアルで気軽な「おうちアフタヌーンティー」をご提案します。
テーブルやお部屋に季節を取り入れ、お好きなテイストでアレンジすれば、そこがあなたの特別なティールーム!
1. 「おうちアフタヌーンティー」をする場所は?
ティールームでの「アフタヌーンティー」もいいですが、おうち遊びでピクニックのようにお庭やベランダ、中庭などで過ごすのはいかがでしょう。外で好きな食べ物や、香りの良いお茶の葉を楽しむ「アフタヌーンティー」は季節も感じられます。

2. テーブルセッティングで上質な空間
面積が広いテーブルは、テーブルクロスの色を季節に合わせて変えるだけで、その場の雰囲気ががらりと変わります。気分が晴れやかになるピンクやオレンジ、落ち着いた気分で過ごすならグリーンやブルーはいかがでしょう。
おこもり生活にアクセントをつける四季折々のお花も飾ってみましょう。新鮮なお花からは元気がもらえます。ちょっとした花束をお部屋にかざれば、季節感があふれて気分はもうお城のお姫様♪それにキャンドルがあれば、ぬくもりのある火のゆらぎに、心も癒されることでしょう。

3.食器選びはここがポイント
お皿が3枚セットされているケーキスタンドがなくても、お気に入りのお皿に季節感あふれるスイーツやサンドウィッチを盛りつければ立派な「おうちアフタヌーンティー」になります。
4.カトラリーと小物で手軽に季節感
フォーマルなマナーでもカトラリーはほとんど必要ありません。バターナイフやデザートスプーンなど、ごく簡単なもので十分です。小物ならイメージを変えやすいのでお勧めです。季節のお花を添えればフレッシュなイメージのアレンジが簡単にできあがります。暖かみがある雰囲気がお好みなら 金色系や手描きの工芸品を取りれてみても。リボン等の雑貨を活用すれば、手軽にかわいらしいイメージに仕上がります。

5. 「おうちアフタヌーンティー」におすすめのメニュー
「アフタヌーンティー」は紅茶とともに軽くつまめる食べ物をちょっとずつ楽しむのが魅力なので、
色や形に愛らしさを意識するときれいに仕上がります。
華やかさで人気があるのは何といってもマカロン!彩り豊かで、お皿にならべるだけでおうちがちょっと特別な空間に変わります。特にフランス産はあっさり目の国産のマカロンとは違い、他にないサクサクした食感としっかりフルーティーな風味が魅力。
コースのアクセントとしても大活躍してくれます。
.jpg)
また、季節をメニューに取り込むのも腕の見せ所。 ダイニングプラスのサイトで料理研究家の上野万梨子さんが連載している「簡単おしゃれレシピ」を使えば、レシピのヒントがたくさん見つかります。 たとえばヒヨコを思わせるようなハモンセラーノと卵を使ったお料理は、イースターにぴったり。
また、クロワッサンを輪切りにして具材をもりつける斬新なアイデアでは、バターの香り豊かでおしゃれな一品があっという間にできあがります。
好きなものを自由に楽しめるのが「おうちアフタヌーンティー」の魅力。 もう少ししっかりお食事をいただきたい、そんな方にはキッシュ系がおすすめ。 最近の冷凍食品にはトースターですぐできるものもあり、とても便利です。 キッシュは作った時に時間をかけて火をいれることで香りや風味が凝縮されています。 だから調理がとても簡単で、小ぶりのピースでもしつこくないのにしっかりした食べ応え。 紅茶はもちろん、シャンパーニュともよく合います。
新型コロナウイルス対策のなかでは、いつものお買いものでも人と会ったり、並んだりするのも気後れしがち。食品通販なら人ごみに出ることなく、海外食品ショッピングやプロのレシピ、美しい写真を、
おうちでゆっくりお楽しみいただけます。時間と手間をカットして上質なあなただけの時間を愉しめば、毎日の生活が彩り豊かになりそうです。
<ダイニングプラスについて>
2001年事業開始、「dancyu」や「日経プラス1」など、メディア紹介多数。こだわりプロ愛用の美味しい海外食品を1パックからお届けする食品通販です。商社直営。
-
 《期間限定》キラキラ夏のアフタヌーンティーセット
《期間限定》キラキラ夏のアフタヌーンティーセット -
 【まるで高級ホテル】な早起きが楽しみになる朝食セット
【まるで高級ホテル】な早起きが楽しみになる朝食セット -
 フランス産 マカロン レッドフルーツ アソート 12個 (4種×各3個)
フランス産 マカロン レッドフルーツ アソート 12個 (4種×各3個) -
 ハムとパセリの彩りテリーヌ (ジャンボン ペルシェ)
ハムとパセリの彩りテリーヌ (ジャンボン ペルシェ) -
 ミニ カヌレ 7個入り
ミニ カヌレ 7個入り -
 信州サーモン 冷燻仕立て
信州サーモン 冷燻仕立て -
 3種のチーズの キッシュ (タルトフロマージュサレ)
3種のチーズの キッシュ (タルトフロマージュサレ) -
 焼くだけ!ミニパンオショコラ 発酵バターが香るフランス産 Bake up生地 30g×6個入り
焼くだけ!ミニパンオショコラ 発酵バターが香るフランス産 Bake up生地 30g×6個入り -
 焼くだけ!ミニクロワッサン 発酵バターが香るフランス産 bake up生地 25g x8個入り
焼くだけ!ミニクロワッサン 発酵バターが香るフランス産 bake up生地 25g x8個入り -
 6種のベリー 北欧カフェデニッシュ 2個入
6種のベリー 北欧カフェデニッシュ 2個入 -
 なめらか食感のブルーベリージャム (プレザーブスタイル)
なめらか食感のブルーベリージャム (プレザーブスタイル) -
冷凍 ポム アリュメット (フレンチフライポテト) 450g
-
 ハモンセラーノ (50gパック)
ハモンセラーノ (50gパック) -
 レモン香るエキストラバージンオリーブオイル
レモン香るエキストラバージンオリーブオイル -
 【サンプル セット】12種類のデニッシュ&パイお味見用セット
【サンプル セット】12種類のデニッシュ&パイお味見用セット
ジャンボン・フロマージュのサンドイッチ|スタッフ海外体験記

フランスに行くと必ず一度は食べたいもののひとつ、それはサンドイッチ。
いわゆるバゲットサンドですが、中でもJambon et Fromage(ジャンボン エ フロマージュ/ハムとチーズ) がお気に入りです。
機内でもエールフランスのヨーロッパ域内の短距離便で、食事時間のフライトの場合にはサンドイッチが機内食として出されます。 サンドイッチのパターンはいくつかありますが、大好物のジャンボン・フロマージュのサンドイッチが出た時は内心小躍りです! 今でもフランスでちょっと余った時間があると美味しいサンドイッチを求めて買いに行きます。

(機内のサンドイッチ)

(購入したサンドイッチ)
以前、フランスのパン屋さんで売り子として働いていた時、最初に任された仕事はこのサンドイッチ作りでした。
日本のサンドイッチしか知らなかった当時、その具材の多さにびっくりしました。
具材の種類ではなく、中に入れるボリュームが多いのです。
まずはバター。
日本ではやわらかいマーガリンをうっすら塗る程度のところ、いえいえ、そこはバターの国フランス。
厨房から取ってきたまだ固いバターの塊からたっぷりナイフにとって、半分に切り目を入れたバゲットの片面にベターっと。
多少かたまっていても、かたよっていても、まったく気にしません。 そこにグリュイエールチーズとハム(Jambon de Paris つまり日本でもおなじみの加熱ハム)のスライスをたっぷりはみ出るぐらい。。。
湿度の低いフランスではバゲットのカリッとした皮の食感が長持ちして、食感が良いだけではなく、バターの層ができるほど入れられたバターの存在感!
しかもそのバターは発酵バターですから、ほんのりのした酸味がこのサンドイッチの美味しさを決めるのです!
さて、先日のパリ。その日は日曜日でパリ市内のお店もお休みが多く・・・ググりました。
「近くのサンドイッチ 人気」で、出てきたのはヴァンドーム広場の近くのサンドイッチ専門店。

その日は小雨の肌寒い日。
歩いている人は少なく、お店は小道を入って歩いて行ったところにありました。
お店が近づくと中は見えないのに何となくざわ~っとにぎわいが伝わります。
後で気づいたのですが、お店の出入りが多いのです。
お店に入ると左側には奥から手前まで2~4名用の小さな丸テーブルとイスがぎっしりとあり、その全てのイスがお客さんで埋まっています。
右手にはカウンターがあり、中ではおじさんがサンドイッチを作り、その横には息子らしい人が飲み物の準備に忙しそうです。
目が合って、カウンターを指さして「座ってもいい?」と合図を送ると目でどうぞ、と。
そして注文。
当然、”un sandwich jambon fromage” シルヴプレ!
すると、どのチーズにする?と聞かれ、シェーヴル、ブルー、白カビ、ハード、といろんなタイプがあるのに気づきました。
そこは迷わずハードタイプなのですが、中でも大好きな“コンテ”でオーダー。
するとおじさんが鼻歌を歌いながら、素手でズタ袋の中に手を入れたら小ぶりのバゲットを1本つかみ、良く切れるナイフで間にスッと切り込みを入れる。
次は目の前のバターの山に突き刺さったバターナイフを手に取ってたっぷりのバターをサッとひと塗り。ナイフをバターの山に戻すと素手でハムとチーズを順番にまんべんなく敷き詰め、最後に真ん中で半分に切って出来上がり。
何とも手際の良いこと。

この日は湿度が高めだったからか、バゲットのバリッとした部分が少なくてちょっと残念だったのですが、中身のハムやチーズはしっかり吟味してあって、噛むほどに良質な小麦の味わいとまじりあって美味しさが出てきます。
たっぷり塗られたバターはもちろんハムともパンとも良く合います。
それにしても圧巻はバターの山。
私が行ったのは午後2時過ぎですから、仮に朝9時から営業していたとして、
いったいこの山はどれだけの高さがあったのかなぁ、などと考えながらかぶりつきました。

ゆっくり食べながらいろいろ観察するときはこんな狭いお店のカウンターは最適ですね。
お店はパリッ子だけでなく観光客にも人気らしく、おじさんは片言の英語ができるようです。カウンターは一人客が思い思いに時間を過ごすだけでなく、カウンターの右側には持ち帰り用のオーダースペースもあります。
子供連れのお父さんがサンドイッチを4つぐらい買って行ったり、アメリカ人風のカップルが食べながら出て行ったり。
そんな持ち帰り客の担当はサンドイッチ作りを担当するおじさん。
ちなみに、素手でお金を受け取り、手は流水で軽く流してからまた素手でサンドイッチ作りへ・・・。
『大丈夫なのか?!』とサンドイッチにかぶりつきながら思わず苦笑い。
あのお店もこの新型コロナで休業中でしょう。。。
騒ぎが収まったら、おじさんは手袋をするのかな・・・なんて気になったりする今日この頃です。
<ダイニングプラスについて>
2001年事業開始、「dancyu」や「日経プラス1」など取材多数。一流プロ愛用の海外食品を1パックからお届けする通販です。商社直営。
-
 優しい味わいのホワイトハム (ジャンボンプティ ブラン)
優しい味わいのホワイトハム (ジャンボンプティ ブラン) -
 ジャンボン ド バイヨンヌ IGP 50g
ジャンボン ド バイヨンヌ IGP 50g -
 ハーフバゲット 140g×2個入り
ハーフバゲット 140g×2個入り -
 薔薇と和紅茶のティーバッグ
薔薇と和紅茶のティーバッグ -
 【電子レンジ対応】 エスカルゴ XLサイズ 12個入(殻付き/ガーリックバター入り)
【電子レンジ対応】 エスカルゴ XLサイズ 12個入(殻付き/ガーリックバター入り) -
 タスマニア産マスタード ホールシードタイプ
タスマニア産マスタード ホールシードタイプ -
 3種のチーズのキッシュ(タルトフロマージュサレ)
3種のチーズのキッシュ(タルトフロマージュサレ) -
 ふわもち食感 サンドイッチ チャバタ 130g×1個
ふわもち食感 サンドイッチ チャバタ 130g×1個 -
 カスタードクリームパイ 100g x 2個
カスタードクリームパイ 100g x 2個 -
 ブルターニュ産 クッキー(ガレット)3種アソート缶(オレンジフラワー)
ブルターニュ産 クッキー(ガレット)3種アソート缶(オレンジフラワー) -
 ブレス産 AOP発酵バター 250g
ブレス産 AOP発酵バター 250g -
 ブレス産 発酵バター ドゥミセル (加塩) 250g
ブレス産 発酵バター ドゥミセル (加塩) 250g -
 パテ ド カンパーニュ ブロック (田舎風豚のパテ) スタンダード
パテ ド カンパーニュ ブロック (田舎風豚のパテ) スタンダード -
 【送料込み】欧州パンとこだわりのバターを愉しむ欲張りセット
【送料込み】欧州パンとこだわりのバターを愉しむ欲張りセット -
 【サンプル セット】7種類のお食事パンお味見用セット
【サンプル セット】7種類のお食事パンお味見用セット
輸入者だから発生する「訳アリ」品? その1 |ダイニングプラスとは?

ダイニングプラスは輸入元直営のオンライン通販会社です。
ダイニングプラスと長年お付き合いをしてくださっているお客様からよくいただくお声として、
「アウトレットを活用しているよ!」というものがあります。
そうなんです。
ダイニングプラスには『アウトレット』が多いのです。。。
それを聞いて、どんなイメージをお持ちでしょうか?
そこで輸入元直営というのがキーワードになります。
>輸入元ならではの「アウトレット」はこちら

海外のメーカーで作られた製品は、それぞれ業務用のカートン(段ボールだったり、フィルムでぐるっと巻かれていたり…)に入れてパレットという板やプラスチック製の台に載せられ、大型のラップでぐるぐる巻きにされて出荷準備完了です。
メーカーの出荷口では、オーダーに合わせて、たいていの場合は10~20パレットの単位でコンテナに積み込んでからコンテナに封(シール)をします。シールと言っても紙のシールではなく、金属製の頑丈なもので、開封するには専用の機材を使い、一度開封したら元には戻せません。(昔は輸入の途上で中身が盗まれる、なんてことがたまにありましたが、最近は減りましたね~。)

例えば、ダイニングプラスでいちばん多く取り扱っているのはヨーロッパの食品ですが、
ヨーロッパから日本に船で輸入するためには40~45日の航海日数がかかります。長いですよね~
時折ニュースなどで大量のコンテナを積んだ船をみかけると、『うちの商品は載っているかな』なんて、気になります。
長い航海の間にはいろんな国に立ち寄ったり、時には積み替えも行われたりするのですから、
日本に到着して通関が切れるまでは気が気ではありません!
頑丈なシールがあるとはいえ、中で何が起こっているかはわからないので、到着すると中身を確認することが大切です。
日本で商品を楽しんでくださる方々にとって、輸入者はメーカーの代わりの役割も果たします。
だからこそ『大切に作られた商品がきちんと美味しい状態で届いているか?』を確かめるのが、お客様へ、そして作った人たちへの責任です。
輸送中に問題はなかったのか?
つぶれたものは入っていないか?
商品の状態は問題ないのか?
100%問題のない生産を目指すのは当たり前でも、
100%問題のない生産はあり得ないのが現状です。
だから検品をすると少しばかりの不良が発見されることが多いのです。
そんな不良をお客様に出すわけには行きません。とはいえ、大切に作られた食べ物であることも事実なので、不良疑いの製品はきちんと再検品をいたします。
日本のお客様は見た目の完成度にもこだわられますので、ヨーロッパではOKとして送られてきても、日本では通常商品としてはNGのものもたくさんあります。

ラベル不良、印字不良、箱つぶれ、焦げ、袋破れ、様々な不良があります。
それをひとつひとつ丁寧に検品しながら、安全に美味しく食べられるものとそうでないものに分けていきます。
まだ安全に美味しく食べられるものを捨てるのはもったいない!
だから検品を終えて出たそういう“訳あり”の製品をアウトレットとして販売しているのです。
皆さまも是非、そんな“訳あり”を活用して、お得に美味しくお取り寄せしてくださいね!
>輸入元ならではの「アウトレット」はこちら

<ダイニングプラスについて>
2001年事業開始、「dancyu」や「日経プラス1」など取材多数。一流プロ愛用の海外食品を1パックからお届けする通販です。商社直営。
-
 訳あり バゲット ルヴィノワーズ
訳あり バゲット ルヴィノワーズ -
 信州サーモン 冷燻仕立て
信州サーモン 冷燻仕立て -
 ブルターニュ産 クッキー(ガレット)3種アソート缶(オレンジフラワー)
ブルターニュ産 クッキー(ガレット)3種アソート缶(オレンジフラワー) -
 ブレス産 発酵バター ドゥミセル (加塩) 250g
ブレス産 発酵バター ドゥミセル (加塩) 250g -
 とろニシン レモンじめ 2フィレ(100g~160g)
とろニシン レモンじめ 2フィレ(100g~160g) -
 焼くだけ!ミニパンオショコラ 発酵バターが香るフランス産 Bake up生地 30g×6個入り
焼くだけ!ミニパンオショコラ 発酵バターが香るフランス産 Bake up生地 30g×6個入り -
 焼くだけ!大きなクロワッサン 発酵バターが香るフランス産 Bake up生地 60g×4個入り
焼くだけ!大きなクロワッサン 発酵バターが香るフランス産 Bake up生地 60g×4個入り -
 ミニ カヌレ 7個入り
ミニ カヌレ 7個入り -
 ハーフバゲット 140g×2個入り
ハーフバゲット 140g×2個入り -
 贅沢いちごジャム (プレザーブスタイル)
贅沢いちごジャム (プレザーブスタイル) -
 なめらか食感のブルーベリージャム (プレザーブスタイル)
なめらか食感のブルーベリージャム (プレザーブスタイル) -
 紫いちじくジャム
紫いちじくジャム -
 【送料込み】欧州パンとこだわりのバターを愉しむ欲張りセット
【送料込み】欧州パンとこだわりのバターを愉しむ欲張りセット -
 【送料無料】ベルデンソ 無ろ過EXVオリーブオイル 3本セット
【送料無料】ベルデンソ 無ろ過EXVオリーブオイル 3本セット -
 【送料込み】ヨーロッパ ちょい呑みセット
【送料込み】ヨーロッパ ちょい呑みセット
世界一の朝食(?)in Sydney|スタッフ海外体験記
何やら、ハリウッドスターが「世界一の朝食」と言ったことで一躍有名になったようです。
もちろんインターネット情報なので、眉唾ものだと思いつつ、そのお店に行ってみました。
タクシーの運転手さんにお店の名前を言っても「?」という感じだったので少し心配になりつつ、歩くと30分以上かかりそうだったのでそのまま乗って10分ほど。
そこはシドニーの中心部から少し郊外に行った住宅地にありました。

入ってみると白い壁に木目の床、全体的に明るい印象。 真ん中に大きなテーブルがあって、真ん中には大きなブーケ。
カラフルなお花というより、シンプルでかわいいお花で、お店の雰囲気にぴったり。
塩やコショウの容器やコップ、カトラリーに至るまで、シンプルながらこだわりを感じます。
地元の方々も入れ替わり来店していて、中には近くのオフィスで働いている風の若い人がコーヒーをテイクアウトしている姿も。お料理への期待も高まります。
届いた瞬間にすぐに人気の理由がわかる気がしました。
食いしん坊にはたまらない美味しそうなビジュアル。そして味も裏切りません。

スクランブルエッグはクリームを加えてふっくらつやつや。
ソーセージは発色剤を使わない無塩せきタイプが2種ついていて、どちらもしっかりした肉質で、ハーブの香りが効いています。
ベーコンは燻液につけたようなものではなく、ウッドチップでしっかりめにスモークをかけたタイプを厚切りでソテー。
間には小ぶりのシャンピニオンを丸ごとソテーにしたもの。
付け合せのほうれん草の葉っぱは少し苦めの味わいが力強いソーセージやベーコンに良く合い、もう一つの付け合せトマトは、中サイズの縦長トマトを半分に切って焼いてあるので味が凝縮していて、切ると出てくる果汁が全体に行きわたるとトマトソースのような効果が!!
そしてパン。
カンパーニュタイプです。石窯で焼いたのでしょう。打ち粉と一緒にきれいに焼けた底面までも美しい。
それを厚めにスライスして、焼いたのはフライパンかな?トースターかな?(たぶん、トースターでしょう。)
その上にバターが輪切りになって載せてあります。
とてもボリュームたっぷりなので、ランチやディナーとしても成立する満足感。
私なんかが言うのもおこがましいですが
ひとつひとつの素材がきちんと吟味してあって、それをきちんと調理してあるのです。
食いしん坊にはたまらない・・・♪
「世界一」かどうかはわかりませんが、素晴らしい朝食プレートでした。

ちなみに、ここはリコッタチーズを使ったパンケーキも有名だそうで・・・
当然食べてみました。
ふっくらしていて、ほんのり甘く、その上に載せられたメープルシロップ入りのバターがまた素晴らしい。
大満足の朝食、いや早めの夕食としていただきました。。。
帰りに歩いてみると静かな住宅地の間に、おしゃれなカフェバーや雑貨店、美容サロンなどが点在し、とても素敵なエリア。
あのお店がここで定着して地元に愛されている理由がわかったような気がしました。
<ダイニングプラスについて>
2001年事業開始、ミシュラン星付き店や日本を代表するホテルが愛用する食材を、どなたにも1パックからお届けする商社直営の通販です。「dancyu」や「日経プラス1」など取材多数。
-
 【まるで高級ホテル】な早起きが楽しみになる朝食セット
【まるで高級ホテル】な早起きが楽しみになる朝食セット -
 石窯焼き パン オ セーグル (ライ麦パン)
石窯焼き パン オ セーグル (ライ麦パン) -
 ハーブ香るブラートヴルスト ドイツ職人の絹引き焼きソーセージ
ハーブ香るブラートヴルスト ドイツ職人の絹引き焼きソーセージ -
 薔薇のつぼみ茶(ハマナスの花)
薔薇のつぼみ茶(ハマナスの花) -
 温泉塩の厚切りベーコン100g
温泉塩の厚切りベーコン100g -
 黒毛和牛のぜいたく霜降りローストビーフ
黒毛和牛のぜいたく霜降りローストビーフ -
 【電子レンジ対応】 エスカルゴ XLサイズ 12個入(殻付き/ガーリックバター入り)
【電子レンジ対応】 エスカルゴ XLサイズ 12個入(殻付き/ガーリックバター入り) -
 地中海風 野菜のキッシュ (タルトメディテラネ)
地中海風 野菜のキッシュ (タルトメディテラネ) -
 焼くだけ!クロワッサン 発酵バターが香るフランス産 Bake up生地 40g×5個入り
焼くだけ!クロワッサン 発酵バターが香るフランス産 Bake up生地 40g×5個入り -
 カヌレ ド ボルドー 60g×2個
カヌレ ド ボルドー 60g×2個 -
 りんごとカスタードのタルト 約21cm10カット フランス製 (タルトノルマンディー)
りんごとカスタードのタルト 約21cm10カット フランス製 (タルトノルマンディー) -
 ブレス産 発酵バター ドゥミセル (加塩) 250g
ブレス産 発酵バター ドゥミセル (加塩) 250g -
 パテ ド カンパーニュ ブロック (田舎風豚のパテ)オーセンティック
パテ ド カンパーニュ ブロック (田舎風豚のパテ)オーセンティック -
 【送料込み】欧州パンとこだわりのバターを愉しむ欲張りセット
【送料込み】欧州パンとこだわりのバターを愉しむ欲張りセット -
 【送料込み】ヨーロッパ ちょい呑みセット
【送料込み】ヨーロッパ ちょい呑みセット
幸せな朝食 in Amsterdam|スタッフ海外体験記
仕事の関係で主にヨーロッパのいろんな国を回りますが、朝食は意外とその国を知るきっかけにもなるものだと思うからです。
でも、時には近くのカフェに出かけて朝食をとりたくなる時もあります。
それは近所に素敵なカフェを見つけた時。朝食を出すカフェはたいてい早朝から営業しているので、前日に営業時間を確認しておくのです。
アムステルダムは毎年展示会で訪れる町ですが、カフェ文化が盛んです。
時間を問わず、素敵でカジュアルなカフェが多く、たいていメニューには美味しそうな軽食も載っています。
もちろんブランチ、ランチ、ディナー使いもOKなカフェですが、美味しい朝ごはんの魅力は万国共通なのでしょう。
人気店は朝からにぎわっているのです。
今回はそんな幸せ朝食のカフェに2日連続で行ってしまったお話しです。

ホテルから歩いて20歩ぐらいのところにそのカフェはありました。
ヨーロッパの人達が大好きなテラス席もあります。
行ったのは5月ですから朝はまだダウンジャケットが欲しくなる寒さです。なのでお店の中でいただくことにしました。

店内はカウンターになっていて好きなパンやドリンクを買って帰ることもできるようになっていて、その横には中二階に続く短い階段があります。
1日目はカウンターの手前にある席で外を眺めながらいただくことにしました。
セットメニューがいろいろあって、どれを選ぼうかとても悩みます。
悩んだあげく、いろいろ入ったセットにしてみました。
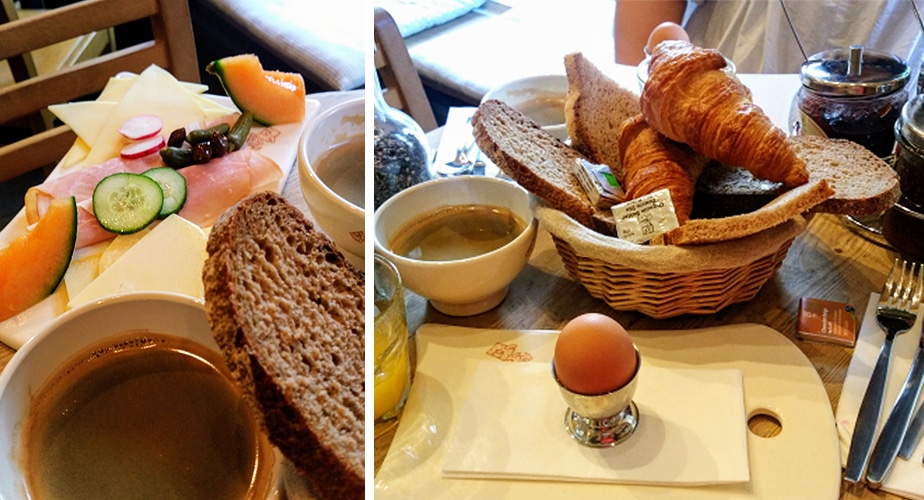
新鮮な半熟のゆで卵とオレンジジュースとコーヒー、クロワッサンやライ麦パンなどがもりもり入ったパンかご、そしてフルーツも一緒に盛られたコールドカットのプレート。
ここで重要なのがコーヒー。アムステルダムのコーヒーはアメリカンタイプでたっぷり出てきます。嬉しい。。。
オランダです。チーズはハードタイプでしっかり厚めのスライスが種類違いで3枚。
付け合せのピクルスも酸味がしっかりあってハムに良く合います。
大満足の朝食だったのですが、横目に他の人が食べているプレートを見て、心の中で「あれが食べたい・・・」
そして2日目
一晩経ってもその横目に見たプレートが忘れられず、行ってまいりました!
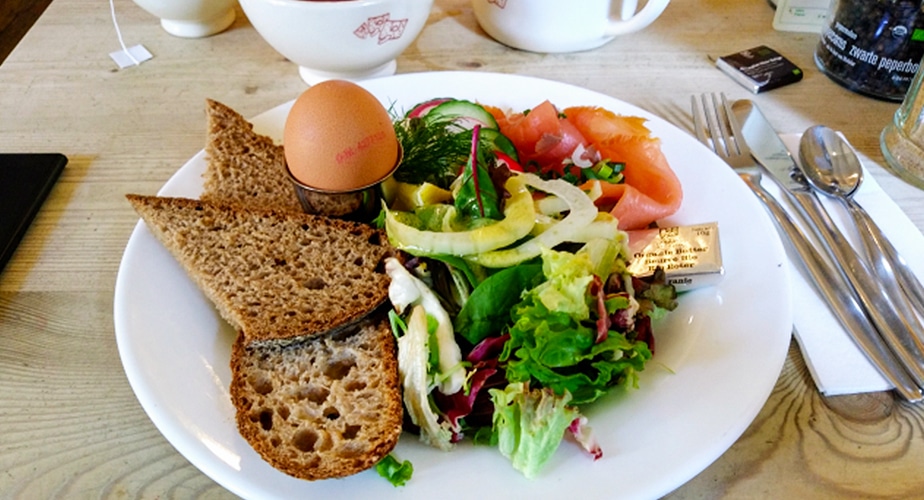
サラダたっぷりのスモークサーモンと卵の朝食プレートです!
そうでした、ヨーロッパでも北海に面する国であるオランダはニシンやサーモンも美味しいんです!
たっぷりサラダには日本ではあまり見かけないフヌイユ(フェンネル)の葉と茎(根に近い膨らんだところ)が入っています。
レモンの効いた上品なドレッシングで、きれいに全体を和えてあって、「やっぱりこのお店、間違いない」と心の中で小躍りしました。
そのレモン味のサラダにねっとりと濃厚なスモークサーモンが合わないはずがない!
そして卵は前日と同じく半熟で、バターを塗ったライ麦パンをとろりとした卵黄部分に付けてみたり、ほんのり酸味のあるパンとサーモンと合わせてみたり。
ちなみにこの日は紅茶を選びましたが、それはティーパックでした。「ここはロンドンではなかった。。。」
でも嬉しいのは一緒に持ってきてくれたたっぷりのお湯とチョコレート。
2日連続の幸せな朝食でした。
<ダイニングプラスについて>
2001年事業開始、「dancyu」や「日経プラス1」など、メディア紹介多数。こだわりプロ愛用の美味しい海外食品を1パックからお届けする食品通販です。商社直営。
-
 【まるで高級ホテル】な早起きが楽しみになる朝食セット
【まるで高級ホテル】な早起きが楽しみになる朝食セット -
石窯焼き風 ライ麦パン(パン・オ・セーグル)
-
 ブレス産 AOP発酵バター 250g
ブレス産 AOP発酵バター 250g -
 ブレス産 発酵バター ドゥミセル (加塩) 250g
ブレス産 発酵バター ドゥミセル (加塩) 250g -
 薔薇と和紅茶のティーバッグ
薔薇と和紅茶のティーバッグ -
 黒毛和牛のぜいたく霜降りローストビーフ
黒毛和牛のぜいたく霜降りローストビーフ -
 信州サーモン 冷燻仕立て
信州サーモン 冷燻仕立て -
 肉厚の旨味 大粒ほたて貝(青森産 黄金ほたて) Lサイズ
肉厚の旨味 大粒ほたて貝(青森産 黄金ほたて) Lサイズ -
 焼くだけ!クロワッサン 発酵バターが香るフランス産 Bake up生地 40g×5個入り
焼くだけ!クロワッサン 発酵バターが香るフランス産 Bake up生地 40g×5個入り -
 りんごとカスタードのタルト 約21cm10カット フランス製 (タルトノルマンディー)
りんごとカスタードのタルト 約21cm10カット フランス製 (タルトノルマンディー) -
 フランス産 マカロン レッドフルーツ アソート 12個 (4種×各3個)
フランス産 マカロン レッドフルーツ アソート 12個 (4種×各3個) -
石窯焼き風 田舎風パン (パン ド カンパーニュ )
-
 フランス伝統生ハム IGP ジャンボン ド バイヨンヌ 200g
フランス伝統生ハム IGP ジャンボン ド バイヨンヌ 200g -
 TETSUYA'S タスマニア産 ソフトスモーク オーシャン トラウト 200g
TETSUYA'S タスマニア産 ソフトスモーク オーシャン トラウト 200g -
 【送料込み】欧州パンとこだわりのバターを愉しむ欲張りセット
【送料込み】欧州パンとこだわりのバターを愉しむ欲張りセット
エトレバター|上野万梨子さんのフランス生産者訪問レポート

数年前のこと、東京で企画したフランスバターの試食勉強会準備中に、私自身初めて知ったのがブレス産、エトレのバターでした。
フランス中のバターが集まるパリのスーパーでもまったく見かけたことがなかったバター。
フランスのAOP認定バターの二大産地と思っていた西のノルマンディーや、ボルドーの北に位置するポワトゥー・シャラントの他に、東のローヌ・アルプ地方にもこの認定を受けた優秀なバターの産地があったのでした。
フランスで3地域しかない価値あるAOP認定ながら、フランスのみならず、世界中の優れた食材が集まるパリで一般の消費者の目にはつかない希少なバター。
それはどんな環境の中で作られているのでしょう。

ブレスはAOP認定の鶏や七面鳥の産地として名高い地方。
バターを産するエトレ村は、ローヌ・アルプ地域圏アン県の県庁所在地、ブル・カン・ブレスから北に車で30分ほどのところにあり、そこから北東方向のフランシュ・コンテ、北西のブルゴーニュ双方の南に位置する、一面にのどかな牧場が広がる小さな村です。
工場から40キロ圏内にある60の農家から朝夕二回集められた生乳は直ちに製造工程に回され、ストックされた冷蔵乳や冷凍乳を混ぜていない最高品質バター、Beurre extra fin のみを生産しています。
使われるのは、フランシュ・コンテが産する、フランスでも日本でもおそらく一番人気のチーズ、コンテに主に使われるものと同じ、モンペリアルド種の牛の乳です。

(生後数週間のモンペリアルド種の仔牛です。大切に育てられ、このあと2年半ほどで初めて乳が取れるようになります。)

搾りたての牛乳はまず低温殺菌され、そこから分離させたクレーム(クリーム)には発酵を促すための乳酸菌が添加され、タンクの中で熟成させます。
この間に乳酸発酵のアロマと程よい酸味が生まれるわけですが、この工程はバターの風味を決める上で最も重要とされ、Maitre beurrier バターマイスターの管理のもとで温度、時間ともに厳密に管理されて行われます。
私たち日本人が食べ慣れているバターに比べて、フランスバターをより美味しいと感じるのは、このクレーム(クリーム)の発酵のさせ方によるところが大きいのです。
作り手によってバターの風味が異なるのは、原料乳自体の違いを除けば、この発酵段階が決めてといってよいでしょう。

この発酵クレーム(クリーム)は次いで撹拌器にかけられ、脂肪分と水分(バターミルク)に分離させます。
水はタンクの外に排出され、ほぼ水分が出切ったころ、脂肪は細かな黄色い粒状態になります。
すると、それまで水分を外に捨てていたタンクにあらためて冷水を流し込んで洗いの工程に入ります。
こうすることで、粒状態になったバターにまだ残っていた水分が、新たに加えられた水が呼び水となることで外に出てくるというわけです。
この洗いを三回繰り返し、最後に練り上げて、バターが完成します。
こうして大きな撹拌器で一度に作る量は増えても、昔ながら、農家が木桶を手で回して撹拌し、少量生産してきた手作りバターと全く同じ工程を経て出来上がるエトレのバター。
生乳をCanon 大砲と呼ばれる機械にかければものの数分でバターが出来上がる、完全オートメーション製造が主流の時代にあって今も残る、貴重な手作りバターといえるでしょう。

希少バターということで、小さな工場であろうとは想像していましたが、一度に600キロのバターができる撹拌器は一つ、その前で働く人は2~3人。工場というと機械任せのイメージですが、エトレの場合はアトリエと言うにふさわしいほどの、そこは人の目と感覚が決め手の職人仕事の場だったのでした。
工場のヤンさんの言葉が印象的です。
「今、私たちは、これまでより食事の量を減らし、そのかわり質の良いもので満たされたいと思うようになっている」と。
そのような時代にあって、ますます価値が高まるのがエトレのようなアルチザン、職人仕事であるのは間違えありません。
そして私が付け加えたいのは、より良い素材を使えば、調理はよりシンプルに、料理にかかる時間は短縮できるということです。
調理時間が短くなれば、水道ガス電気などのエネルギー資源も確実に節約できるでしょう。エトレバターのように自然環境に配慮して生まれた製品を受け取り、消費する側として、心に留めておきたいことではないでしょうか。

できたてのバターはタンポポの花のように春めいた黄色。 ほのかな甘みとノワゼット(ヘーゼルナッツ)を思わせる風味、そして空気を含んだような口当たりの軽さも魅力的です。 これはやはり、いきなり炒め物などの調理に使わずに、まずはシンプルにパンに、ぬるのではなく、塊をのせて、バター自体を食べて味わっていただくのが一番でしょう。
文・上野万梨子さん
(※当ブログ内容は、2019年12月時点での情報内容になります。)
<ダイニングプラスについて>
2001年事業開始、「dancyu」や「日経プラス1」など、メディア紹介多数。こだわりプロ愛用の美味しい海外食品を1パックからお届けする食品通販です。商社直営。
-
 ブレス産 AOP発酵バター 250g
ブレス産 AOP発酵バター 250g -
 ブレス産 発酵バター ドゥミセル (加塩) 250g
ブレス産 発酵バター ドゥミセル (加塩) 250g -
 薔薇と和紅茶のティーバッグ
薔薇と和紅茶のティーバッグ -
 2種チーズのバスクチーズケーキ
2種チーズのバスクチーズケーキ -
 肉厚の旨味 大粒ほたて貝(青森産 黄金ほたて) Lサイズ (1㎏)
肉厚の旨味 大粒ほたて貝(青森産 黄金ほたて) Lサイズ (1㎏) -
 ビーフ100% ひき肉ステーキ(ステークアッシェ) 100g×2
ビーフ100% ひき肉ステーキ(ステークアッシェ) 100g×2 -
 焼くだけ!ミニパンオショコラ 発酵バターが香るフランス産 Bake up生地 30g×6個入り
焼くだけ!ミニパンオショコラ 発酵バターが香るフランス産 Bake up生地 30g×6個入り -
 焼くだけ!大きなクロワッサン 発酵バターが香るフランス産 Bake up生地 60g×4個入り
焼くだけ!大きなクロワッサン 発酵バターが香るフランス産 Bake up生地 60g×4個入り -
 ブルターニュ産 クッキー(ガレット)3種アソート缶(ヴァイオレットフラワー)
ブルターニュ産 クッキー(ガレット)3種アソート缶(ヴァイオレットフラワー) -
石窯焼き パン オ セーグル (ライ麦パン)
-
 なめらか食感のブルーベリージャム (プレザーブスタイル)
なめらか食感のブルーベリージャム (プレザーブスタイル) -
 メルゲーズ ムートン 生ソーセージ 400g (国内加工)
メルゲーズ ムートン 生ソーセージ 400g (国内加工) -
 【送料込み】欧州パンとこだわりのバターを愉しむ欲張りセット
【送料込み】欧州パンとこだわりのバターを愉しむ欲張りセット -
 【サンプル セット】7種類のお食事パンお味見用セット
【サンプル セット】7種類のお食事パンお味見用セット -
 【送料込み】ヨーロッパ ちょい呑みセット
【送料込み】ヨーロッパ ちょい呑みセット
シャルキュトリの宝庫、リヨンで食べました、珍味度★5のアレ!|スタッフ海外体験記
シャルキュトリの宝庫、リヨンで食べました、珍味度★5のアレ!
アンドゥイエットとブーダンノワール
フランス中部のリヨンというと、昔から美食の町として有名ですよね。
そういえば、子供の頃に初めて連れて行ってもらった本格的なフランス料理店の名前もリヨンでした。
その頃はそれが町の名前だということすら知らなかったのですが・・・
>フランス伝統のシャルキュトリ「ブーダンノワール」はこちら

リヨンの中央駅の近くにある市場は別名、ポールボキューズ市場とも呼ばれ、リヨンを美食の町として世界に知らしめたかの有名な料理人の名前を冠しています。
規模こそ、大きくないものの、魚、肉、チーズ、お菓子、ワイン、となんでも揃う楽しい空間です。

中でも肉売り場には、様々な種類の生肉に加え、その売場の半分以上も占めるのは様々なシャルキュトリです。
サラミや生ハム、ソーセージなど、その品揃えは圧巻!
とりわけリヨンらしいのはアンドゥイエットやブーダンではないでしょうか。
アンドゥイエットは豚の内臓のいろんな部位を腸詰にしたもの、ブーダンノワールは豚の血を使ったソーセージ。
どちらもダイニングプラスでも販売しておりますが、何しろ、特殊な商品で、「珍味」という言葉がぴったりです。
そのため、シャルキュトリ系の商品の一部をわかりやすく表現するために、「珍味度」という言葉を使い、★の数で表しております。
(★が多いほど珍味度が高い・・・)
フランスの食に詳しい方々は当然ご存知の珍味なので、その容赦ない本場度には間違いなく自信があります。
とはいえ、知らない方にとってはどんなものなのか、想像がつきませんよね?
そこで!
リヨンのポールボキューズ市場での実食レポートです!
市場の中には簡単に食事ができるスペースもあって、お昼時ともなれば近くのサラリーマン風の人たちで混み合います。それらの一角に席を取り、メニューを見ると、その日の定食メニューに交じって、あるではないですか!

「リヨン珍味の盛り合わせ」
アンドゥイエットとブーダンノワールがたっぷりのじゃがいもと一緒にアツアツの鉄板に載って、マスタードクリームソースがたっぷり!
どちらもダイニングプラスで販売しているサイズの1本を半分に切った状態でこんがり焼かれています。
 アンドゥイエットはこんがりと焼かれたものを少しずつ切り分けます。
アンドゥイエットはこんがりと焼かれたものを少しずつ切り分けます。
そのとき、アンドゥイエットは中身がほろりとこぼれ出るのですが、それをフォークですくってソースと一緒に口に運ぶのです。
すると・・・マスタードの程よい酸味がクリーミーに絡まって、大変美味!臭みなんて全くなくてワインが進む♪
ちなみに、この時合わせたのはボジョレー(ヌーボーではなく)の赤ワイン。

そしてブーダンノワール。。。
実はこの下にたっぷり敷かれていたのは焼きリンゴ。皮を剥いて串切りにしたリンゴは、とろっとなる一歩手前、わずかに食感が残る程度に焼かれ、ブーダンの下に潜ませてあったのです。
ブーダンノワールを切った時に気づいて一緒に食べたら、これが美味!
ブーダンノワールは一般的なパリッと肉肉しいタイプのヨーロッパのソーセージとは違ってふんわりした中身が特徴。
どちらかというと、こんがり焼かれた皮よりもその中身を焼いたリンゴに絡めて食べるイメージです。
このフォークに載ったブーダンノワールにもクリームが一緒に絡まって、しっとりと何と美味しいことでしょう。
実は注文する前は「勉強、勉強」と言い聞かせていたのですが、食べ始めると夢中になってあっという間に完食したのでした。
>フランス伝統のシャルキュトリ「ブーダンノワール」はこちら
<ダイニングプラスについて>
2001年事業開始、「dancyu」や「日経プラス1」など、メディア紹介多数。こだわりプロ愛用の美味しい海外食品を1パックからお届けする食品通販です。商社直営。
-
 フランス産 生ソーセージ シポラタ 500g (50g×10本)
フランス産 生ソーセージ シポラタ 500g (50g×10本) -
 メルゲーズ ムートン 生ソーセージ 400g (国内加工)
メルゲーズ ムートン 生ソーセージ 400g (国内加工) -
 ブーダン ノワール 470g (豚の血と脂の腸詰)
ブーダン ノワール 470g (豚の血と脂の腸詰) -
 パテ ド カンパーニュ ブロック (田舎風豚のパテ) スタンダード
パテ ド カンパーニュ ブロック (田舎風豚のパテ) スタンダード -
 薔薇の花びら茶
薔薇の花びら茶 -
 なめらか食感のすりおろしリンゴ 200g
なめらか食感のすりおろしリンゴ 200g -
 【電子レンジ対応】 エスカルゴ XLサイズ 12個入(殻付き/ガーリックバター入り)
【電子レンジ対応】 エスカルゴ XLサイズ 12個入(殻付き/ガーリックバター入り) -
 とろニシン レモンじめ 2フィレ(100g~160g)
とろニシン レモンじめ 2フィレ(100g~160g) -
 タスマニア産マスタード ホールシードタイプ
タスマニア産マスタード ホールシードタイプ -
 カヌレ ド ボルドー 60g×2個
カヌレ ド ボルドー 60g×2個 -
 りんごとカスタードのタルト 約21cm10カット フランス製 (タルトノルマンディー)
りんごとカスタードのタルト 約21cm10カット フランス製 (タルトノルマンディー) -
 スペイン チュロス (シナモンシュガー付き)
スペイン チュロス (シナモンシュガー付き) -
 【送料込み】欧州パンとこだわりのバターを愉しむ欲張りセット
【送料込み】欧州パンとこだわりのバターを愉しむ欲張りセット -
 【送料込み】ヨーロッパ ちょい呑みセット
【送料込み】ヨーロッパ ちょい呑みセット -
 【送料込み】週末ご褒美プチセット
【送料込み】週末ご褒美プチセット
ドイツのB級グルメ代表!カリーヴルスト|スタッフ海外体験記
ドイツのB級グルメ代表!カリーヴルスト
ドイツと言えば、ビールとソーセージを思い浮かべますよね。
ソーセージの中でもベルリンが発祥と言われるカリーヴルストは、今やドイツ全国で楽しめるB級グルメ。
その存在は、まさに大阪のたこ焼きのよう。
ちょっとした街角や駅の構内にもたこ焼き・・・いえ、カリーヴルストのスタンドが。
先日も、デュッセルドルフの鉄道駅の構内で発見!
>長さ20センチ!カリーヴルストにもぴったりのドイツソーセージはこちら
>万能調味料!ジューシーなカリーヴルスト用カレーソースはこちら

ドイツの駅は切符がなくても駅の構内をウロウロできて、中にはサンドイッチ屋さん、スーパー、本屋さんなど、
たくさんのお買い物スペースがあります。
この日はちょうど雨の日曜日。
せっかくなので、最近、駅の近くにオープンしたという大型スーパーに行ったら、日曜日はなんと休み!
日本では考えられない!と一人ぶつぶつ文句を言いながら、仕方ないので駅の方へ。
夕方の駅の中は用事を済ませて帰ってきた人や、観光客などでごった返しています。
そんな中、ちょっと昔風に見えるカリーヴルストのスタンドがスタイリッシュなパン屋さんの隣にありました!
しかも結構繁盛しています!
お買い物帰り風の女性の一人客。親子とみられる二人連れ。家で楽しもうと持ち帰りの車椅子の男性。
旅行中らしい英語を話す女性3人。そして私。
メニューはソーセージだけで、全部にパンが付きます。

手前の鉄板では2種類のソーセージがジュウジュウと香ばしく焼かれ、奥のオーブンではプチパンが焼かれています。
一番人気はやはり、カリーヴルスト。
専用のマシンの穴にソーセージを入れると、きれいにカットされて下から出てくる。それを耐油加工された紙皿で受ける。
そこにたっぷりのカリーソースとカレー粉をふりかけてフォークを刺したら、ペーパーでつかんだパンと共に『はい』と手渡し。

スタンドの横は台になっていて、そこで食べるシステム。
甘いケチャップ味のカレーソースとカレー粉に優しい味のソーセージたっぷりつけて、時折ちぎったパンをカレーソースに絡めて食べる。
>長さ20センチ!カリーヴルストにもぴったりのドイツソーセージはこちら
>万能調味料!フルーティーなドイツ産カリーヴルスト用カレーソース

買っていく人々、駅を通る人々の様子を見ながら食べるカリーヴルストは温かくお腹を満たすと共に旅の思い出ともなるのでした。
<ダイニングプラスについて>
2001年事業開始、「dancyu」や「日経プラス1」など、メディア紹介多数。こだわりプロ愛用の美味しい海外食品を1パックからお届けする食品通販です。商社直営。
-
 ロングブラートヴルスト ドイツ職人のスモーク焼きソーセージ
ロングブラートヴルスト ドイツ職人のスモーク焼きソーセージ -
 ハーブ香るブラートヴルスト ドイツ職人の絹引き焼きソーセージ
ハーブ香るブラートヴルスト ドイツ職人の絹引き焼きソーセージ -
 シンケンクナッカー ドイツ職人のスモークソーセージ
シンケンクナッカー ドイツ職人のスモークソーセージ -
 ふわもち食感 サンドイッチ チャバタ 130g×1個
ふわもち食感 サンドイッチ チャバタ 130g×1個 -
 2.4kg テルエルポーク 肩ロース ブロック
2.4kg テルエルポーク 肩ロース ブロック -
 エキストラホット グルメソース カレー(カレーケチャップ辛口)
エキストラホット グルメソース カレー(カレーケチャップ辛口) -
 ドイツ伝統の味 グルメソースカレー(カリーヴルスト専用ソース)
ドイツ伝統の味 グルメソースカレー(カリーヴルスト専用ソース) -
 タスマニア産マスタード ホールシードタイプ
タスマニア産マスタード ホールシードタイプ -
 ベーコンとチーズのキッシュ(キッシュ ロレーヌ)
ベーコンとチーズのキッシュ(キッシュ ロレーヌ) -
 スティック プレッツェル 70g×2個入り
スティック プレッツェル 70g×2個入り -
バタープレッツェル 79g×2個入り
-
 ブレス産 発酵バター ドゥミセル (加塩) 250g
ブレス産 発酵バター ドゥミセル (加塩) 250g -
 【送料込み】欧州パンとこだわりのバターを愉しむ欲張りセット
【送料込み】欧州パンとこだわりのバターを愉しむ欲張りセット -
 ドイツ職人シリーズ 4種のソーセージ
ドイツ職人シリーズ 4種のソーセージ -
 【送料込み】ヨーロッパ ちょい呑みセット
【送料込み】ヨーロッパ ちょい呑みセット
フランスの朝は機内でもショコラショー|スタッフ海外体験記
フランスの朝食と言えば、クロワッサンとカフェオレ・・・
そんなイメージを持つ方も多いのでは?
先日乗ったエールフランスの朝のフライトで、期待どおりにクロワッサンが出てきました。

>バター100%の幸せ!簡単に焼きたてのおいしさ フランス産クロワッサン(冷凍パン)
片側3席の窓側に座っていた私に「欲しかったら取って」とばかりにさしだされたのは、
プラスチックのかごに山盛りにされたクロワッサン。
上に乗ったペーパーナフキンを使って意外と大きいクロワッサンをひとつ。
ダイニングプラスでも販売しているクロワッサンはバターがリッチに香って焼き立ての幸福感が・・・♪
などという夢のような美味しさではありませんでしたが、
エールフランスで食べるクロワッサンはそれなりの夢があるなぁ、と感じながら・・・
大切なのはそれに合わせる飲み物!
回りを見ると・・・
コーヒーと並んで人気はやはりショコラショー!
平日朝のフライトはサラリーマンがほとんどです。
男性、女性、20代~50代、いろんなサラリーマン風の方々がスーツを着て注文するショコラショー♪
ショコラショーはいわゆるココアのことですが、甘いだけではない、カカオのほろ苦さも備えたココアには
チョコレートを愛するヨーロッパの人たちの文化を感じます。
だったら私もショコラショー!
「ショコラショー スィルヴプレ?(ホットココアお願いします?)」
「ビアンシュール!(もちろん!)」
程よい甘みとカカオの香りが湯気と共に立ち上り、冷たいクロワッサンを噛みしめながら、
時にはココアに浸しながら、幸せな朝食となりました。
>バター100%の幸せ!簡単に焼きたてのおいしさ フランス産クロワッサン(冷凍パン)
<ダイニングプラスについて>
2001年事業開始、「dancyu」や「日経プラス1」など、メディア紹介多数。こだわりプロ愛用の美味しい海外食品を1パックからお届けする食品通販です。商社直営。
-
 ココア専門メーカーのこだわりココア (スプレードライ製法)
ココア専門メーカーのこだわりココア (スプレードライ製法) -
 焼くだけ!ミニクロワッサン 発酵バターが香るフランス産 bake up生地 25g x8個入り
焼くだけ!ミニクロワッサン 発酵バターが香るフランス産 bake up生地 25g x8個入り -
 焼くだけ!クロワッサン 発酵バターが香るフランス産 Bake up生地 40g×5個入り
焼くだけ!クロワッサン 発酵バターが香るフランス産 Bake up生地 40g×5個入り -
 焼くだけ!大きなクロワッサン 発酵バターが香るフランス産 Bake up生地 60g×4個入り
焼くだけ!大きなクロワッサン 発酵バターが香るフランス産 Bake up生地 60g×4個入り -
 薔薇の花びら茶
薔薇の花びら茶 -
 2種チーズのバスクチーズケーキ
2種チーズのバスクチーズケーキ -
 3種のチーズのキッシュ(タルトフロマージュサレ)
3種のチーズのキッシュ(タルトフロマージュサレ) -
 6種のベリー 北欧カフェデニッシュ 2個入
6種のベリー 北欧カフェデニッシュ 2個入 -
 三角 プレッツェル 85g×2
三角 プレッツェル 85g×2 -
 贅沢いちごジャム (プレザーブスタイル)
贅沢いちごジャム (プレザーブスタイル) -
 モデナ産 バルサミコ酢 IGP 5グレープ 250ml (オリタリアブランド)
モデナ産 バルサミコ酢 IGP 5グレープ 250ml (オリタリアブランド) -
 ブレス産 発酵バター ドゥミセル (加塩) 250g
ブレス産 発酵バター ドゥミセル (加塩) 250g -
 フランス伝統生ハム IGP ジャンボン ド バイヨンヌ 200g
フランス伝統生ハム IGP ジャンボン ド バイヨンヌ 200g -
 【送料込み】欧州パンとこだわりのバターを愉しむ欲張りセット
【送料込み】欧州パンとこだわりのバターを愉しむ欲張りセット -
 【サンプル セット】12種類のデニッシュ&パイお味見用セット
【サンプル セット】12種類のデニッシュ&パイお味見用セット
ハモンセラーノは他の生ハムとどう違うのか?特徴や食べ方、保存方法をご紹介

ハモンセラーノは、日本でも人気のあるスペイン産の生ハムです。生ハムの世界的な産地として特に知られているのはスペインとイタリアですが、ハモンセラーノはスペイン産の生ハムでもっとも知名度が高い銘柄の1つといってよいでしょう。
おそらくその名前を1度は聞いたことのある方も多いでしょうが、ハモンセラーノとはどのような特徴を持った生ハムなのでしょうか。また、ハモンイベリコや、プロシュートなどの他の生ハムとどのように異なっているのでしょう。この記事では、スペインを代表する生ハム・ハモンセラーノの特徴や作り方などについてご紹介します。
【ハモンセラーノとは】

スペインは元々、世界一の生ハム生産量を誇る国ですが、その生産量の9割ほどをハモンセラーノが占めています。名前の由来ですがハモンは「ハム」を意味し、セラーノは「山の」という意味の言葉です。つまり「山のハム」という名称になりますが、その名の通りスペインのなかでも、山岳地域でさかんに作られていることからこの名前が付けられたといわれています。
ハモンセラーノのおもな産地であるスペインの山沿いでも、特にトレベレスとテルエルで作られたものは「ハモン・デ・テルエル」「ハモン・デ・トレベレス」と呼ばれます。これらの銘柄は、ハモンセラーノのなかでも一級品とされています。
テルエル産のハモンセラーノは「原産地呼称制度(DO)」認定を、トレベレス産は「EU地理的表示保護指定(PGI)」の認可をそれぞれ受けています。つまり、それらを名乗るにふさわしい高品質が保証されているということですね。
ハモンセラーノは、イタリア・パルマ産の「プロシュート・ディ・パルマ」、中国の「金華火腿(きんかかたい・金華ハム)」とともに、世界三大生ハムとして称されることでも知られています。
>世界三大生ハムのひとつ 「ハモンセラーノ」はこちら
1. ハモンセラーノの製法
ハモンセラーノの製法には特徴があり、豚の後ろ脚の皮の一部をはぎ取ってから塩漬けした後、乾燥・熟成します。皮をはいでから塩に漬けることで、特徴ある味わいが生まれるそう。
ハモンセラーノの熟成期間は36週(9か月)程度といわれていますが、50か月も熟成されるものもあるなど、製品それぞれで熟成期間の幅が広い点も特徴です。
2. ハモンセラーノの味
先に述べた通り、ハモンセラーノは皮をはいでから塩漬けするため、しっかりとした塩味が付いています。この製法を用いることで肉の水分が早く抜けるため、肉の味が凝縮されてコクのある味わいになります。
また、プロシュートなどよりやや硬い食感で食べ応えがある点も特徴。熟成期間が長くなるほど肉の風味が抑えられ、香り高い味わいを生み出します。
>肉の旨みが凝縮した世界三大生ハム 「ハモンセラーノ」はこちら
【他の生ハムとの違い】

先ほどご紹介した「世界三大生ハム」をはじめ、世界の生ハムにはさまざまな種類があります。他の有名な生ハムとハモンセラーノには、どのような違いがあるのでしょうか。
ここでは、世界三大生ハムの1つである「プロシュート」と、同じくスペイン産生ハムである「ハモンイベリコ」を例に挙げ、両者との違いについてご紹介します。
1. ハモンセラーノとプロシュートはどう違うのか
スペイン産生ハムのハモンセラーノは、先にご紹介した通り皮の一部をはいでから塩漬けするのが特徴です。その一方で、イタリア産生ハムであるプロシュート(プロシュット)は、皮を残したまま塩漬けしています。
肉の味わいやコクを強く感じられるハモンセラーノに対し、プロシュートはしっとりとした食感に仕上がり、適度な塩味が付いているという味・食感の違いがあります。
<プロシュートについてはこちら>
2. 同じスペイン産生ハムでも違いがある
ハモンセラーノとハモンイベリコは、どちらも同じスペイン産の生ハムです。ハモンセラーノはおもに白豚の後ろ脚を使用していますが、ハモンイベリコはイベリコ豚の後ろ脚を使用します。まず原材料となる豚肉の種類が、大きな違いとなっています。
ハモンセラーノの原料になる白豚は、基本的に豚舎で育てられる豚です。その一方、ハモンイベリコの原料となる豚はおもに放牧豚です。イベリコ豚は放牧によって育てられ、ドングリなどをエサとすることも多いため、肉自体に濃厚なコクと甘みがある点が特徴です。
ハモンセラーノとハモンイベリコでは原料となる豚に違いがあるため、スペインでは種別が判別しやすいように蹄が付いたままの状態のブロック(原木)が流通しています。
【ハモンセラーノの美味しい食べ方】

ハモンセラーノは濃厚なコクとうま味がポイントですから、そのままスライスして食べるのが何といってもおすすめです。塩味が効いているため、同じスペイン産の赤ワインやチーズ、パンなどと合わせるとさらに美味しくいただけます。
ハモンセラーノを食べる際には、冷えたままではなく常温で少し戻してから食べると、脂が溶けやすくなり味や香りを口の中でしっかりと感じられます。
>スペイン伝統の味「ハモンセラーノ」はこちら
【生ハムの保存方法】

スライスされ、パック詰めされた製品の場合、残ったものはラップに包むなどして、できるだけ空気に触れないよう気を付けながら冷蔵庫で保存するのがおすすめです。加工肉とはいえ生ハムだけに、空気に触れると酸化や乾燥が進んで味が落ちてしまいます。
原木(ブロック)の製品の場合は、脂やオリーブオイルを垂らしたキッチンペーパーなどでハムの切り口を覆って乾燥しないようにし、直射日光などの当たらない所で常温保管します。
ただし、この方法で保存する場合でも、開封後1週間を目安に食べきるようにしましょう。
【生ハムは種類によって特徴が異なる】

生ハムは生産国や産地・製法などによって、味や食感といった特徴がそれぞれ異なる奥の深い食材です。さまざまな生ハムを食べ比べることで、ご自身の味覚や食べ方にぴったりの生ハムを見つけられるかもしれません。
今回ご紹介したハモンセラーノをはじめ、さまざまな銘柄の生ハムを味わってみて、自分好みの銘柄や食べ方を見つけられればさらに面白いかもしれません。
<ダイニングプラスについて>
2001年事業開始、「dancyu」や「日経プラス1」など、メディア紹介多数。こだわりプロ愛用の美味しい海外食品を1パックからお届けする食品通販です。商社直営。
-
 ハモンセラーノ (200gパック)
ハモンセラーノ (200gパック) -
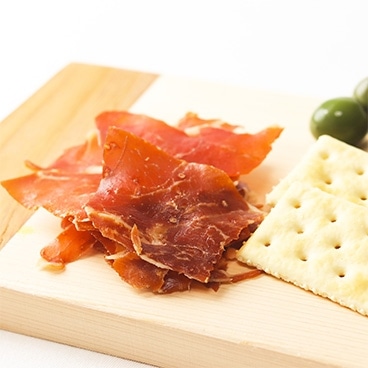 新食感!旨み凝縮生ハムジャーキー 30g
新食感!旨み凝縮生ハムジャーキー 30g -
 生ハム切り落とし ボリュームパック スペイン産
生ハム切り落とし ボリュームパック スペイン産 -
 フランス伝統生ハム IGP ジャンボン ド バイヨンヌ 200g
フランス伝統生ハム IGP ジャンボン ド バイヨンヌ 200g -
 【ジップパック】 ミニ ダイスカット 生ハム 150g
【ジップパック】 ミニ ダイスカット 生ハム 150g -
 本場スペインのとろけるバスクチーズケーキ
本場スペインのとろけるバスクチーズケーキ -
 2.4kg テルエルポーク 肩ロース ブロック
2.4kg テルエルポーク 肩ロース ブロック -
 3種のチーズのキッシュ(タルトフロマージュサレ)
3種のチーズのキッシュ(タルトフロマージュサレ) -
 ふわもち食感 サンドイッチ チャバタ 130g×1個
ふわもち食感 サンドイッチ チャバタ 130g×1個 -
 フランス産 マカロン レッドフルーツ アソート 12個 (4種×各3個)
フランス産 マカロン レッドフルーツ アソート 12個 (4種×各3個) -
石窯焼き風 ライ麦パン(パン・オ・セーグル)
-
バタープレッツェル 79g×2個入り
-
 箱入り薪窯ピザ 4チーズ 200g
箱入り薪窯ピザ 4チーズ 200g -
 【送料込み】欧州パンとこだわりのバターを愉しむ欲張りセット
【送料込み】欧州パンとこだわりのバターを愉しむ欲張りセット -
 【送料無料】ベルデンソ 無ろ過EXVオリーブオイル 3本セット
【送料無料】ベルデンソ 無ろ過EXVオリーブオイル 3本セット
エキストラバージンオリーブオイルとは?オリーブオイルとの違いや効果を解説

パスタやピッツァ、アヒージョなどさまざまな料理で使用されている油といえば、オリーブオイルです。長らく人々の食生活において親しまれてきたオリーブオイルですが、近年は健康や美容にも効果が期待できるとされ、さらに人気が高まっています。
この記事では、そんなオリーブオイルのなかでも最高品質とされる「エキストラバージンオリーブオイル」について、くわしくご紹介します。
1-1 オリーブオイルの等級
1-2 ピュアオリーブオイルとは?
1-3 日本のエキストラバージンオリーブオイルは偽物が多い?
2 おすすめの使い方
【エキストラバージンとピュアの違い】

日本の一般的なスーパーなどで市販されているオリーブオイルには、「オリーブオイル(ピュアオリーブオイル)」と「エキストラバージンオリーブオイル」の2種類があります。一見同じオリーブオイルに見えるこれら2つには、どのような違いがあるのでしょうか。
ここでは、「エキストラバージンオリーブオイル」とはどのようなものなのかについて、ご紹介します。
>オリーブ果実「生搾り」 無ろ過(ノンフィルター)エキストラバージンオリーブオイルはこちら
1.バージンオリーブオイルの等級
オリーブオイルの国際規格を定める「国際オリーブ協会(IOC)」では、「オリーブの実だけを原料にし、加熱や化学的な処理を行っていないもの」をバージンオリーブオイルと呼び、等級を細かく規定しています。とりわけ食用区分では、バージンオリーブオイルを3等級に分けています。
それらバージンオリーブオイルのなかで、特に「遊離酸度が0.8%以下で、風味に欠点がないもの」だけを「エキストラバージンオリーブオイル」と呼ぶことを認めています。それに次ぐ等級として、「遊離酸度0.8~2.0%かつ、風味に欠点がないもの」は「バージンオリーブオイル」と呼ばれます。
また、「遊離酸度2.0~3.3%以下のもの」は「オーディナリーバージンオリーブオイル」と呼ぶこととなっています。
このように、バージンオリーブオイルとひと口にいっても、その等級は非常に厳密に区別されていることが分かります。
2.ピュアオリーブオイルとは?
では、ピュアオリーブオイルとは何のことでしょうか?
エキストラバージンオリーブオイルと認められなかったバージンオリーブオイルの一部は、精製されて酸度を下げたり、欠点を取り除く処理が施されます。その処理をした結果、失われてしまうオリーブオイルの風味などを補うためにバージンオイルをブレンドして作られるのがピュアオリーブオイルです。
ピュアオリーブオイルは精製されたオリーブオイルが使われることから、エキストラバージンオリーブオイルとは全く異なるのです。
3.日本のエキストラバージンオリーブオイルは偽物が多い?
日本国内でささやかれる噂として「本物の『エキストラバージンオリーブオイル』はほとんど出回っていない」という説があります。この原因のひとつとして、先にご紹介した「国際オリーブ協会」が定める規格と、国内独自の「日本農林規格(JAS)」が定める品質規格が異なることが挙げられます。
日本農林規格(JAS)の規格では、食用オリーブ油は「酸価2.0以下」のものを「オリーブ油」、「酸価0.6以下」のものを「精製オリーブ油」と定めています。「オリーブを絞って抽出した油=オリーブ油」、「それをさらに精製したもの=精製オリーブ油」というざっくりとした分け方と考えると分かりやすいでしょう。(指標として使われる酸度と酸価は似たような単語ですが、異なる指標です。ここからも違いがわかりますね。)
国際オリーブ協会(IOC)が定める規格とは、基準も異なっています。世界基準のエキストラバージンオリーブオイルを味わいたい方や、より高品質なオリーブオイルを選びたい方は、国際オリーブ協会の基準を参照するとよいかもしれません。
ただ、国際オリーブ協会の基準を参照と言っても、スーパーなどで選ぶ際にはわかりにくいことでしょう。その場合は、ヨーロッパで作られたエキストラバージンオリーブオイルであることがひとつの目安と考えるとわかりやすいでしょうね。
【おすすめの使い方】

エキストラバージンオリーブオイルの使い方に、特別なルールはありません。一般的な油と同じように、炒め物や揚げ物の油として使うことができます。また風味がよいため、ドレッシングのようにサラダにかけたり、そのまま飲用したりすることもできます。
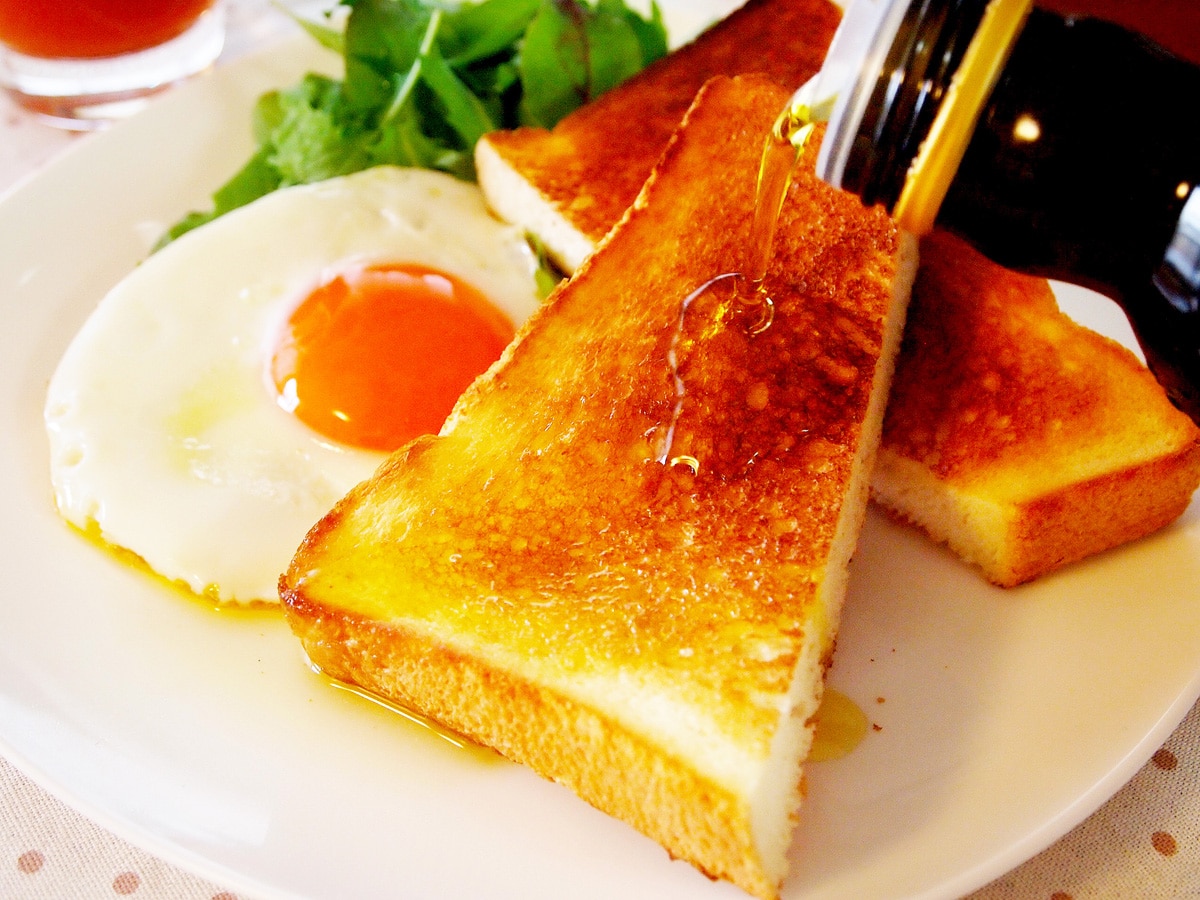
もっとも、揚げ物など長時間の加熱によって風味が失われる場合はあるでしょう。しかしその際にも、身体によいとされるオレイン酸自体は大きく変質しないため、健康を考えて摂る分には支障ありません。また、発煙温度も比較的高いことも加熱料理にも向いている理由として挙げられます。
同じエキストラバージンオリーブオイルと称されていても、フルーティーな香りを持つものや辛みを感じるものなど、製品によって風味は異なります。さまざまな産地や銘柄のものを試すなどして、ご自身のお好みに合うエキストラバージンオリーブオイルを探してみましょう。
>オリーブ果実100% 無ろ過(ノンフィルター)エキストラバージンオリーブオイルはこちら

エキストラバージンオリーブオイルは酸化しやすいため、ご自身で保管される際には必ず遮光性の高い瓶(茶色に着色された遮光ボトル)に入れたり、瓶をアルミホイルでくるむなどして、涼しく光の当たらない場所で保管しましょう。
【エキストラバージンオリーブオイルは健康にもよい?】

先にもご紹介しましたが、オリーブオイルに多く含まれる成分の1つに「オレイン酸」が挙げられます。オレイン酸は、悪玉コレステロールと呼ばれるLDLコレステロールの値を下げるといわれることで知名度の高い成分です。
バージンオリーブオイル(精製または工業的に処理されていないオリーブオイル)には、さまざまな抗酸化作用を持つ成分が豊富に含まれています。それらポリフェノールやカロテノイド、ビタミンEなどの抗酸化物質は、老化の原因とされる酸化物質を作る活性酸素を抑制するといわれています。
活性酸素自体は身体によくないものではなく、体内に微量あるレベルなら人体に有用といわれています。しかし、大量に生成されすぎると過酸化脂質を作り出し、動脈硬化やがん、免疫機能の低下などを誘発する可能性が指摘されています。
それらバージンオリーブオイルに含まれる抗酸化物質のなかでも、特にビタミンEが細胞膜に十分にあることで細胞の老化が予防できるといわれ、心身の若々しさを保ちたい方におすすめです。
また、オリーブオイルは緑黄色野菜と共に摂取することで、野菜に含まれる色素成分である「ベータカロテン」の体内への吸収を促すことが分かっています。ベータカロテンは体内でビタミンAに変化するため、皮膚・粘膜の健康維持に役立つことが期待できるでしょう。また、ベータカロテンにも抗酸化作用があるため、体内で活性酸素を抑制する働きが報告されています。
>オリーブ果実「生搾り」
無ろ過(ノンフィルター)エキストラバージンオリーブオイルはこちら
【日常にエキストラバージンオリーブオイルを取り入れていきましょう】

エキストラバージンオリーブオイルは香り高く風味がよいだけでなく、適量を継続的に摂取することでさまざまな効果が期待できる食材の1つです。
世界の各地で生産されているエキストラバージンオリーブオイルですが、産地によって風味や香りも異なります。各種を試すことで、さまざまな魅力を発見できるでしょう。ぜひご自身のお好みに合うエキストラバージンオリーブオイルを探し、豊かな食生活や美容・健康のために役立ててみてはいかがでしょうか。
<ダイニングプラスについて>
2001年事業開始、「dancyu」や「日経プラス1」など、メディア紹介多数。こだわりプロ愛用の美味しい海外食品を1パックからお届けする食品通販です。商社直営。
-
 【送料無料・ギフト包装】ベルデンソ 無ろ過 EXVオリーブオイル&ジャムギフト
【送料無料・ギフト包装】ベルデンソ 無ろ過 EXVオリーブオイル&ジャムギフト -
 【送料無料】ベルデンソ 無ろ過EXVオリーブオイル 3本セット
【送料無料】ベルデンソ 無ろ過EXVオリーブオイル 3本セット -
 ベルデンソ 無ろ過 エキストラバージン オリーブオイル 500ml オリタリア
ベルデンソ 無ろ過 エキストラバージン オリーブオイル 500ml オリタリア -
 モデナ産 バルサミコ酢 IGP 5グレープ 250ml (オリタリアブランド)
モデナ産 バルサミコ酢 IGP 5グレープ 250ml (オリタリアブランド) -
 薔薇のハーブソルト(ミル付き)
薔薇のハーブソルト(ミル付き) -
 信州サーモン 冷燻仕立て
信州サーモン 冷燻仕立て -
 肉厚の旨味 大粒ほたて貝(青森産 黄金ほたて) Lサイズ
肉厚の旨味 大粒ほたて貝(青森産 黄金ほたて) Lサイズ -
 ミニ カヌレ 7個入り
ミニ カヌレ 7個入り -
 りんごとカスタードのタルト 約21cm10カット フランス製 (タルトノルマンディー)
りんごとカスタードのタルト 約21cm10カット フランス製 (タルトノルマンディー) -
 石窯焼き パン オ セーグル (ライ麦パン)
石窯焼き パン オ セーグル (ライ麦パン) -
 ハーフバゲット 140g×2個入り
ハーフバゲット 140g×2個入り -
 ブレス産 AOP発酵バター 250g
ブレス産 AOP発酵バター 250g -
 ハモンセラーノ (200gパック)
ハモンセラーノ (200gパック) -
 パテ ド カンパーニュ ブロック (田舎風豚のパテ) スタンダード
パテ ド カンパーニュ ブロック (田舎風豚のパテ) スタンダード -
 【送料込み】欧州パンとこだわりのバターを愉しむ欲張りセット
【送料込み】欧州パンとこだわりのバターを愉しむ欲張りセット
アイスバインとはどんな料理?美味しい食べ方などをご紹介

ドイツの名品といえば、日本では自動車や刃物などヨーロッパ文化を感じさせる工業製品がよく知られています。しかし、ドイツの料理というと日本ではあまり馴染みがない印象をお持ちの方も多いでしょう。
そんな興味深いドイツの味覚のなかに、「アイスバイン」という料理があります。その名前を聞いただけでどのような食べ物か想像できる方は、まだまだ少ないかもしれません。アイスバインとは、いったいどのような料理なのでしょうか。
この記事では、ドイツを代表する料理の1つ「アイスバイン」の美味しい食べ方などをご紹介します。
【アイスバインとは】

アイスバインとは、ドイツを代表する家庭料理の1つです。特にドイツ北東部の大都市・ベルリンやその近郊では、非常に見かける機会の多い名物料理として知られています。
ローリエなどの香辛料(スパイス)と一緒に塩漬けした骨付きの豚すね肉に、香味野菜(ハーブ)を合わせてじっくりと煮込んだ料理がアイスバイン。また豚すね肉に限らず、骨付きの豚足を塩漬けにして燻製した料理も、アイスバインと呼ばれることがあります。
1.名前の意味は?
アイスバイン(eisbein)という名前の由来には、諸説あるといわれています。まずは、ラテン語で「坐骨」を意味する「os ischbeen」という名詞が名前の由来という説。
そして、ドイツ語で「Eis=氷」、「Bein=脚」ですから、かつて動物の骨をアイススケートの靴のエッジとして使用していたことが由来という説もあります。また、肉に含まれるゼラチン質がいったん煮込んでから冷えて固まると、氷のように見えるからという説もあるそうです。
2.アイスヴァインとの違いに注意
ちなみに、よく似た名前の食料品として「アイスヴァイン(Eiswein)」という、アイスバイン(eisbein)と非常に近い名称のドイツワインがあります。アイスヴァインは、凍らせたブドウの果実から作られた甘口の高級白ワインで、やはり本場ドイツでよく知られている名物です。
ドイツ国内のレストランや食料品店でそれぞれを頼むときには、発音に気を付けたり説明を付け足したりするなどして、混同を防ぐようにしましょう。
>特別な日にふさわしい輸入食品セール「クリスマス 2020」はこちら
【アイスバインの美味しい食べ方】
アイスバインは、日本ではまだそれほど馴染みがない料理です。しかし、このアイスバインを日本で美味しくいただくには、どのような食べ方がよいのでしょうか。ここでは、アイスバインを日本で美味しく食べられるおすすめの食べ方をご紹介します。
1.添え物をして

アイスバインはメインディッシュになる肉料理ですから、そのままでも美味しく食べることができます。しかし、さらに本場ドイツの味わいを楽しみたいなら、ザワークラウトや粒マスタードと、ゆでたジャガイモの付け合わせで食べるとドイツの家庭料理風に。
ザワークラウトといえば、こちらもドイツ名物の酸っぱいキャベツの漬物ですね。酸味のある付け合わせと一緒に食べることで、アイスバインが持つ味の深みがさらに増して美味しく食べられます。
また、アイスバインをさらにグリルしてカリカリになるまで焼き上げると、「シュバインハクセ(schweinshaxe)」という料理になります。外はこんがり、中はジューシーな食べごたえある肉料理がお好みなら、こちらの食べ方にもチャレンジしてみては。
2.ポトフやスープにして

アイスバインは骨付き肉を塩漬けしてあるため、ポトフやスープなどの煮込み料理の具材としても最適です。ポトフやスープにアイスバインを加えることで、野菜は肉のうま味を吸ってまろやかになり、豚肉のうま味を料理全体でしっかり味わえるはず。
また、アイスバインは香辛料(スパイス)で味付けして作られるため、塩味と豚肉のうま味に香辛料が加わることで、深みある味わいが楽しめます。アイスバイン自体に塩気があるため、調理で基本的に塩を加える必要はありませんが、もし足りなければお好みで塩を加えても問題ないでしょう。
3.お酒との相性も抜群

スパイシーなお肉料理に合うお酒といえば、やっぱりビールでしょう。ドイツを代表する家庭料理であるアイスバインですから、もちろんビールとの相性も抜群によいことで知られています。
せっかくなら、ドイツビールを手に入れてこだわりの本場の味を再現するのもおすすめ。
またアイスバインは塩漬けにしたハムのような加工肉の一種ですから、ワインと合わせてももちろん美味しく楽しめます。
【アイスバインはさまざまな楽しみ方ができる料理】
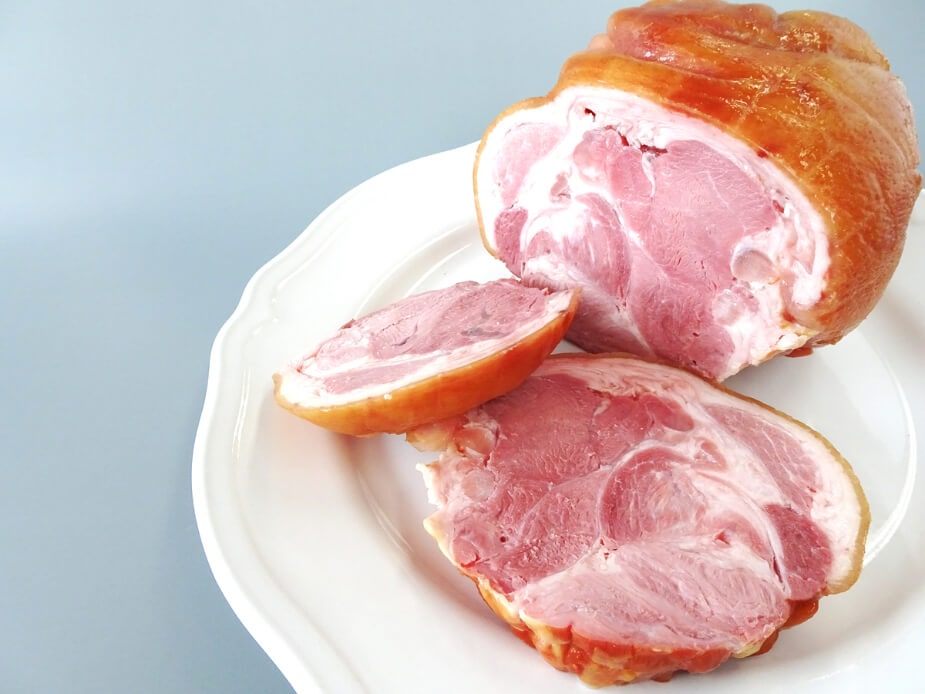
ベルリンやその近郊で、代表的な家庭の味として長く愛されているアイスバイン。そのまま食べて美味しいことはもちろんですが、さらに焼いたり煮たりしてもひと味違った美味しさが楽しめます。
ビールやワインなどのお酒にももちろん合いますから、その楽しみ方は実にさまざま。お肉をしっかり味わえるボリュームのある料理ですから、パーティーの際などにメインディッシュとして用意するのもおすすめです。
アイスバインはこってりとし過ぎない肉料理ですから、日本人も食べやすい一品。ぜひ一度、本格的なドイツの味覚を堪能してみてはいかがでしょうか。
<ダイニングプラスについて>
2001年創業、ミシュラン星付きレストランや有名高級ホテル愛用の上質な食材を1パックからお届けする食品通販です。商社直営。
-
 滋味あふれるスモークハム(ジャンボンプティ)
滋味あふれるスモークハム(ジャンボンプティ) -
 温泉塩の厚切りベーコン100g
温泉塩の厚切りベーコン100g -
 パテ ド カンパーニュ ブロック (田舎風豚のパテ) スタンダード
パテ ド カンパーニュ ブロック (田舎風豚のパテ) スタンダード -
 クリスマス シュトーレン 500g
クリスマス シュトーレン 500g -
 スティック プレッツェル 70g×2個入り
スティック プレッツェル 70g×2個入り -
 薔薇の花びら茶
薔薇の花びら茶 -
 ベラミーズパイシート フレッシュバター100% 300g
ベラミーズパイシート フレッシュバター100% 300g -
 ごろっと大粒ほたて(青森産 黄金ほたて)のコキーユ(グラタン) 8個入り
ごろっと大粒ほたて(青森産 黄金ほたて)のコキーユ(グラタン) 8個入り -
 焼くだけ!大きなクロワッサン 発酵バターが香るフランス産 Bake up生地 60g×4個入り
焼くだけ!大きなクロワッサン 発酵バターが香るフランス産 Bake up生地 60g×4個入り -
 三角 プレッツェル 85g×2
三角 プレッツェル 85g×2 -
 りんごとカスタードのタルト 約21cm10カット フランス製 (タルトノルマンディー)
りんごとカスタードのタルト 約21cm10カット フランス製 (タルトノルマンディー) -
バタープレッツェル 79g×2個入り
-
 ブレス産 AOP発酵バター 250g
ブレス産 AOP発酵バター 250g -
 【送料込み】欧州パンとこだわりのバターを愉しむ欲張りセット
【送料込み】欧州パンとこだわりのバターを愉しむ欲張りセット -
 【送料込み】ヨーロッパ ちょい呑みセット
【送料込み】ヨーロッパ ちょい呑みセット
発酵バターとは?特徴や使い方、使う際の注意点などをご紹介

お料理やお菓子作りで、日ごろからバターをよく使っている方も多いはず。バターにも、原料や製法の違いによっていくつかの種類があります。よく知られているのは塩を含んだ「有塩バター」と、塩を使用していない「無塩バター」の2種類でしょう。実はそれ以外に、発酵の有無でもバターの種類が区別されています。
発酵させたバターは一般的に「発酵バター」と呼ばれます。特に近年、通販などでも発酵バターが販売されているのを見かけることが多いでしょう。この記事では、従来のバターと発酵バターの違いや、発酵バターの特徴などについてご紹介します。
【発酵バターとは】

「発酵バター」とは、どのようなバターなのでしょうか。「発酵しているバター」であることは漠然と分かりますが、ここでは発酵バターの製法や従来のバターとの違いについてもご説明します。
>AOP認証 クリーミーなフランス産「発酵バター」はこちら
1.普通のバターとの違い
日本で一般的に販売されているバター(無塩バター、有塩バター)は、厳密には「甘性バター」と分類されるものです。非発酵(発酵を行わない)製法で作られている点が、甘性バターの特徴です。
甘性バターと比較して、発酵バターはバター特有の風味やコクが強く感じられる点が特徴。日本では甘性バターが一般的に使用される機会が多くなりますが、ヨーロッパでは発酵バターのほうが一般的です。
2.発酵バターの作り方
一般的なバターは、クリームをかき混ぜて乳脂肪分を分離させることで作られます。発酵バターは、殺菌したクリームに乳酸菌を混ぜて発酵させてから作ります。
ヨーロッパでは、紀元前からバターが作られ、使われていた記録も残っているそうです。古くから伝わる伝統的なバターの作り方は、原料の乳からクリームを分離し、チャーニング(かくはんすること)をする方法です。当時は乳を殺菌することなく使っていたことに加え、チャーニングにとても時間がかかったため、作っている間に発酵し、自然と発酵バターになっていました。
チャーニングには古くは皮や木製容器、陶器などが使われていましたが、中世頃になると専用のチャーン(かくはん器)が作られ、時代を経るごとに改良されていきます。19世紀になって遠心分離の技術が加わってからはクリームの分離が短時間でできるようになったことと、殺菌乳を使うことで発酵バターの独特の風味は失われていきました。
そこでヨーロッパではかつての発酵バターの美味しさを求めて、殺菌されたクリームに乳酸菌を加えて発酵クリームを作ってからバターを作るようになったのです。
特にEU諸国では、原料や工程・生産地域などの基準を満たすバター製品はAOP(原産地名称保護)認定を受けられる制度が整えられているなど、厳しい品質管理のもとに生産されている商品も数多くあります。
>AOP認証 フランスでも入手困難な「発酵バター」はこちら
3.発酵バターの使い方
従来のバターとは製法が異なる発酵バターですが、その使い方は普通のバターとほぼ同様です。従来のバターと同様に「有塩」と「無塩」に分けられているため、用途に合わせて使い分けることもおすすめです。
発酵バターは日本で一般的な非発酵のバターよりも、バター特有の風味が強く感じられる製品です。そのため、サブレやマドレーヌのようなシンプルな材料を使用したお菓子作りや、バターの風味を際立たせたい料理に使用することがおすすめです。もちろん、パンなどにそのまま塗って食べることも、よりバターの風味が感じられておすすめです。
【発酵バターは健康にもよい】

バターと聞くと、「脂肪分の塊」「健康のためには控えたほうが無難」というイメージを持ってしまう方も多いはず。しかし、バターそのものは決して健康に良くない食品ではなく、適量を摂取する分にはむしろ健康によい食品なのです。
特に発酵バターは、今話題の乳酸菌を含む発酵食品ですから、従来のバターと比較してより健康によい影響を与える効果が期待できます。ここでは、バターの健康への効果についてご紹介します。
1.腸内環境を整えてくれる
発酵バターの製造過程では乳酸菌を用いて原料のクリームを発酵させているため、基本的にはヨーグルトに近い健康効果も期待できるといわれています。つまり腸内の善玉菌を増やし、腸内環境を整えるはたらきがあるとされているのです。
2.ビタミンが豊富
バターにはビタミンA・ビタミンBなどの体調を整える栄養素が豊富に含まれています。これらのビタミンには、肌の健康を維持したり、動脈硬化などを防いだりする効果が期待できるとされています。また、抗酸化作用の強いビタミンEや、免疫力の向上に効果的なビタミンDなども、バターには含まれています。特にビタミンAやビタミンDのような脂溶性ビタミンは、バターの脂肪分とともに摂取することで体内に吸収されやすくなります。
>AOP認証 栄養豊富なフランス産「発酵バター」はこちら
【発酵バターを使う際の注意点】

ここでは、発酵バターを食用や料理用に使う際の注意点をご紹介します。発酵バターは一般的なバターと比較して鮮度が落ちるのが早いため、いったん開封したら早く使い切るようにしましょう。また、使用しないときは必ず冷蔵庫で保管するよう注意してください。
「バターは油性の食品なので傷みにくい」と思いがちですが、発酵バターは従来のバターよりも足が早く傷みやすい食品です。消費期限・賞味期限や保管方法には十分注意し、鮮度が落ちないよう気を付けながら使うようにしましょう。
【発酵バターを使って、料理をいっそう楽しみましょう】

従来のバターの代わりに発酵バターを料理やお菓子作りで使用すれば、いっそうバターの風味豊かな料理やお菓子を楽しむことができます。特にバター好きの方なら、バターの味がより芳醇で濃厚に際立つ発酵バターを選ぶことがおすすめでしょう。
また、発酵バターのデメリットは従来のバターよりも傷みやすい点なので、特に鮮度には気を配りながら発酵バターを上手に使うようにしましょう。
>AOP認証 ナッツのような風味のフランス産「発酵バター」はこちら
<ダイニングプラスについて>
2001年事業開始、「dancyu」や「日経プラス1」など、メディア紹介多数。こだわりプロ愛用の美味しい海外食品を1パックからお届けする食品通販です。商社直営。
-
 ブレス産 AOP発酵バター 250g
ブレス産 AOP発酵バター 250g -
 ブレス産 発酵バター ドゥミセル (加塩) 250g
ブレス産 発酵バター ドゥミセル (加塩) 250g -
 薔薇の花びら茶
薔薇の花びら茶 -
 2.6kg テルエルポーク 肩ロース ブロック
2.6kg テルエルポーク 肩ロース ブロック -
 信州サーモン 冷燻仕立て
信州サーモン 冷燻仕立て -
 解凍するだけ カナダ産 ムール貝
解凍するだけ カナダ産 ムール貝 -
 ミニ シリアルロール 44g×5個
ミニ シリアルロール 44g×5個 -
 フランス産 マカロン レッドフルーツ アソート 12個 (4種×各3個)
フランス産 マカロン レッドフルーツ アソート 12個 (4種×各3個) -
石窯焼き パン ド カンパーニュ (田舎風パン)
-
 ハーフバゲット 140g×2個入り
ハーフバゲット 140g×2個入り -
バタープレッツェル 79g×2個入り
-
 贅沢いちごジャム (プレザーブスタイル)
贅沢いちごジャム (プレザーブスタイル) -
 爽やかオレンジマーマレード
爽やかオレンジマーマレード -
 【送料込み】欧州パンとこだわりのバターを愉しむ欲張りセット
【送料込み】欧州パンとこだわりのバターを愉しむ欲張りセット -
 【サンプル セット】7種類のお食事パンお味見用セット
【サンプル セット】7種類のお食事パンお味見用セット
ライ麦パンは健康にいい?ライ麦パンの特徴や美味しい食べ方についてご紹介

朝食や、洋食の主食として食べられる機会が多いパン。パンといえば小麦から作られるものが一般的ですが、小麦以外の穀物から作られるパンもあります。その代表的なものが、名前を聞く機会も多い「ライ麦パン」でしょう。
この記事では、ライ麦から作られたパンである「ライ麦パン」の特徴や、美味しい食べ方についてご紹介します。ライ麦パンに「食べごたえがありそう」「ヘルシー」などのイメージを持っている方も多いでしょうが、果たして実際のところはどうなのでしょうか。
2-1 従来のパンより栄養価が高い
2-2 血糖値の上昇を穏やかにする
3-1 スプレッドを塗って食べる
3-2 サンドイッチにする
【ライ麦パンとはどんなパン?】

ライ麦パンとはその名前の通り、ライ麦から作られたパンを指しています。小麦から生産される一般的なパンと比較して食感が硬いため、「ハードパン」の一種として分類されています。それに対し、中間の硬さのパンは「セミハードパン」、やわらかいパンは「ソフトパン」となっています。
ライ麦パンは「ドイツパン」「黒パン」とも呼ばれ、ドイツをはじめとする寒冷地に属する国でよく作られ、食べられている点が特徴です。
冷涼な気候のドイツでは小麦の栽培が難しかったため、代わりにライ麦を使ってパンを作っていたそうです。その伝統から「ドイツパン」という別名が生まれたと考えられています。
またライ麦粉からはグルテンが出来ない一方、乳酸発酵させると粘りが出ます。それを利用して作られるのが、「サワー種」というライ麦粉と水だけでつくる酵母種によってつくられたライ麦パンです。そのため、従来の小麦のパンとは異なるずっしりと重量感ある仕上がりと、独特の酸味があることでも知られます。
以前は入手が難しかったライ麦パンですが、現在は街のベーカリーなどでも製造・販売され手に入れやすくなりました。また、純粋なライ麦パンとは異なりますが、ライ麦粉に小麦粉を混ぜることで、私たちの口に合うよう食べやすくしたパンも数多く生産されています。
>フランス産石窯「ライ麦パン」(冷凍パン)はこちら
【ライ麦パンは健康や美容にも効果的】

ライ麦パンに「ヘルシーなパン」というイメージをお持ちの方も多いでしょう。実際に、小麦粉で作られた食パンのような白いパンと比較し、ライ麦パンには健康によいとされる特徴がいくつかあります。
ここでは、ライ麦パンが健康や美容に効果的でヘルシーといわれる理由をご紹介します。
1.従来のパンより栄養価が高い
ライ麦パンは、ビタミンB類をはじめミネラル・食物繊維などの栄養素を豊富に含んでいます。従来の白いパンよりも栄養価が高く、噛みごたえがあって咀嚼回数が増えるという特徴も。これらのことから、少量でも満腹感が得られやすいというメリットも取りあげられています。そのため健康によいことはもとより、太りやすい成分を減らしながらバランスよく食べることでダイエットなどの美容面でも効果が期待できます。
2.血糖値の上昇を穏やかにする
ライ麦パンは「低GI食品」と呼ばれ、健康に悪影響のある血糖値の急上昇が起こりにくい食品の1つです。GIとは「Glycemic Index」を略した呼び名で、食後血糖値の上昇を表す指標です。
基本的に白米や白パンなど糖質を多く含む食品はGI値が高く血糖値を急に上げやすい性質がありますが、ライ麦パンは低GI食品のため食後の血糖値もゆるやかに上昇する特徴があります。
またライ麦パンはGI値が低いだけでなく、食パンなどと比較するとカロリーも低めです。ダイエット中などで糖質やカロリーを抑えたい場合も、おすすめの主食といえるでしょう。小麦粉の使用分量が少ないため、グルテンの摂取量も少なくできます。
>香ばしくヘルシー!フランス産石窯「ライ麦パン」はこちら
【ライ麦パンのおすすめの食べ方】

ライ麦パンの味の特徴としては、独特の酸味(酸っぱさ)が挙げられます。この酸味が得意ではないという方も、いるかもしれません。ここでは、ライ麦パンの風味が苦手な方でも美味しく食べられるおすすめの食べ方について、ご紹介します。
1.スプレッドを塗って食べる
スプレッド(塗り物)を塗って食べることで、独特の風味をカバーしながら食べることができます。
またクリームチーズ、ペースト、レバーパテなどを塗って食べるのもおすすめです。ハチミツやジャムなど、甘いものを塗って食べてももちろん美味しいはず。ワインやビールなどのお酒との相性もよいため、お酒のおつまみとして楽しむ方法も。
2.サンドイッチにする
パン自体の栄養価が高いため、チーズや野菜などを挟んで栄養満点のサンドイッチを作るのもヘルシーでよいでしょう。特に、ライ麦パンにはほのかな酸味があるため、チーズなど乳製品との相性は抜群です。乳製品がライ麦パンの酸味をやわらげ、マイルドな味わいになります。
それ以外でも、ハムやソーセージのような食肉加工品などとはよく合います。また酸味を生かすには、果物を挟みフルーツサンドのようにしていただく方法もおすすめです。
>ヘルシーでほどよい酸味が魅力の石窯「ライ麦パン」(冷凍パン)はこちら
【栄養満点なライ麦パンを美味しく食べよう】

ライ麦パンは非常に栄養価が高い食べ物で、食事や栄養のバランスに気を遣う方ならぜひ日常に取り入れたい主食の1つです。
風味に癖があってライ麦パンが苦手な方なら、小麦粉の含有量が多く口当たりのよいものを選んだり、食べ方を工夫したりすることでより美味しく味わうこともできます。
美味しく食べて健康をめざせるライ麦パンをぜひ食卓の定番にして、よりヘルシーな食生活を心がけてみませんか?
<ダイニングプラスについて>
2001年事業開始、「dancyu」や「日経プラス1」など、メディア紹介多数。こだわりプロ愛用の美味しい海外食品を1パックからお届けする食品通販です。商社直営。
-
 【送料込み】欧州パンとこだわりのバターを愉しむ欲張りセット
【送料込み】欧州パンとこだわりのバターを愉しむ欲張りセット -
 石窯焼き パン オ セーグル (ライ麦パン)
石窯焼き パン オ セーグル (ライ麦パン) -
 パテ ド カンパーニュ ブロック (田舎風豚のパテ)オーセンティック
パテ ド カンパーニュ ブロック (田舎風豚のパテ)オーセンティック -
 そのまま食べられるアボカドスライス130g
そのまま食べられるアボカドスライス130g -
 【電子レンジ対応】 エスカルゴ XLサイズ 12個入(殻付き/ガーリックバター入り)
【電子レンジ対応】 エスカルゴ XLサイズ 12個入(殻付き/ガーリックバター入り) -
 信州サーモン 冷燻仕立て
信州サーモン 冷燻仕立て -
 肉厚の旨味 大粒ほたて貝(青森産 黄金ほたて) Lサイズ
肉厚の旨味 大粒ほたて貝(青森産 黄金ほたて) Lサイズ -
 タスマニア産マスタード ホールシードタイプ
タスマニア産マスタード ホールシードタイプ -
 ビーフ100% ひき肉ステーキ(ステークアッシェ) 100g×2
ビーフ100% ひき肉ステーキ(ステークアッシェ) 100g×2 -
 焼くだけ!クロワッサン 発酵バターが香るフランス産 Bake up生地 40g×5個入り
焼くだけ!クロワッサン 発酵バターが香るフランス産 Bake up生地 40g×5個入り -
 りんごとカスタードのタルト 約21cm10カット フランス製 (タルトノルマンディー)
りんごとカスタードのタルト 約21cm10カット フランス製 (タルトノルマンディー) -
 贅沢いちごジャム (プレザーブスタイル)
贅沢いちごジャム (プレザーブスタイル) -
 ブレス産 AOP発酵バター 250g
ブレス産 AOP発酵バター 250g -
 ドイツ職人シリーズ 4種のソーセージ
ドイツ職人シリーズ 4種のソーセージ -
 【送料無料】ベルデンソ 無ろ過EXVオリーブオイル 3本セット
【送料無料】ベルデンソ 無ろ過EXVオリーブオイル 3本セット
シャルキュトリとはどんな食材?意味やおすすめの食べ方をご紹介

「シャルキュトリ」という食材についてご存じですか?その語感から、「フランス料理の食材かな」と思う方も多いはず。シャルキュトリという食材やその名前には、日本ではなかなか馴染みがないと感じるかもしれません。
しかし本場のフランスでは、シャルキュトリは食卓に欠かすことができない料理として愛されています。また、近年では日本でもシャルキュトリ専門店がオープンするなど話題を呼び、知名度が向上しつつあります。
シャルキュトリとは、どのような食材なのでしょうか。この記事では、フランスではお馴染みの食材である「シャルキュトリ」についてご紹介します。
【シャルキュトリとは】

シャルキュトリとは、肉を加工して食べることの多いフランスの食文化が生んだ食材カテゴリーの一つです。ちなみに一種類の食材のみを指すのではなく、ハムやソーセージをはじめ、パテやテリーヌなども含む「食肉加工品」を総称して「シャルキュトリ」と呼んでいるのです。
シャルキュトリのおもな原料は豚肉ですが、牛肉・鴨肉やその他の野生動物肉(ジビエ)が用いられることもあります。その製法は塩漬けや燻製、乾燥などが主体で、肉を長期にわたり保存するための手段として発達した食文化とされています。また、肉を加工して長持ちさせる文化には、古代ギリシャから続く長い歴史があるともいわれています。
次の項目からは、シャルキュトリとはどのような意味の言葉なのか、またシャルキュトリのくわしい製法についてもご紹介します。
1.シャルキュトリの意味
シャルキュトリ(シャルキュトリー、charcuterie)という名称の由来ですが、フランス語で「肉」を意味するchairと、「火を入れる」という意味のcuiteが語源であるといわれています。なお、肉に火を入れるという意味で名づけられてはいますが、必ずしも製造の過程で火を通すとは限らない場合もあります。
ちなみに同様の加工肉をドイツ語では「メツゲライ」、イタリア語では「サルメリア」と呼んでいます。そのため「メツゲライ」や「サルメリア」の名が冠された食肉加工品の販売店でも、シャルキュトリと同様の加工肉を購入できます。
また、シャルキュトリの販売店を「シャルキャトリ」と呼び、肉を加工する職人のことを「シャルキュティエ(女性の場合はシャルキュティエール)」と呼んでいます。
>フランスの多彩な「シャルキュトリ」お取り扱いございます
2.シャルキュトリの製法
シャルキュトリの原材料となる肉は、塊(かたまり)肉、ひき肉、内臓や血の3種に大きく分けられます。また、製法も加熱する方法があれば非加熱製法もあるなど、多岐にわたります。
シャルキュトリの製造に関するノウハウは「シャルキュトリ規定書」にまとめられており、それらの異なる製造方法によってさらに16種類に分けられています。
「シャルキュトリ規定書」は、「フランスシャルキュトリ・ケータリング・食肉加工工業連盟(略称:FICT)」と「シャルキュティエ・ケータリング・全国連合(略称:CNCT)」という、2つのフランス農水省の外郭団体が発行しています。
またシャルキュトリ規定書は、EUやフランスの食肉製品に関する規定に則って制作されており、原料や添加物などについてもこの書面で明確に定められています。フランスでシャルキュトリの生産に携わる人たちは規模の大小を問わずすべて、この規定書に基づいた製法を守ってシャルキュトリの生産を行っているのです。とはいっても、店や製造所による味や食感の個性が際立っていることも、シャルキュトリを楽しむうえで欠かせないポイント。ルールがありながら多様性が息づいているところにも、シャルキュトリという食材の奥の深さが現れているといえるでしょう。
シャルキュトリ規定書には450種類ものレシピが掲載されており、読めばじつに多様な種類のシャルキュトリがあることが分かります。これだけ多くのシャルキュトリのレシピがあれば、日本の食文化にもマッチする食べやすいシャルキュトリを見つけることもできるのではないでしょうか。
>気分はフランス旅行!日本では入手困難なフランスの「シャルキュトリ」はこちら
【シャルキュトリのおすすめの食べ方】

>ブーダンや生ソーセージなど、フランス産「シャルキュトリ」はこちら
シャルキュトリはフランスの食文化から生まれた食材だけに、ワインやチーズなどフランス名産とされている食材との相性が非常に良いことで知られています。また、ワインやチーズ以外の食材のなかでは、ビールやパンなどともよく合いますし、中には日本酒や焼酎と相性の良いものもあるでしょう。
食肉加工品は全般的にお酒との相性が良いものですし、特にソーセージやサラミ、パテなどの食材ならパーティーシーンでも活用しやすいでしょう。また、すでに加工が済んだ状態で販売されており、多くの製品は調理が不要な点も魅力です。買ってきたらすぐ簡単に食べることができる点も、シャルキュトリならではの長所といえそうですね。
【シャルキュトリはさまざまな形で楽しめる】

>ワインにぴったりのフランス産「シャルキュトリ」はこちら
シャルキュトリはさまざまな食肉加工品を総称した呼び名なので、種類によってその楽しみ方も多彩になります。シャルキュトリのなかでも、どんな製品が好みで何を口にする機会が多いかなども、人によってそれぞれでしょう。ご自身のお好みの味の製品を見つけるのも楽しいでしょうし、お気に入りを見つけたらそれに合った飲み物や付け合わせにこだわってみても食生活が豊かになりそうですね。
日持ちがして見栄えも良く、難しい調理なども要らないシャルキュトリは、テーブルを気軽に華やかにできる料理といえます。日常的にハムなどの加工肉に親しむ方もそうでない方も、フランスの食文化に触れる楽しさを知るべく、さまざまな種類のシャルキュトリを召し上がってみてはいかがでしょうか。
<ダイニングプラスについて>
2001年事業開始、「dancyu」や「日経プラス1」など、メディア紹介多数。こだわりプロ愛用の美味しい海外食品を1パックからお届けする食品通販です。商社直営。
-
 ブーダン ノワール 470g (豚の血と脂の腸詰)
ブーダン ノワール 470g (豚の血と脂の腸詰) -
 フランス産 生ソーセージ シポラタ 500g (50g×10本)
フランス産 生ソーセージ シポラタ 500g (50g×10本) -
 メルゲーズ ムートン 生ソーセージ 400g (国内加工)
メルゲーズ ムートン 生ソーセージ 400g (国内加工) -
 パテ ド カンパーニュ ブロック (田舎風豚のパテ)オーセンティック
パテ ド カンパーニュ ブロック (田舎風豚のパテ)オーセンティック -
 薔薇と和紅茶のティーバッグ
薔薇と和紅茶のティーバッグ -
 ベラミーズパイシート フレッシュバター100% 300g
ベラミーズパイシート フレッシュバター100% 300g -
 3種のチーズのキッシュ(タルトフロマージュサレ)
3種のチーズのキッシュ(タルトフロマージュサレ) -
石窯焼き パン オ セーグル (ライ麦パン)
-
 紫いちじくジャム
紫いちじくジャム -
 ポテトニョッキ 1kg
ポテトニョッキ 1kg -
 ベルデンソ 無ろ過 エキストラバージン オリーブオイル 500ml オリタリア
ベルデンソ 無ろ過 エキストラバージン オリーブオイル 500ml オリタリア -
 ブレス産 AOP発酵バター 250g
ブレス産 AOP発酵バター 250g -
 【送料込み】欧州パンとこだわりのバターを愉しむ欲張りセット
【送料込み】欧州パンとこだわりのバターを愉しむ欲張りセット -
 ドイツ職人シリーズ 4種のソーセージ
ドイツ職人シリーズ 4種のソーセージ -
 【送料込み】ヨーロッパ ちょい呑みセット
【送料込み】ヨーロッパ ちょい呑みセット
ピューレとは?ピューレとペーストの違いや使用方法をご紹介

「トマトピューレ」などの製品をはじめとする「ピューレ」という食品の名称を、一度は聞いたことがある方も多いでしょう。どのような状態の加工食品か、なんとなく想像できる方もいるかと思います。しかし実際に、ピューレとはどのような手順で加工された食品なのか、あるいはペーストやジャムとはどう違うのかなどをくわしくご存じの方は少ないかもしれません。
そこでこの記事では、ピューレという食品の概要やペースト・ジャムとの違いをはじめ、ご家庭でのピューレの作り方や、ピューレの使い方のアイデアについてご紹介します。
【ピューレとは】

>フランスの人間国宝がレシピ監修した「フルーツピューレ」(フランボワーズ)
ピューレ(ピュレ)とは、野菜や果物などの食材をすりつぶし、さらに裏ごしをして滑らかに整えた半液体状の加工食品を指す名称です。
食材によって加熱してからピューレにしたり、生のままをピューレにしたり、果物などの場合には砂糖を加えたり、様々なつくり方があります。 またピューレは、フランス語で「濾(こ)された」という意味を持つ言葉を語源としています。
料理用語などでは、食材を上記の製法でこす際に「ピューレする」「○○をピューレして」などと表現する場合もあります。また、料理名の一部として「○○のピューレ添え」などと使われているのも良く目にします。
1.ピューレとペースト・ジャムの違い
ピューレと似た加工食品に「ペースト」もあります。「トマトピューレ」と「トマトペースト」が店頭に並べられていて「どう違うのだろう?」と、思った経験がある方も多いでしょう。ピューレとペーストでは、そのレシピが若干異なるのです。
ペーストも、野菜や果物などの食材を煮詰めたりすりつぶしたりして、なめらかにしたものを指します。ただし、その製法でできたピューレをさらに煮詰めて、水分を飛ばすことで濃厚にしたものをペーストと呼んでいます。
また「ジャム」ですが、実は製法そのものはピューレとほとんど変わりません。ただし、原料をすりつぶさない場合もある他、原料中の成分などが加熱により変性したり、固まる作用のあるものを加えたりすることで、ゼリー状に固まった加工食品のことを指す場合が一般的です。
2.ピューレの作り方
ここでは、ピューレの作り方についてくわしくご紹介します。
基本的なピューレの作り方ですが、素材をミキサーなどでとろみが出る程度まで撹拌し、裏ごししてなめらかに整える方法でご家庭でも作ることができます。
トマトのように水分量が多くピューレ向きの野菜からいちごやオレンジのような果物まで、さまざまなものをピューレにすることができます。ご家庭にミキサーかフードプロセッサーがあれば、ぜひ試してみるとよいでしょう。
ピューレの保存方法ですが、冷凍庫に小分けにして入れておくのがおすすめ。必要なときに必要な分量だけを取り出して、手軽に使用することができます。もし食材をまとめ買いしたけれど生食では使い切れないようなときには、ピューレにして冷凍保存する方法も便利ですね。
3.ピューレの使い方
ピューレには「口当たりがなめらか」「水分量や甘さがほどよい」など、味や食感の面でも多くの料理やお菓子作りに使いやすい特徴があります。そのため、常備しておけば実にさまざまなジャンルの調理に活躍してくれます。
ここでは、バリエーション豊富なピューレの使い方のうち、ご自宅のレシピにも取り入れたくなるいくつかの例をご紹介します。
>フランスの人間国宝がレシピ監修した「フルーツピューレ」(マンゴー)

<ソースとして>
トマトピューレはスパゲッティやピザ、ラザニアなどイタリア料理のメニューに大活躍します。また、チキンライスの味付けをする際にケチャップの代わりに使えば、甘さを抑えながらトマトの酸味がひきたつさわやかで大人っぽい味わいに。ハヤシライスやラタトゥイユなど煮込み料理のソースや、トマト鍋スープのベースに使っても美味しい一品ができます。
<お菓子にも>
お菓子作りに使いやすいのは、いちごやりんご、マンゴーなどフルーツのピューレです。甘みを加えて炭酸水で薄めたドリンクなど簡単なものから、パフェやアイスクリームのソースや味付けにも。ゼリーやムースを作る際、味のベースとしてフルーツピューレを使うのもおすすめです。また、パイなど焼菓子のソースにしたり、スポンジケーキを重ねるとき間に塗ったりするなど、幅広い用途で楽しめます。ピューレを多めのゼラチンで固めて、フルーツ100%のグミキャンディを作れば、安心なお子様のおやつにもなりますね。
<水と調味料を加えてスープに>
ピューレのもっとも簡単で美味しくなる使い方といえば、水を加えて野菜ベースのスープやポタージュにする方法も挙げられますね。塩こしょうやブイヨンなどを足して自分だけの味付けができるため、塩分量の調整も自由にできてとてもヘルシー。トマトのほか、じゃがいもや枝豆、にんじん、かぼちゃなどをピューレにしておくと栄養価も彩りも満足のスープバリエーションを実現できます。
【ピューレを日常の料理にうまく取り入れましょう】

ピューレといえばトマトピューレが有名ですが、トマト以外の野菜やフルーツでも簡単に作ることができます。作る材料によって、使い方のバリエーションもさまざま。
特にご家庭で調理をしていて「もう一品何かほしい」と思ったとき、ピューレを冷凍などで常備しておけば思いついたときにサッと手軽なアイデア料理を実現できます。
ピューレがあれば、日常の料理やお菓子作りもより幅が広がるはず。ご家庭で作り置きすることも意外にむずかしくないため、ぜひご家庭でのお料理やお菓子作りにも野菜や果物のピューレを取り入れてみてはいかがでしょうか。
>フランスの人間国宝がレシピ監修した「フルーツピューレ」(マンゴー)
<ダイニングプラスについて>
2001年事業開始、「dancyu」や「日経プラス1」など、メディア紹介多数。こだわりプロ愛用の美味しい海外食品を1パックからお届けする食品通販です。商社直営。
-
 フランボワーズ (ラズベリー) 冷凍ピューレ 1kg
フランボワーズ (ラズベリー) 冷凍ピューレ 1kg -
 マンゴー 冷凍ピューレ 1kg
マンゴー 冷凍ピューレ 1kg -
 フレーズ (ストロベリー) 冷凍ピューレ 1kg
フレーズ (ストロベリー) 冷凍ピューレ 1kg -
カシス 冷凍ピューレ 1kg
-
 パッションフルーツ 冷凍ピューレ 1kg
パッションフルーツ 冷凍ピューレ 1kg -
 ベラミーズパイシート フレッシュバター100% 300g
ベラミーズパイシート フレッシュバター100% 300g -
 6種のベリー 北欧カフェデニッシュ 2個入
6種のベリー 北欧カフェデニッシュ 2個入 -
 フランス産 マカロン レッドフルーツ アソート 12個 (4種×各3個)
フランス産 マカロン レッドフルーツ アソート 12個 (4種×各3個) -
石窯焼き風 ライ麦パン(パン・オ・セーグル)
-
 モデナ産 バルサミコ酢 IGP 5グレープ 250ml (オリタリアブランド)
モデナ産 バルサミコ酢 IGP 5グレープ 250ml (オリタリアブランド) -
 ブレス産 AOP発酵バター 250g
ブレス産 AOP発酵バター 250g -
 ココア専門メーカーのこだわりココア (スプレードライ製法)
ココア専門メーカーのこだわりココア (スプレードライ製法) -
 【送料込み】欧州パンとこだわりのバターを愉しむ欲張りセット
【送料込み】欧州パンとこだわりのバターを愉しむ欲張りセット -
 【サンプル セット】7種類のお食事パンお味見用セット
【サンプル セット】7種類のお食事パンお味見用セット -
 《期間限定》キラキラ夏のアフタヌーンティーセット
《期間限定》キラキラ夏のアフタヌーンティーセット
プロシュットとは?生ハムとの違いやプロシュットの特徴をご紹介

ワインがお好きな方なら、プロシュットとチーズをお供にして飲む機会が多いのではないでしょうか。プロシュットはワイン好きの方ならこだわりたいおつまみの1つですが、生ハムとはどのような違いがあるのかご存じですか?
「プロシュットは生ハムの一種?」「生ハムのなかでも決まった特徴があるものをプロシュットと呼ぶの?」など、さまざまな疑問をお持ちの方もいるでしょう。そこでこの記事では、プロシュットと生ハムの違いや生ハムの産地についてご紹介します。
1 生ハムとは
1-1 プロシュットと生ハムの違い
3-1 DOPマークがあるかどうか
3-2 プロシュット・ディ・パルマの探し方
3-3 DOP以外の美味しいプロシュット
3-4 熟成期間を確認する
4-1 ハモン・セラーノ
4-2 金華火腿(金華ハム)
【生ハムとは】

生ハムとは、豚もも肉を塩漬けして乾燥させたものや、塩漬けしたあとに低温で燻製にした加工肉を指します。しっかりと加工されているため厳密にいえば生ものではありませんが、火を通していないという意味合いで便宜上「生ハム」と呼ばれているのです。
日本では近年になってドイツソーセージに次いで生ハムが取り入れられたため、低温燻製のドイツタイプの生ハムが一般的に作られてきました。 一方、イタリアやスペインでは長期熟成させるタイプが一般的です。
生ハムの歴史は古く、紀元前の時代よりエジプトやイラク周辺、中国などで作られていたと伝えられています。肉食文化を持つ地域で、塩を使って肉を長期保存できるように、という生活の知恵から生まれたのが「熟成」という方法でした。
そのため生ハムの味の特徴は、通常加熱で処理したハムよりも塩味が効いていること。この味わいがあってこそ、ワインを中心としたお酒とよく合うのですね。
では、プロシュットと生ハムには違いはあるのでしょうか。また、どのように異なっているのでしょう。次の項目では、生ハムとプロシュットの違いについてご紹介します。
1.プロシュットと生ハムの違い
プロシュット(prosciutto、プロシュート)とは、イタリア語ではハム全般のことを指しますが、日本では主に、イタリア産生ハムのなかでも燻製していないもの、熟成させたものをプロシュットと呼ぶことが多いようです。
プロシュットと呼ばれる熟成生ハムのうち、「世界三大生ハム」の1つに数えられるイタリア・パルマ産の「プロシュット・ディ・パルマ」は、世界的な生ハムの名品としてよく知られています。
プロシュット・ディ・パルマの特徴はパルマ産の白豚を使用している点と、1~2年ほどもかけて長期で乾燥・熟成させていることです。
上記の製法で生産されるパルマ産生ハムのなかでも、パルマハム協会が定めた厳しい条件をクリアした製品のみに「DOP(保護指定原産地呼称)」が与えられます。それらの銘柄だけが、プロシュット・ディ・パルマと名乗ることを許可されるのです。
イタリア産生ハムの名品としては、プロシュット・ディ・パルマのほかにも「プロシュット・ディ・サンダニエーレ」などがよく知られています。
全世界で生産されている生ハムのなかで、ことイタリア産のものについて「プロシュット」と呼ばれていると区別するとよいでしょう。日本ではさらに、「燻製しないイタリア産生ハム=プロシュット」であるという認識が一般化しています。
【プロシュットの特徴】
プロシュットは、味にクセが少なくどなたでも比較的食べやすい生ハムといわれています。長期熟成による香りの高さと、豚の皮を残したまま塩漬けする製法の特徴により、やわらかく滑らかな口当たりと程よい塩味が楽しめる点が多くの方に好まれています。
生ハムにメロンを合わせた食べ方は人気がありますが、プロシュットも薄くスライスしてメロンのように水気のある果物と合わせれば、よりその味わいの特徴を楽しめるでしょう。
メロンの他にいちじくや柿など季節にあわせて自分好みの果物とプロシュットとの組み合わせを見つけるのも楽しんでいただけるポイントです。もちろん、生ハムの塩気を活かしてサラダに入れたり、ピザやパスタにトッピングする食べ方もおすすめです。
【美味しいプロシュットの選び方】

イタリア人であれば、それぞれに信頼のおけるお気に入りのお店があって、その店主のおすすめのプロシュットを買うのが一番良い方法とされます。では、日本で美味しいプロシュット、名品とされるプロシュットを選ぶには、どのような点に気をつければよいのでしょうか。
美味しいプロシュットを見分けるには、以下に注目することがポイントです。
1.DOPマークがあるかどうか
DOPマークとは、先にもご説明した「DOP(保護指定原産地呼称)」が与えられた商品につけられるマークです。このマークがあれば「イタリアの名産地で作られたプロシュット」であることを容易に判断できます。
2.プロシュット・ディ・パルマの探し方
「プロシュット・ディ・パルマ」を見つけたい場合は、「パルマ公爵の王冠の焼き印」が捺されていることを確かめましょう。この焼き印があれば品質が保証されていると判断でき、正真正銘のプロシュット・ディ・パルマであることがわかります。
ただし、これは原木と呼ばれるスライス前の状態でのお話しです。 プロシュット・ディ・パルマは、一旦スライスされてしまうと、元々その王冠の焼き印が記されていたかどうかはわからなくなってしまうため、パルマハム協会ではパルマ地域でスライスされたものだけを正当なプロシュット・ディ・パルマとしてDOPマークをつけること、と厳しく規定しています。
一方、王冠の焼き印がついたパルマハムを原木で仕入れて日本国内でスライス加工されたプロシュットに関しては協会の規定によって「パルマ」の名前を使うことができません。
スライスの鮮度を重要視した結果、日本国内でスライスしているものもたくさんあり、その場合は商品説明においても「パルマ」という文字を使用することすらできません。
つまり、商品名や商品説明からはプロシュット・ディ・パルマであることはわかりません。その際の目安になるのが熟成期間です。パルマハム協会が定めているプロシュット・ディ・パルマの熟成期間は最初の塩漬けから12ヶ月以上です。それ未満の熟成期間のものはプロシュット・ディ・パルマではないことがわかります。
3.DOP以外の美味しいプロシュット
生ハムの売り場を気を付けて見てみると、実に多くの種類のプロシュットが売られているのに気づきます。
「プロシュット・ディ・パルマは美味しい」けれど「プロシュット・ディ・パルマは高い」というジレンマはイタリア人にとっても同じです。そこで近年作られて人気が高まってきているのがDOP以外のプロシュットです。
同じパルマ地方でプロシュット・ディ・パルマと同じ製法で作られても原料の豚肉がイタリアの他の地域や、ヨーロッパの他の国を産地とするものを使ったプロシュットは「プロシュット・ディ・パルマ」とは呼べません。
ところが、これらのプロシュットの中にはプロシュット・ディ・パルマと似たような美味しさを感じることができるものも多くあります。
それらを見分けるためには原材料を確認するのがわかりやすいでしょう。プロシュット・ディ・パルマ(および豚肉原産国違いのプロシュット)の原材料はとてもシンプルで「豚肉」と「食塩」だけで、他のものは一切使用しません。
4.熟成期間を確認する
美味しいプロシュットのなかでも、特に美味しいとされるものは「熟成期間が18ヶ月程度」と覚えておくとよいでしょう。このくらいの熟成期間のプロシュットならクセもなく、美味しく食べることができるはずです。
もちろん、できるだけ賞味期限が近づいていない新鮮なものを選ぶことや、保存方法を確認することもお忘れなく。
生ハムと合わせるワインにこだわる方の場合は、ワインの産地に合わせてプロシュットの産地を選ぶ方法もおすすめです。
【プロシュット以外の生ハム】

プロシュットはイタリア産の生ハムのことを指していますが、もちろんプロシュット以外にも世界各国で生ハムは生産されており、多くの種類があります。 ここではプロシュット以外の生ハム、特にプロシュット・ディ・パルマと同様に「世界三大生ハム」と呼ばれる2つの生ハムをご紹介します。
1.ハモン・セラーノ
ハモン・セラーノの「セラーノ」とは山のことで、スペインの山岳地帯で作られた生ハムをこう呼んでいます。産地の特徴から「山のハム」とも呼ばれることがあります。
ハモン・セラーノの製法の特徴は、豚肉の皮の大部分をはいでから塩漬けすること。そのため塩分が強くなり、お肉の味がしっかり凝縮されてコクのある味わいに仕上がります。
スペイン産の生ハムとしては、ハモン・セラーノのほか「イベリコ豚」を使用した「ハモン・イベリコ」などもよく知られています。
2.金華火腿(金華ハム)
「世界三大ハム」の残り1つは、中国の浙江省で作られる「金華火腿(金華ハム)」。肉の断面が赤い見た目の特徴から、「金華火腿」と名付けられています。
金華火腿の食べ方の特徴は、基本的には生で食べないこと。硬く塩味も強いため、そのままでは食べることがむずかしいのです。スープの出汁にしたり、酒蒸しして料理に添えたりするなど、味にアクセントを加える使い方が主流となります。
【プロシュットの特徴を知って、料理に合うものを選ぼう】

プロシュットは、さまざまな生ハムのなかでも味にクセが少ないことで多くの料理やワインに合わせやすい生ハムです。
プロシュットの特徴を知っていれば、上手に選んで料理やお酒に合わせながらより美味しく味わえますね。熟成期間によっても味わいが微妙に変化しますから、さらにこだわりたいという方なら産地や熟成期間などの知識も身につければ、もっとプロシュットを楽しめるはず。
<ダイニングプラスについて>
2001年事業開始、「dancyu」や「日経プラス1」など、メディア紹介多数。こだわりプロ愛用の美味しい海外食品を1パックからお届けする食品通販です。商社直営。
-
 フランス伝統生ハム IGP ジャンボン ド バイヨンヌ 200g
フランス伝統生ハム IGP ジャンボン ド バイヨンヌ 200g -
 ハモンセラーノ (200gパック)
ハモンセラーノ (200gパック) -
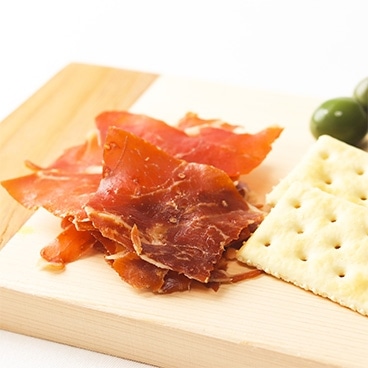 新食感!旨み凝縮生ハムジャーキー 30g
新食感!旨み凝縮生ハムジャーキー 30g -
 生ハム切り落とし ボリュームパック スペイン産
生ハム切り落とし ボリュームパック スペイン産 -
石窯焼き風 ライ麦パン(パン・オ・セーグル)
-
 薔薇のハーブソルト(ミル付き)
薔薇のハーブソルト(ミル付き) -
 プレミアム タルト オ ポワール 550g (直径約 21cm 8カット)
プレミアム タルト オ ポワール 550g (直径約 21cm 8カット) -
 そのまま食べられるアボカドスライス130g
そのまま食べられるアボカドスライス130g -
 ごろっと大粒ほたて(青森産 黄金ほたて)のコキーユ(グラタン) 8個入り
ごろっと大粒ほたて(青森産 黄金ほたて)のコキーユ(グラタン) 8個入り -
 3種のチーズのキッシュ(タルトフロマージュサレ)
3種のチーズのキッシュ(タルトフロマージュサレ) -
 紫いちじくジャム
紫いちじくジャム -
 ポテトニョッキ 1kg
ポテトニョッキ 1kg -
 薪窯ナポリ風ピザ マルゲリータ 200g
薪窯ナポリ風ピザ マルゲリータ 200g -
 【送料込み】欧州パンとこだわりのバターを愉しむ欲張りセット
【送料込み】欧州パンとこだわりのバターを愉しむ欲張りセット -
 【送料込み】ヨーロッパ ちょい呑みセット
【送料込み】ヨーロッパ ちょい呑みセット